
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...


ふるさと納税とは、自分の故郷や「応援したい」と思う自治体に対し、寄付ができる制度です。寄付に対して、返礼品や所得税の還付や住民税が控除される恩恵があります。
返礼品は寄付した先の自治体ごとに特色があり、バラエティ豊かな地元の特産物・名産品が楽しめるのも特徴。飲食物や家電製品・体験型アクティビティのサービス・伝統工芸品などがあり、減税目的はもちろん、返礼品を楽しみとしてふるさと納税の人気が高まっています。
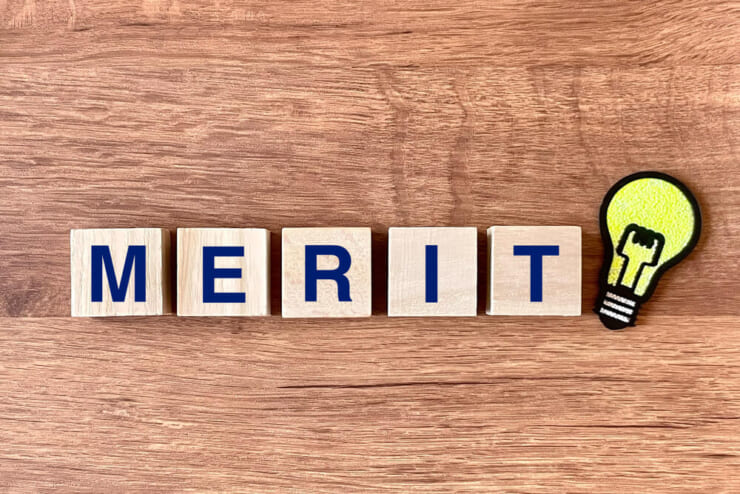
ふるさと納税といえば、地域のバラエティ豊かな返礼品。しかし、ふるさと納税には返礼品以外にも、以下のような大きなメリットがあります。
それぞれ詳しくチェックしていきましょう。
ふるさと納税をすると、税金の控除をうけることができます。しかし、「聞いたことはあるけれど、具体的な仕組みはよくわからない」という方も多いようです。
ふるさと納税(寄付)をすると、寄附額のうち2,000円(自己負担額)を越える部分について、所得税と住民税が控除されます。
ただし、ふるさと納税をすればするほど無制限に控除がうけられるわけではありません。本人の所得に応じて、控除の上限額があることを知っておいてください。
上限額内で、①②③の合計金額の控除を受けられます。2,000円は、自己負担額です。
| 住民税から控除を受けられる金額 計算式 (ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除) |
|---|
| ①(ふるさと納税額-2,000円)×10%・・・・・・基本分
②(ふるさと納税額-2,000円))×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)・・・・・・特例分 |
| 所得税から控除を受けられる金額 計算式 (ふるさと納税を行った年の所得税から控除) |
|---|
| ③(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。 |
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」
ふるさと納税の本来の目的は、「好きな自治体に寄付をする」ことです。
通常、所得税は国に、住民税は住民票のある自治体に納めます。
ふるさと納税は「寄付金」として希望する自治体に支払う制度ですが、支払った分のうち一定額が、後で所得税や住民税の控除という形で戻ってくる仕組みです。
つまり、実質的には自分の税金の一部を、応援したい自治体に振り向けられる制度といえます。
「自分の故郷やゆかりのある場所を応援したい」、その思いをかたちにできる制度が「ふるさと納税」といえるでしょう。
ネットやテレビでも話題になる返礼品は、ふるさと納税の楽しみの最たるもの。実質自己負担額の2000円で、自治体からの返礼品を受け取ることができます。
返礼品は地域ごとに特色があり、地元の名産品から、その地域に工場を持つ大手家電メーカーの商品・体験型サービス・服飾・雑貨など多岐にわたります。返礼品を選ぶ楽しさも「ふるさと納税」の魅力の一つです。

本人の収入や家族構成によって、ふるさと納税で控除を受けられる上限額(限度額)は異なります。
また、アパートやマンション経営、不動産投資などで不動産所得がある場合は、所得が増える分だけふるさと納税の限度額も高くなります。
一方で、マンション経営や不動産投資が赤字の場合は、所得が減る分だけ限度額も低くなります。
ここからは、それぞれのケースについて具体例を挙げて説明していきます。
例として以下の条件で計算します。
この場合の総所得は給与所得の276万円と不動産所得300万円を合わせた576万円になります。
給与所得:400万円(給与収入)ー124万円(給与所得控除)=276万円
不動産所得:400万円(不動産収入)-100万円(不動産にかかる経費)=300万円
また総所得から基礎控除48万円(令和6年)、配偶者控除38万円、社会保険料控除60万円(給与収入400万円×15%)を差し引いた、課税所得は430万円となります。
給与以外に収入がある場合のふるさと納税上限額計算には以下の式を使います。
| 個人事業主の上限額 計算式 |
|---|
| 住民税所得割額×課税所得に応じた変数(%)+2,000円 |
「住民税所得割額」は、自治体が発行する「住民税決定通知書」に記載されています。住民税決定通知書は、毎年5月・6月頃に、住民票のある自治体から送付されるものです。
「課税所得に応じた変数(%)」は、以下の表でチェックします。
これによると課税所得が430万円の場合の変数は28.744%であることから、住民税所得割額が43万円(※)とすると、ふるさと納税上限額は約12万5000円(43万円×28.744%+2000円)になります。
ちなみに給与収入400万円のみの夫婦世帯のふるさと納税上限額は約3万3000円(参照:総務省サイト)であることから、不動産所得が300万円加わることでふるさと納税の上限額は約9万2000円増加したことになります。
※正確な額は「住民税決定通知書」の通りですが、ここでは課税所得の10%を仮の住民税所得割額として計算しています。
| 課税所得に応じた変数 | 課税所得金額 |
|---|---|
| 23.559% | 195万円まで |
| 25.066% | 195万円から330万円 |
| 28.744% | 330万円から695万円 |
| 30.068% | 695万円から900万円 |
| 35.520% | 900万円から1,800万円 |
| 40.683% | 1,800万円から4,000万円 |
| 45.398% | 4,000万円以上 |
※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
こんな悩み、抱えていませんか?
こうした悩みがある場合は、手軽に試せる不動産一括査定がおすすめです。
今の家がいくらで売れるか不安で、新しい住まい探しに踏み切れない
税金や名義変更の手続きも含め、何から始めればいいのか分からない
会社によって売却額が数百万円変わると聞き、選び方で損をしないか心配
簡単な質問に答えるだけで最大6社があなたの物件価値をしっかり査定します。その中から「信頼できる一社」を見つけて理想的な不動産売却を実現させましょう。

不動産収入を経費が上回り不動産所得がマイナスの場合、ふるさと納税の上限額にどのような影響があるのでしょうか。先ほどの例で不動産に経費が500万円かかった場合の計算をしてみます。
この場合の総所得は給与所得の276万円から不動産所得の赤字分100万円を引いた176万円になります。
給与所得:400万円(給与収入)ー124万円(給与所得控除)=276万円
不動産所得:400万円(不動産収入)-500万円(不動産にかかる経費)=-100万円
また総所得から基礎控除48万円(令和6年)、配偶者控除38万円、社会保険料控除60万円(給与収入400万円×15%)を差し引いた、課税所得は30万円となります。
先ほどの表より課税所得が30万円の場合の変数は23.559%であることから、住民税所得割額が3万円(※)とすると、ふるさと納税上限額は約9000円(3万円×23.559%+2000円)となり、不動産所得のマイナスの影響はふるさと納税の上限額にも大きな影響を与えることが分かります。
※正確な額は「住民税決定通知書」の通りですが、ここでは課税所得の10%を仮の住民税所得割額として計算しています。
ふるさと納税の各ポータルサイトでは、給与収入と配偶者の有無の入力でできる控除上限額シミュレーションが用意されています。扶養家族の人数も考慮した詳細シミュレーションもあるので、手軽でおすすめです。

返礼品を受け取れ、税の控除を受けられるなどお得に思えるふるさと納税ですが、いくつか注意点があります。
後から「こんなはずじゃなかったのに」とならないためにも、ふるさと納税のメリットだけでなく、デメリットも知っておきましょう。
「ふるさと納税=節税」と思われがちですが、正確には節税ではありません。
実際には、翌年度に支払うはずの税金の一部を、ふるさと納税という形で先に納める(前払いする)仕組みです。
寄付した金額のうち2000円を超える部分は、所得税や住民税から控除されるため、結果的に税負担は変わりません。
ただし、2000円の自己負担で返礼品を受け取れることから、「節税したように感じる」人が多いのです。
ふるさと納税の返礼品が高額の場合、課税対象になる場合があります。具体的には返礼品の合計額が年額50万円を超える場合は「一時所得」として、超えた部分について課税対象になります。
ふるさと納税を選ぶのは楽しくつい高額になりがちですが、返礼品の合計額が年間50万円を超えないように注意してください。
ワンストップ納税制度とは、会社で年末調整を受けており、他に申告すべき所得がない会社員が、年間5自治体以内にふるさと納税を行った場合に確定申告が不要になる制度です。ワンストップ特例制度によって、会社員などの給与所得者は確定申告の手間がなくなり、手軽にふるさと納税を楽しめるようになりました。
ただし、不動産に限らず給与以外の所得が20万円以上の会社員は、そもそも確定申告が必要となりますのでワンストップ納税はつかえません。不動産所得が年間20万円を超える方はご注意ください。
不動産所得がある場合は、その分所得が増えるため、ふるさと納税で控除を受けられる上限額も高くなります。
上限の範囲内で寄付を行えば、所得税や住民税の控除を受けつつ、各地の魅力ある返礼品も楽しめるのが、ふるさと納税の大きな魅力です。
ふるさと納税を正しく理解し、上手に活用しましょう。
