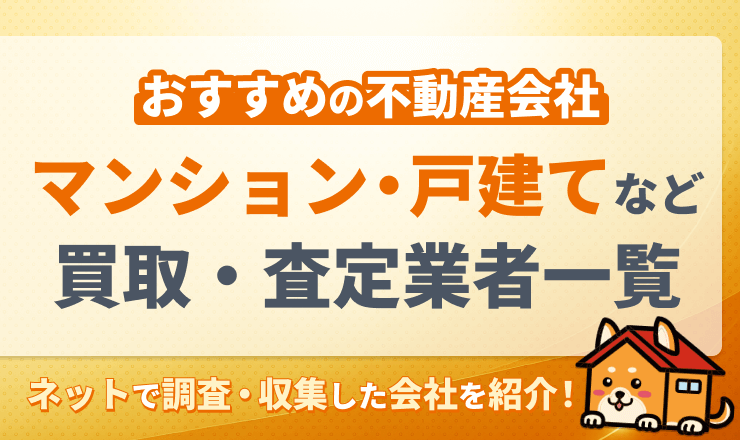
-
東久留米市でおすすめの不動産(マンション・戸建て・土地)買取...


減価償却(げんかしょうきゃく)とは、マンションなどの住宅が経年劣化により価値が下がった分を金額として表す会計処理のひとつです。
事業をしている場合にも、機器類に対して減価償却費用を計算しますが、マンションと比較すると「減価償却」の意味が異なります。
| 事業用機器 | 居住用マンション |
|---|---|
|
|
マンション売却で得た収入金額からマンション購入代金を経費として計上できますが、マンションの価値は経年劣化によって年々下がるため、全額を計上できません。特別な会計処理が必要となるので正しい減価償却の方法を理解しておく必要があります。

マンション売却で税金がかかるかどうかは、譲渡所得の有無によって異なります。譲渡所得を計算する際は、計算式に減価償却を使用するため、減価償却についての理解を深めておくことは大変重要です。
税制上、マンションなどの建物や土地は以下のように判断します。
【税制上におけるマンションの内訳】
| マンションが建っている土地部分 | 経年劣化しない |
|---|---|
| マンション本体部分 | 経年劣化する |
会計処理では、土地については、ときが経っても劣化しないという判断である一方、その上に建つマンションなどの建造物については、築年数を経るごとに建物が劣化するという考え方が一般的です。
居住用に限らず投資用にマンション1棟を土地ごと購入していた場合でも、減価償却できるのは建物部分のみです。
不動産を売却したときに利益が発生すると、譲渡所得税と呼ばれる税金が発生します。
譲渡所得税
譲渡所得に応じて納める税金のこと。
土地や不動産、株式などの売却で出た利益が課税対象。譲渡所得税は、通常の給料や事業で得た売上などの所得とは分離して課税されます。
不動産売却においては、売却することで利益が出る場合と、出ない場合があります。
【譲渡所得税を導き出す計算式】
上記の式の中に、「取得費」というものがあります。
減価償却費は建造物部分を購入した際の費用の95%が限度と決まっており、購入時の代金5%分は、取得費として計上可能です。
以上のことからも、一般的な譲渡所得を計算する際に必要な取得費を正しく把握するために減価償却費を算出しなければなりません。
なお、以下のような条件下で不動産を売却し、算出された譲渡所得がマイナスになる場合は、確定申告することで税金の軽減が適用される可能性があります。
【譲渡所得がマイナスになった際に受けられる措置】
マンションの場合、購入時期によって減価償却費の算出方法が異なります。
【減価償却の計算方法】
それぞれの特徴を以下の表を引用し、ご紹介します。
| 定額法 | 定率法 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。 |
| 計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。)ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。 改定取得価額×改定償却率 |
出典:nta.go.jp
原則、毎年同額を納めることになる定額法よりも、経過年数とともに納める金額負担が減少する定率法のほうが、減価償却費の納税ペースが速いことがわかります。
実際に数字を使って見てみましょう。
2,000万円が購入原価のマンションを4年後に減価償却した際、定額法と定率法では以下の違いがあります。
詳しい計算方法については後述しますが、定額法と定率法の計算式と税額の違いを確認しましょう。
| 定額法 | 定額法:2,000万円×0.25=500万円 |
|---|---|
| 定率法 | 定率法:2,000万円×0.625=1,250万円 (期首残存価額×定率法の償却率) |
現在は法改正により、1998年4月以降に購入したマンションを売却する際は、定額法のみ適用可能です。
さらに、2007年(平成19年)の税制改正により定額法の計算方法も刷新されており、自宅用のマンションの場合はこれまでの計算方法(旧定額法)が採用されています。
特別な届出をしていない場合は、旧定額法での計算となることを覚えておくと役立ちます。
減価償却の計算において、建物がいつまで使えるかというのは、国税庁が定める建材によって変化する法定耐用年数をもとにすることを覚えておかなければなりません。
税制上、法定耐用年数と減価償却する資産種別ごとにモノの価値が減少する早さが決まります。法定耐用年数では、主に以下の3項目に注目が必要です。
【法定耐用年数で見るべき主な要素】
自分で調べる場合は、国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表というサイトが参考になりますが、自分で調べてもわからないものは、最寄りの税務署に聞くことをおすすめします。
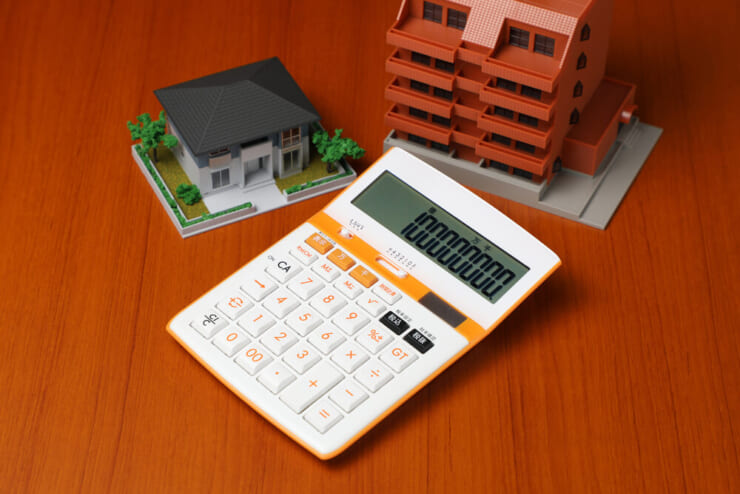
自宅用のマンションを売却する場合の主な計算方法はもちろん、必須項目の調べ方を把握していると、実際に売却する際に役立ちます。
減価償却費は以下の計算式で算出します。
【減価償却費の計算式】
※0.9=建物の購入費用から残存価額(購入費用の10%)を差し引いた金額にするために、かけ合わせられている数字
それぞれの項目に数字を当てはめる際は、自身で以下の項目を算出しなければなりません。
【自分で調査、計算が必要な項目】
上記の3項目は、以下の5ステップで算出可能です。
それぞれについて数字を用いながら、わかりやすくご紹介します。
マンションを購入する際は、土地代も込みで購入することが一般的です。マンションの場合は前述の通り、建物の部分のみが納税上の計上対象となることから、土地代とされている部分を抜粋しなければなりません。
土地代を除いた純粋な建物購入代金を自分で調べるには、以下の4つの調べ方があります。
【マンションの建物購入代金の調べ方】
もし、自力で上記4つの方法で調べてみても不明な場合は、不動産会社や専門家へ相談して建物購入代金を算出してもらうと安心です。
まず、マンションを購入した際の売買契約書内に、土地と建物の代金がどのように記載されているか確認しましょう。
価格が土地と建物で金額の記載がわかれている場合は、売買契約書に記載されている内容をそのまま活用できます。
もし、記載がわかれていないという場合は、以降の方法で土地代金と建物代金をわけて計算しましょう。
売買契約書を見た際に土地代金と建物代金が一緒になっていた場合は、最初に消費税から建物代金を計算する方法を試してみましょう。消費税から建物代だけを算出できるとする理由は、土地は非課税だからです。
建物代金のみの消費税は、以下のように算出します。
【消費税から建物代金を算出する計算式】
売買契約書に記載の消費税÷消費税率+消費税=建物購入代金
なお、税率は購入した年の税率が適用となるため、注意が必要です。
| 消費税率 | |
|---|---|
| 1989(平成元)年4月1日~1997(平成9)年3月31日まで | 3% |
| 1997(平成9)年4月1日~2014(平成26)年3月31日まで | 5% |
| 2014(平成26)年4月1日~2019(令和元)年9月30日まで | 8% |
| 2019(令和元)年10月1日~ | 10% |
以上を踏まえて、2018年(平成30年)に3,000万円で購入したマンションの建物代金を例に算出してみましょう。
個人の売主からマンションを購入した場合、売買契約書に消費税の記載がないことがあります。
このような場合は、国土交通省が毎年発表している「標準建築単価」から算出する方法を活用することで算出可能です。
国税庁からもチェックできますので、以下のリンクを参考にしてみてください。
参考:国税庁「【参考2】1 建物の標準的な建築価額表」
「標準建築単価」をもとに、建築年数と構造で使われる建材から、1平方メートルの建築価格を算出していきます。
【計算式】
こちらも、事例を交えてみましょう。売ろうとしているマンションが、以下の条件だとします。
【売却予定のマンションスペック】
条件と計算式を代入すると、以下のようになることがわかります。
【事例における計算式】
1~3までの調べ方で建物代金が算出できないという場合は、固定資産税評価額から調べる方法もあります。
固定資産税評価額とは地方自治体へ納税する固定資産税の基準となる価格のことで、土地と建物それぞれで定められています。春ごろに地方自治体から届く固定資産税の納税通知書で確認可能です。
計算方法は以下の通りですが、初心者には複雑であることから、固定資産税評価額から建物代金を算出する際は、なるべく不動産会社の担当者や専門家に相談することをおすすめします。
【建物代金を固定資産税評価額から算出する方法】
マンションの購入代金が算出できたら、建物の購入代金以外の費用を算出しましょう。具体的には、動産を取得したときの物件の購入金額と諸費用を算出していきます。
| 土地と建物の取得にかかる費用 ※金額を土地分の価格と建物分の価格に分ける(按分する) |
|
|---|---|
| 建物の取得にかかる費用 | リフォーム |
一例として、以下の場合における購入代金以外の費用を算出してみましょう。
土地:建物が4:6の割合だとすると、計算は以下のようになります。
【計算例】
ただし、取得費といってもすべて費用換算できるとは限りません。特に、業所得などの必要経費にプラスしたものは、取得費に含めることができないため、注意しなければなりません。以下に代表例をまとめましたので、ご覧ください。
【取得費として計算できない費用の一例】
続いて、マンションの償却率を調べます。
償却率を計算するには、マンションの法定耐用年数を算出した後、国税庁が発表している表をもとに用途や構造・経過年数を当てはめ、合致する償却率を調べなければなりません。
償却率は、以下のサイトで確認可能です。
参考:国税庁「「減価償却費」の計算について」
以下に代表的な建材の償却率を引用・提示します。
| 建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 | |
|---|---|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 | |
| れんが造、石造又はブロック造 | 57年 | 0.018 | |
| 金属造 | 骨格材の肉厚4mm超 | 51年 | 0.020 |
| 骨格材の肉厚3mm超4mm以下 | 40年 | 0.025 | |
| 骨格材の肉厚3mm以下 | 28年 | 0.036 | |
| 木造又は合成樹脂造 | 33年 | 0.031 | |
| 木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 | |
マンションを購入してから売却するまでの所有期間の年数が、経過年数です。経過年数を算出する際は、端数によって以下のように切り上げるか、切り捨てるかが異なります。
【経過年数の切り上げ、切り捨て】
ちなみに、マンションを保有している間にリフォームをした場合は、リフォームが完了した日から数えた経過年数で個別計算が必要となります。つまり、マンション購入日とまとめて計算しないできちんと分けて計算するということを覚えておくと安心です。
1~4で調査した各数字を、減価償却費の計算式に代入していきます。自宅用のマンションを売却する場合の主な計算式は、以下の通りです。
【計算式】
計算式内の0.9という数字は、建物の購入代金から購入代金の10%(残存価額)を差し引いた金額にするために、かけ合わせられている数字です。
では、実際に数字を使って計算してみましょう。
| マンション区分 | 新築 |
|---|---|
| マンションの取得価格(建物部分) | 1000万円 |
| 鉄筋コンクリート(RC造)の法定耐用年数 | 47年 |
| 購入日 | 2005年11月1日(平成17年) |
| 売却日 | 2022年11月20日(令和4年) |
| 経過年数 | 17年0か月 |
| 減価償却費 | 1,000万円×0.9×0.015×17年=229.5万円 |
マンションの売却に当たっては、譲渡所得税の関係から必ず自身で建造物部分に対する減価償却費について調査する必要があります。
最後に、マンション売却における減価償却費の計算式をおさらいしましょう。
【減価償却費の計算式】
減価償却費の計算に必要な数字を算出するのは非常に複雑で手間がかかるように見えますが、以下の順番でひとつずつ調査すれば安心です。
【マンションの建物購入代金の調べ方】
減価償却費を正しく申告することで、マンション売却時の節税に繋がる可能性もアップするでしょう。不安があるという場合は、不動産売却にかかるシミュレーターを使ったり、専門家に相談したりしながら進めるという手もあります。
マンション売却時にかかる正しい利益計算や確定申告をするためにも、この記事を参考に減価償却費の計算にチャレンジしてみてください。
