
-
不動産の瑕疵担保責任とは?トラブルを防ぐためのポイントを解説
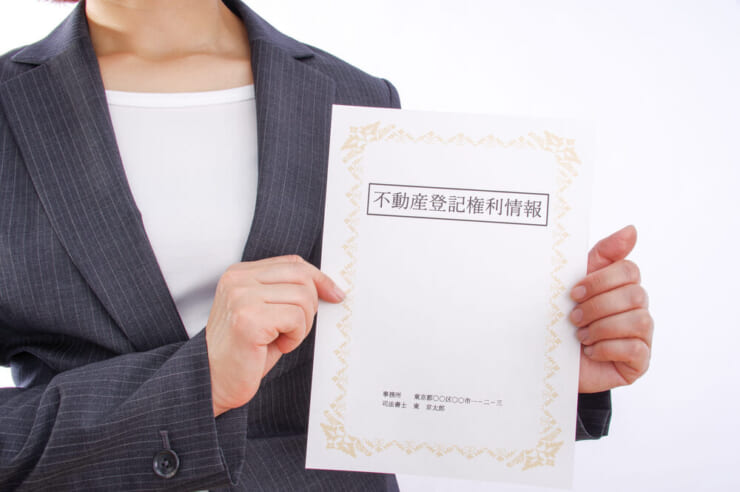

不動産における登記とは、「土地や建物が誰のものなのか」を明確にするための登録のことです。厳密には、所有権の所在だけではなく、保有者が住宅ローンを組んでいる金融機関やその借入額の情報がすべて記載されています。
この登記は、不動産購入時はもちろん、以下のように登記内容が変わった場合にもおこなう必要がある手続きです。
【不動産登記が必要な状況】
上記のような状況で不動産登記をおこなわなかった場合、罰則があるため注意しましょう。
また、不動産登記をした不動産の情報は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されます。
この書類は、法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」「かんたん証明書請求」などで手数料を支払うことで、誰でも入手可能です。400〜600円ほどで入手できるため、不動産の登記状況が気になる人は申請してみましょう。
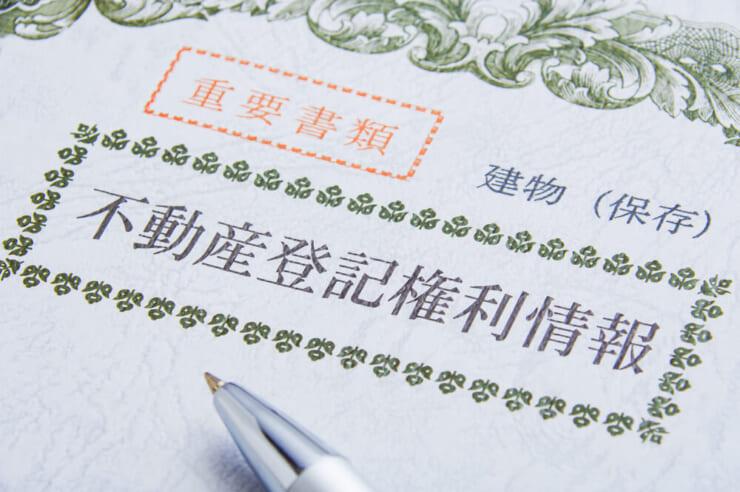
不動産売却時に必要な登記は以下の2つです。
所有権移転登記と抵当権抹消時の違いをまとめました。
【不動産登記の種類】
| 種類 | タイミング | 負担 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記 | 不動産購入時 | 買主 |
| 抵当権抹消登記 | 不動産売却時 | 売主 |
上記のように不動産登記は種類によって手続きのタイミングや費用を負担する人物が異なります。両者の違いをしっかり把握しておかないと、後でトラブルになる恐れがあるので注意してください。それぞれの不動産登記がどのようなものなのか詳しく見ていきましょう。
「所有権移転登記」は、第三者の所有する不動産を購入・取得した場合など、不動産の所有権が移る取引の際に必要になる登記です。
不動産売却では売主から買主に所有権が移転しますが、第三者からは所有権が移転したことが分かりません。登記は不動産にどのような権利があるのかを明確にするものです。所有権移転登記は売主から買主に所有権が移転したことを明確にするためにおこないます。
所有権移転登記をおこなわないと、トラブルに発展する恐れがあるため、不動産の買主は売買契約締結後に速やかに所有権移転登記をおこなわなくてはなりません。また、登記にかかる費用は買主負担が原則です。
具体的には、登記簿謄本の所有権に関する記載である「甲区」の内容の書き換えがおこなわれます。
また、新築物件を購入するケースでは、建物には「所有権保存登記」、土地には「所有権移転登記」の2つの登記が必要になるため、注意しなければなりません。
「抵当権抹消登記」は、住宅ローンの借り入れ時に設定した「物件の抵当権」を抹消するために必要な登記のことです。
抵当権とは、金融機関が設定する権利のことで、債務者が債務を実行できなかった場合に債権者である金融機関が抵当権の設定された資産を処分できるというものです。
住宅ローン契約では、金融機関は契約者が滞納した場合に備えて、融資を実行する不動産に抵当権を設定します。抵当権が設定されたままの不動産は、いつ処分されるか分からない不動産なので買い手がつきません。
そのため、不動産を売却する際、売主は抵当権を設定した金融機関の許可を得て抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消にかかる費用は原則売主負担です。
抵当権は土地と建物の両方に設定されているのが一般的なので、抵当権を抹消する際には、土地と建物の2回分の手間と費用がかかる点に注意してください。

不動産を売買した際に発生する登記費用は、以下の通りです。
【不動産の売却時の登記費用】
この中で売主が負担するのは、「抵当権抹消登記費用」のみです。
その他の登記費用は買い手が負担しますが、売却後に新しく不動産を購入する場合などには当然支払う必要があります。そのため、この章では不動産を売買する際に発生する登記費用すべてを解説していきます。
「登録免許税」は、登記内容を変更する際の手続き手数料のようなもので、買い手が法務局の窓口で支払います。原則は現金納付ですが、3万円以下なら収入印紙で納付することも可能です。
登記手続きを司法書士に依頼している場合は、司法書士へ支払う形になるでしょう。その場合は、不動産の引き渡し決済時に手数料と登録免許税をまとめて支払っておき、司法書士が代わりに税を納める形です。
また、登録免許税は「不動産取得時」と「抵当権設定時」で計算方法が異なります。
【登録免許税額の計算式】
| 登録内容 | 計算式 |
|---|---|
| 不動産取得時 | 固定資産税評価額×税率 |
| 抵当権設定時 | 抵当権設定金額×0.004 |
まず、不動産取得時の計算で必要な「固定資産税の評価額」とは、自治体が定めている土地や家屋の評価額のことを指します。
毎年自治体から送付される「納税通知書」の「課税資産明細」欄で確認できるものです。不動産の売却価格とは異なるため、混同しないよう注意しましょう。
また、税率は以下のように登記内容によって異なります。
【所有権移転登記の税率】
| 登記内容 | 税率 |
|---|---|
| 相続・合併 | 0.4% |
| 遺贈・贈与 | 2% |
| 売買等 | 2%(原則税率) |
固定資産税評価額が1,000万円の不動産を購入した場合は、「1,000万円×2%」となり、20万円が登録免許税としてかかります。
次に、抵当権設定時の登録免許税額に必要な「抵当権設定金額」とは、不動産購入時に借入をした金額です。例えば、3,000万円を住宅ローンで借りている場合には、12万円が登録免許税として必要となります。
住宅ローンを借り入れて不動産を購入している場合には、どちらの登録免許税もかかるため、20万円と12万円で合計32万円の登録免許税を支払う必要があるのです。
「司法書士手数料」は、登記手続きの代行を司法書士に委託した場合に支払う手数料や報酬額のことを指します。
登記手続きそのものに必要な費用は一律ですが、司法書士に支払う「報酬額」については自由設定のため、事務所ごとに金額が異なる特徴があるのです。
各登記にかかる司法書士費用の目安金額については、以下を参考にしてください。
【司法書士に依頼した場合の手数料・報酬】
| 登記手続き | 手数料相場 |
|---|---|
| 抵当権抹消登記 | 1~1.5万円 |
| 所有権移転登記 | 3~4.5万円 |
つまり、司法書士に登記手続きを依頼する場合は、「登録免許税+司法書士手数料」の支払いが必要になります。
「抵当権抹消登記」の登録免許税は、不動産1個につき1,000円かかります。この抵当権抹消登記にかかる費用は、売主の支払い義務です。
登記手続きをおこなう際は、金融機関から司法書士を通しておこなうよう指定されることがほとんどです。そのため、事務所によって多少変動はありますが、1万円程度の司法書士費用もかかります。
また、手続きをおこなう不動産が戸建ての場合は、土地と物件それぞれに抵当権が設定されているため、費用の計算時は注意が必要です。
所有権を移転するのは、買い手です。そのため売却時には支払い義務がありませんが、買い替えなどで新たな不動産を購入した場合には、移転登記をする必要があります。
所有権を移転する際に必要な登記費用の計算方法は、以下の通りです。
【所有権移転登記費用の計算方法】
所有権移転登記費用=登録免許税+司法書士報酬+手続きの実費
所有権移転時の登録免許税と司法書士報酬の計算方法・相場は前述の通りですが、これにプラスして手続きの実費がかかります。具体的には、以下の通りです。
【所有権移転登記にかかる費用】
| 費用 | 金額(相場) |
|---|---|
| 登記事項証明書の発行手数料 |
|
| 戸籍収集手数料 | 6,000円 |
| 各種書類の手数料 | 5,000円 |
| 事前調査及び立ち会い | 1〜1.5万円 |
| 住宅用家屋証明書取得費 | 1〜1.5万円 |
この中で、「事前調査及び立ち会い」「住宅用家屋証明書取得費」の費用は、新築物件購入時にのみ必要となります。
所有権の移転をおこなう場合には、上記の実費も事前に把握しておきましょう。

不動産を売却した際の登記費用は、すべてを売り手が負担する必要はありません。以下の5種類の登記のうち、売主が負担しなくてはいけない登記は、「抵当権抹消登記」のみです。
【不動産売買時に発生する登記】
それ以外の登記は、買い手がおこなわなければいけない手続きです。そのため、売却後に賃貸マンションに引っ越す場合には、抵当権抹消登記だけおこなえば十分となります。
しかし、買い替えなどで新たに不動産を購入する際には、新しい物件への登記が必要となるので注意しましょう。
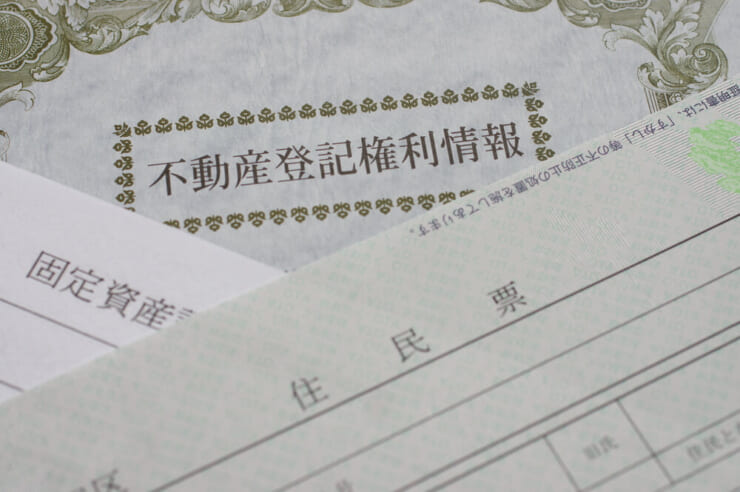
不動産売却時の登記に必要な書類は、以下の通りです。
【不動産売却時の登記に必要な書類】
| 書類名 | 必要な登記 | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 登記申請書 | すべての登記 | 登記の申し込みに必要 | 法務局ホームページのフォーマットから申請書を入手 |
| 登記識別情報または登記済証 | 抵当権抹消登記所有権移転登記 | ローン完済後に金融機関から受け取る書類 | 金融機関への問い合わせ |
| 登記原因証明情報(解除証書もしくは完済証明書) | 抵当権抹消登記所有権移転登記 | ローン完済後に金融機関から受け取る書類 | 金融機関への問い合わせ |
| 住民票 | 引っ越しを伴う登記 | 有効期限なし | 最寄りの役所 |
| 戸籍の附票 | 所有権移転登記相続登記など | 登記上の住所と現住所まで複数回引っ越しがある場合に必要住民票の代わりにもなる | 最寄りの役所 |
| 戸籍謄本 |
|
登記上の氏名と現在の氏名が異なる場合に必要 | 最寄りの役所 |
上記は必要書類の一覧ですが、必ずしもすべての書類が必要になるわけではないので注意が必要です。実際にどの書類の提出が求められるかは、手続きする登記内容によって変動します。
事前に各種書類を入手しておくことでスムーズな手続きが可能になるので、早めの対応をしておきましょう。

登録免許税は、適用条件に該当すれば減税措置が受けられます。登録免許税が減額される主な特例は以下の4つです。
【登録免許税が減額される4つの特例】
この特例のうち、2〜4は「令和4年3月31日までが適用期限」とされていました。
しかし、令和4年の4月1日に、法務局が「2年延長措置を講じる」ことを発表したため、現在も継続して適用可能となっています。
詳しくは法務局の「令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」をご覧ください。
土地を売却する際に必要な「所有権移転登記」には、本来2.0%の税率がかかります。ただし、軽減措置を利用すれば、1.5%まで減額可能です。
適用条件には、以下のようなものがあります。
【適用条件の例】
また、上記以外にも、認定長期優良住宅に該当する物件であることや、その住宅の所在する自治体の証明書の事前提出など、細かい適用条件が定められています。
詳しくは国税庁の「登録免許税の税額表」をチェックしてください。
新築住宅などの購入時に必要な「所有権の保存登記」は、原則0.4%の税率が課せられる登記です。ただし、特例を利用することにより0.15%まで軽減できます。
新築住宅の保存登記の特例を適用する条件は、以下の通りです。
【適用条件の例】
新築住宅の保存登記の特例は、当初令和4年3月31日までが適用期限でしたが、現在は令和6年3月31日まで延長されています。
詳しくは国土交通省のホームページ「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」をご覧ください。
中古住宅を購入した場合に必要な「所有権移転登記」には、本来2.0%の税率がかかりますが、特例を利用すれば、0.3%まで軽減することが可能です。
ただし、適用するには、以下の条件に該当しなければなりません。
【適用条件の例】
中古住宅の移転登記の特例は、他の特例と同様に令和6年3月31日まで適用期間が延長されています。
マンションなどの耐火建築物は25年以内、戸建てなどの耐火建築物でない物件は20年以内の築年数であることが前提条件です。
また、築年数の条件に該当しない場合であっても、新耐震基準内であり、瑕疵保険に入っている物件であれば、適用される可能性があります。
詳しくは国税庁の「登録免許税の税額表」をチェックしてください。
住宅ローンを契約していた物件を売却する際は、抵当権の抹消登記が必要です。本来は0.4%の税率がかけられますが、軽減措置が適用されれば、0.1%まで下げることができます。
抵当権の設定登記の適用条件は、以下の通りです。
【適用条件の例】
抵当権の設定登記の適用期限に関しても、令和4年3月31日から令和6年3月31日まで延長となっています。
ただし、登記の申請書と一緒に「物件が50㎡以上であること」や「一定の要件を満たすこと」が確認できる自治体発行の証明書が必要です。
詳しい適用条件については、国税庁の「登録免許税の税額表」を確認してください。
不動産売却では、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの不動産登記が必要です。所有権移転登記は売主から買主に所有権が移転したことを証明するため、抵当権抹消登記は住宅ローン契約時に金融機関が不動産に設定した抵当権を外すためにおこなう登記です。
これらの不動産登記は買主・売主のどちらがおこなうのか、どちらが費用を負担するのかは原則決まっています。所有権移転登記をおこなわないと第三者に所有権を主張できずトラブルに発展します。抵当権抹消登記をおこなわないと売買契約の成立に支障が生じます。
不動産登記を速やかに完了させるかつトラブルを未然に防ぐためにも、どんな不動産登記を誰がいつおこなうのか、どんな書類が必要なのかを事前に確認しておきましょう。
