
-
旗竿地が売れない理由は?売れる場合の理由や売る際のポイントも...


土地や物件などの不動産を売却したら、その翌年には確定申告が必要になります。確定申告は、年間で得た所得の合計金額を税務署に申告して、その所得に応じて税金を支払うためにおこなう手続きのことです。
日本の税制は「申告制納税方式」を採用しているため、個人が得た収入を正しく申告し、税を納めることが義務付けられています。
そのため、1月1日~12月31日までの所得・税額を計算して、翌年の2月16日~3月15日の期間に申告・納税をおこなわなければならないのです。
しかし、サラリーマンやアルバイトをしている人の中には、この確定申告をしたことがないという人も少なくないでしょう。このような「給与所得」を得ている人は、企業がまとめて従業員の税額を納めてくれています。
つまり、確定申告は、所得が発生している人全員がおこなわなければならないものです。
まずは、不動産売却に関して「確定申告が必要になる・不必要である」ケースをそれぞれ見ていきましょう。
不動産売却で発生する利益を「譲渡所得」といいます。この譲渡所得が発生している場合は、金額に関わらず必ず確定申告をおこなわなければなりません。
また、譲渡所得が発生した場合は、企業に勤めている人も確定申告をおこなわなければならないので注意しましょう。企業に申告義務があるのは従業員の「給与所得」のみです。
そのため、ほかに所得が発生した際には自分自身で申告する必要があります。
譲渡所得が発生しているかどうかは以下で概算できます。
課税譲渡所得(売却益)=売却金額-取得費用-譲渡費用
これらを土地の売却金額から差し引いて残ったものが譲渡所得です。計算式の内訳については後述しますが、この式がプラスになる場合には確定申告が必要になります。
確定申告は所得を申告するためのものです。そのため、不動産売却にかかる譲渡所得が0円またはマイナスであった場合は、確定申告は義務ではありません。
ただし、確定申告をしなかった場合は、国税庁から「お尋ね」という名目のアンケート調査がされることがありますので覚えておきましょう。
国は土地売却による登記の移動記録があったことを把握しているので、譲渡益が出ている可能性がある人を対象に調査をおこなっています。調査を受けたらありのままを伝えるようにしましょう。
また、譲渡所得に損益が発生している場合には、義務はなくても確定申告をしたほうがいいケースもあります。確定申告には払い過ぎた税を返還する「還付申告」の性質もあるためです。
さらに、特例を利用すれば特別控除・繰越控除が受けられる可能性もあるので、利益がマイナスであっても確定申告をおこなうことをおすすめします。

もし、所得が発生していて確定申告をしなければならないのにも関わらず、その義務を怠った場合はどうなるのでしょうか。ここからは、確定申告をしないと起こってしまうデメリット・ペナルティについて解説していきます。
確定申告を怠った際に起こりうるデメリットには、以下のようなものがあります。
申告義務があるにも関わらず申告しなかったことが発覚した際には、上記のようなリスクが発生するので十分注意しましょう。
故意におこなったことが発覚すると、通常通り申告した場合の何十倍もの金額を支払う羽目になってしまいます。さらに、意図せず期限に遅れてしまってもペナルティを受けてしまうので、慎重におこないましょう。
不動産取引で大きな金額が動いた際には、税務署からチェックが入ります。さらに、税務署は「登記移動記録」なども把握しているため、無申告の可能性がある取引は税務調査の対象となるのです。
以下のケースに該当する人は、税務調査の対象となる場合があります。
税務調査は無造作にピックアップされるもので、すべての人に実施されるのではありません。
調査の結果、不動産売却による利益を隠蔽していた・申告を怠っていたことが発覚すると、税務署が指定する税額で強制的に納税させられることになります。
この金額は厳格な基準によって決定され、自分で確定申告をおこなうよりも課税額が大きくなることもあるので注意が必要です。
さらに、確定申告を怠ることで信用情報が傷つき、銀行などの融資が受けられなくなる場合もあります。さらに、銀行から税務署に通告されてしまうと、無申告が発覚しペナルティが課せられる可能性も上がるでしょう。
特に、事業をおこなっている人にとっては重大な問題となります。確定申告をしていないと、その年の決算書が正しく作成されていないことと同義に捉えられるためです。
決算書がないと事業としての信用度が低くなり、新しく融資が受けられない・すでに受けているものも打ち切られてしまうというリスクが発生します。
決算書を偽っていることが発覚した際には、今後一切取引しないと宣言されてしまうこともあるでしょう。
明らかに所得が発生しているのにも関わらず、それを隠蔽したあるいは確定申告を怠った場合には、悪質であると判断され「重加算税」のペナルティが課せられてしまいます。
重加算税の税率は35~40%と非常に重いものです。きちんと期限内に確定申告をした場合と比較すると、何十倍もの税額を支払わなければならなくなるので注意しましょう。
重加算税の対象は「悪質と認められる場合」であり、明確に定義があるわけではありません。しかし、「申告の必要性を知っていたがあえてしなかった」など、故意に怠った場合には対象になりやすい傾向があります。
さらに、申告内容を間違えて納税額を過小申告してしまった場合には「過小申告加算税」が発生することも覚えておきましょう。過少申告加算税は、追加で10%が課されるペナルティです。
過少申告した金額が多かった場合には、さらに金額が上乗せされてしまいます。ただし、自主的に申告誤りを修正した場合には、過少申告加算税は課されないので、間違いに気付いた場合は早めに申告しましょう。
確定申告には明確な申告期限が定められています。この期限を超過してしまうと、「無申告加算税」が徴収されるので注意しましょう。
無申告加算税の請求額の目安は、以下の通りです。
| 納付すべき税額 | 課税率 |
|---|---|
| 50万円まで | 15% |
| 50万円以上 | 20% |
ただし、税務署からの調査前に自己申告した場合のみ、期限後に申告した場合でも無申告加算税が課税されない特別措置が取られるケースもあります。
条件については以下を参考にしてください。
【無申告加算税が課税されないケース】
そのため、万が一遅れてしまいそうな場合は、早めにその旨を申告しておくことをおすすめします。
また、期限後申告には、別途「延滞税」の支払いも発生するので覚えておきましょう。延滞税は超過した日数に対して課せられるもので、延滞の申告有無にかかわらず発生するものです。
ただし、期限を超過しても短期間で納めれば負担は軽く済みます。延滞税の課税率は以下を参考にしてください。
| 超過日数 | 課税率 |
|---|---|
| 2か月以内 | 7% |
| 2か月以上 | 14% |
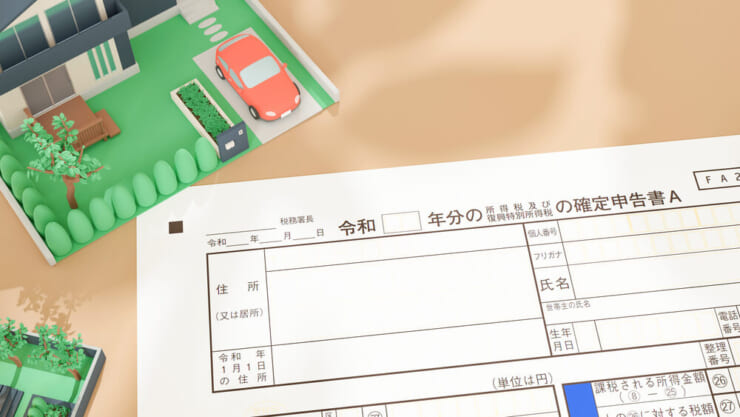
ここからは、確定申告をおこなう際の流れについて詳しく解説していきます。自分自身で確定申告することを検討している人は、しっかり流れを覚えて自身の申告に役立ててください。
土地売却をした際の確定申告は、以下の流れでおこないます。
確定申告は、法定申告期限に間に合うようにおこなわなければならないものです。不慣れな人だとスムーズに申告できない可能性があるため、十分時間を確保して準備することをおすすめします。
まずは、課税対象となる譲渡所得がいくらになるかを概算します。先述した以下の計算式を用いて算出しましょう。
課税譲渡所得(売却益)=売却金額-取得費用-譲渡費用
取得費用は、土地を購入する際にかかった費用です。また、譲渡費用は土地の売却のためにかかった諸費用のことを指します。それぞれに該当する具体的な費用の例は以下を参考にしてください。
| 取得費用の例 | 譲渡費用の例 |
|---|---|
| 不動産の購入金額 | 仲介手数料・広告費 測量費・立ち退き費 建物取り壊し費用・印紙税など |
上記費用は経費計上されるため、土地を譲渡して得た収入から差し引いて計算できるメリットがあります。不動産売買に関する特例が適用できる場合は、さらに控除額分を差し引くことも可能です。
納税額が概算できたら、申告に必要な書類を準備しましょう。土地売却時の確定申告における必須書類は、以下を参考にしてください。
【確定申告の必要書類】
| 書類名 | 取得場所 |
|---|---|
| 確定申告書第一表・第二表(B様式) | 税務署 |
| 申告書第三表(分離課税用) | 税務署 |
| 譲渡所得の内訳書(土地・建物用) | 税務署 |
| 売買契約書の写し | 不動産売却時 (または売却時の仲介不動産会社) |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 |
| 領収書 | 土地売却時 |
税務署で取得する書類は、直接来所して受け取ることもできますが、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で取得・作成することも可能です。
ただし、後者の場合にはマイナンバーカードの所持か、専用のID・パスワードの発行が必要になります。
資料がそろったら申告書に必要事項の記入をおこない、確定申告書を作成しましょう。
記入の仕方・計算方法が難しくて分からないという人は、税理士に相談するのがおすすめです。税理士に相談する方法については後述します。
さらに、確定申告の時期は税務署でも無料相談を開催してくれるので、そちらを利用するのもいいでしょう。その際は、添付書類を揃えた状態で、事前に不明点・疑問を把握しておくとスムーズです。
申告書作成時の不明点は早めに解決しておき、期限に間に合うように書類を準備してください。
申告書の作成と添付書類の準備が完了したら、確定申告書類の提出をおこないます。法定期限は翌年の2月16日~3月15日までとなり、この期間を経過すると先述したペナルティが課せられるので注意しましょう。
申告書の提出は以下の方法でおこないます。
e-Taxは、「ICカードリーダーライター」という専門機器を用意すれば、自宅から確定申告できる方法です。国税庁が運営しているものでセキュリティ性能も高く、安心して申告できる特徴があります。

確定申告は、慣れない人にとっては労力のかかる大変な作業になります。そのため、自分で確定申告の手続きをおこなうのが億劫だという人は、税理士に依頼するのも一つの手です。
税理士に確定申告手続きを依頼すると、申告書の作成や不備のチェックなどを丸投げできるメリットがあります。
また、税理士は税制度を熟知している専門家であるため、適用できる特例や減税制度などについてもアドバイスがもらえるかもしれません。
ここからは、税理士に依頼する方法や依頼費用について紹介していきます。
確定申告を税理士に依頼した場合の費用は、依頼内容によって変動します。一般的に、申告書の作成と提出のみを依頼する場合には約5万円、すべての手続きを依頼すると約10万円の依頼費用が必要です。
また、仕訳込みで依頼する場合は、仕訳をおこなう取引数(仕訳の作業量)によって費用が変動します。以下は青色申告を仕訳込みで依頼した場合の料金目安です。
| 申告する所得 | 依頼費目安 |
|---|---|
| 500万円以下 | 10万円 |
| 500万円以上1,000万円以下 | 15万円 |
| 1,000円以上 | 20万円 |
税理士報酬は税理士が自由に決められるので、依頼費用は事務所によって変動します。そのため、見積もりをもらったら予算内でどこまでの範囲を依頼できるかをしっかり確認しておきましょう。
税理士への依頼に失敗しないためには、自分に合った税理士を見つけることが重要になります。税理士を見つけるおすすめの手段は以下の通りです。
ここからは、上記4つの方法について詳しく紹介していきます。目的によって適した方法が異なるので、自分に合った方法で税理士を見つけてください。
「税理士紹介サイト」とは、サイト登録をして希望の条件を入力するだけで、インターネット上で簡単に複数の税理士事務所を探せる手段です。気になる税理士事務所にコンタクトを取り、価格交渉をした上で契約を締結します。
税理士紹介サイトは以下の人におすすめです。
税理士紹介サイトは無料で利用できるものですが、すべての事務所が登録しているわけではないことは留意しておきましょう。相見積もりを避けるため、そもそも登録していない税理士事務所も多いためです。
相見積もりとは、価格・サービスなどの見積もり内容を、ほかの競合と比較して契約先を検討することを指します。
税理士紹介サイトは、相見積もりによって価格競争が起こりやすい特徴があり、安くサービスを提供できる税理士事務所が多い傾向があるのです。金額が安いぶん、サービスの質が低い可能性もあるので注意が必要です。
親や友人等が税理士を利用したことがある場合には、直接その税理士を紹介してもらうのがよいでしょう。紹介で税理士を探すのが適している人は以下の通りです。
親しい人がおすすめする税理士であれば、自分とも相性や波長が合う可能性が高いでしょう。ただし、紹介してくれるのが取引先や業者である場合はその限りではありません。
取引先・業者からの紹介は、業務提供をすることで紹介料を得るビジネスである可能性が高いため、注意が必要です。
さらに、利害関係のある相手から紹介してもらった場合には、紹介された税理士と相性が悪かったとしても、解約しづらくなってしまうデメリットもあります。
商工会議所でおこなわれる税理士の無料相談に参加してみるのも一つの方法です。商工会議場では定期的に税務相談の無料開催をおこなっているので、実際に税理士の話をうかがってから契約するか判断することができます。
無料相談がおすすめの人は以下の通りです。
無料相談は、相談することが目的であるため、そもそも税理士側が営業目的で臨んでいるかどうかはわかりかねます。そのため、「良い税理士だったのでぜひ依頼したい」と思って声をかけても断られてしまう可能性があるのです。
また、事前に金額提示しているわけではないため、その場で開示された依頼費用が予算と見合わない場合は、どんなに良い税理士でも断念せざるを得ないでしょう。
税理士に依頼することよりも、まずは確定申告の不安・疑問を解消したいと考えている人におすすめの方法です。
税理士や税理士事務所が主催する確定申告セミナーに参加する方法もあります。確定申告の時期が近くなってくるとさまざまなセミナーが開催されるので、セミナー内容が気になるところに問い合わせて参加してみるのもいいでしょう。
セミナー参加は以下のような人に適しています。
商工会議場の無料相談と異なる点は、セミナーを開催している税理士のほとんどが営業目的であるということです。そのため、依頼しても断られてしまうことは少ないでしょう。
ただし、セミナーを開催している税理士事務所は、有名な先生や大手の事務所である場合がほとんどです。依頼しても仕事内容に直接関わらない可能性があるため、実際に本人が着手してくれるのかどうかの確認は必要でしょう。
土地を売却して譲渡利益が発生した場合は、確定申告をおこなわなければなりません。確定申告には明確な法定申告期限が定められているため、万が一この期限を過ぎてしまうと追加徴税などのペナルティが課せられてしまいます。
さらに、申告義務を怠った場合は、通常通り申告した場合よりもはるかに大きい額が徴税されるため、十分注意してください。
確定申告は、ゆとりをもってしっかり準備をおこない、期限内の申告を心掛けましょう。
