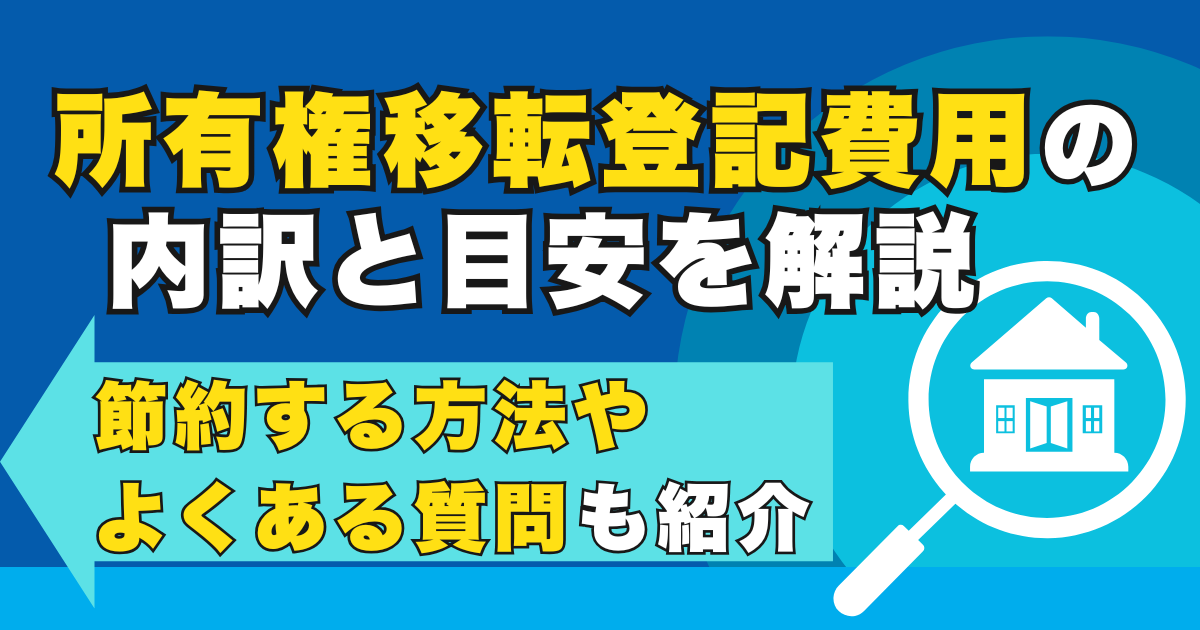
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...

「親から相続した家をいざ売ろうとしても、なかなか買い手が見つからない。」
「毎年送られてくる固定資産税の通知書を見るたびに、ため息をついてしまう…。」
築年数が古いボロ家や空き家がなかなか売れず困っている人は少なくありません。
結論、あなたの家が売れないのには、必ず理由があります。逆に言えば、理由に合わせた正しい対処法を知ることさえできれば、売却は十分可能なのです。
この記事では、なぜあなたの家が売れないのか、理由から具体的な解決策までわかりやすく解説します。
所有している古い家がなかなか売れない主な理由は以下の6つです。
ボロ家が売れない理由は、物件の状態から法律上の制約まで、様々な要因が絡み合っていることが多いため、ご自身の物件がどのケースに当てはまるのか一緒に確認していきましょう。
古い家が売れない最も根本的な理由は、買い手にとって建物そのものの価値がゼロ、場合によっては解体費用がかかる「マイナス」と見なされてしまっている点にあります。
木造戸建ての場合、法定耐用年数は22年と定められており、不動産市場では築25年〜30年も経つと、建物自体の資産価値はほぼ無いと評価されるのが実情です。(参照元:主な減価償却資産の耐用年数表)
少しイメージしてみてください。あなたが家を建てるために土地を探しているとして、すぐ隣に条件がそっくりな2つの土地が売りに出されています。
あなたなら、どちらの土地を選びますか?
おそらく、ほとんどの方がAの更地を選ぶのではないでしょうか。Bの土地を購入した場合、新しい家を建てる前に、まず古い家を解体しなければならず、その費用として100万円~300万円ほどの追加出費が見込まれるからです。
つまり、買い手にとってBの土地は、実質的に「2,200万円前後の土地」に見えてしまいます。
これでは、同じ価格で売りに出していても、買い手の候補から外れてしまうのは当然と言えるでしょう。
長年適切なメンテナンスがされていなかった家が売れにくいのは、購入後にいくらかかるか分からない「見えないリフォーム費用」が、買い手の大きな不安を煽ってしまうからです。
雨漏りやシロアリの被害、水回りの故障など、人が住むために大規模な修繕が必要な状態では、買い手は内見に訪れても「住める状態にするには、修繕費用がいくらかかるんだろう…」と不安を感じてしまいます。
物件の状態が原因で売れない場合は、費用はかかりますが、インスペクション(住宅診断)やリフォーム、害虫駆除などをして「買い手が安心できる状態」にする必要があります。
建物の安全性が、売却の大きなハードルになることも少なくありません。
特に、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」で建てられており、これが売れない直接的な原因になっているケースが非常に多いです。
1981年6月以降に建てられた建物は「新耐震基準」によって強化されましたが、木造住宅に関しては2000年(平成12年)の改正で耐震性能がさらに大きく向上しています。
以下の表は、各時期の耐震基準の違いをまとめたものです。
| 項目 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 | 現行基準(2000年改正) |
|---|---|---|---|
| 適用期間 | 1950年~1981年5月31日までの建築確認 | 1981年6月1日以降の建築確認 | 2000年(平成12年)6月1日以降の建築確認 |
| 想定する地震 | 震度5強程度の揺れで倒壊しないこと | ・中地震(震度5強程度):ほとんど損傷しないこと ・大地震(震度6強~7程度):倒壊・崩壊せず、人命を守ること |
・中地震:ほとんど損傷しない ・大地震:倒壊・崩壊を防ぎ、人命を守る ※より厳密な耐震性能評価を導入 |
| 設計の考え方 | 許容応力度計算地震力に対して部材が耐えられるかを検証 | 許容応力度計算(一次設計)に加え、保有水平耐力計算(二次設計)を導入大地震時に建物全体がどれだけ耐えられるかを検証 | 耐力壁の量と配置バランスの両方を重視。接合部(構造金物)の仕様を明確に義務化し、地盤調査も事実上必須に。木造住宅の弱点だった「接合部の弱さ」「壁の偏り」を根本的に改善。 |
| 改正の背景 | 1950年の建築基準法制定 | 1978年の宮城県沖地震の被害を受けて | 木造住宅の耐震性能向上を目的に大幅改正。構造バランスと接合部強化により性能が飛躍的に向上。 |
なぜ旧耐震基準の建物が敬遠されるのかというと、買い手にとって「安全性の不安」と「金銭的なデメリット」が残ってしまうからです。
旧耐震基準では震度5強程度までしか想定されていないため、大きな地震に対する不安が残ります。
また、現在の耐震基準を満たしていない物件は、住宅ローン控除や耐震改修補助金などの税制優遇を受けられないケースも多く、買い手にとって魅力が薄くなります。
安心して住めないうえに金銭的なメリットもないとなれば、敬遠されてしまうのも無理はありません。
売れない理由として意外と多いのが、その土地が「再建築不可物件」であるケース。
これは、今ある建物を取り壊してしまうと、新しい建物を建てることができない土地のことを指します。
建築基準法では、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルール(接道義務)があり、これを満たしていない土地には家を建てられません。
簡単にいうと「車や人が道路から敷地内へ安全に出入りできる、最低限の入り口の幅(2m以上)を確保してくださいね」というルールのことです。
買い手からすると、将来的に建て替えができない、リフォームに制限がある物件は選びづらいのが正直なところ。
また、金融機関も再建築不可物件への融資には非常に慎重なため、買い手は住宅ローンを組むことさえ難しい点も売れにくい理由です。
物件そのものに大きな問題がなくても、立地が不便なために売れないケースも多くあります。
買い手は、家そのものだけでなく、そこで始まる「新しい生活」をイメージして物件を探しているからです。
このような立地では、日々の生活のしづらさが懸念され、買い手の候補から外れやすくなってしまいます。特に、車が必須の郊外や地方の物件では、この傾向がより顕著になります。
意外に思われるかもしれませんが、土地が広すぎることが売却の足かせになることもあります。これは、個人の買い手が求めるニーズと、物件の価格や管理の手間が合致しないために起こります。
土地が広いと、その分、土地の評価額が高くなり、売却価格も高額になる傾向にあります。
しかし、一般的な家庭にとっては「こんなに広い土地は必要ない」「庭の手入れや草むしりが大変そうだ」と感じてしまいます。
また、固定資産税が高くなることもデメリットです。結果として、物件の価値と買い手の需要にミスマッチが生まれ、売れ残ってしまうのです。
ボロ家が売れない、でもできるだけ高値で売りたいという場合は、以下5つの売却方法がおすすめです。なかでも、とにかく早く売却したい場合は「不動産買取を利用する」、少しくらい時間がかかっても高く売りたい場合は「古い物件の売却が得意な不動産会社を見つける」という方法を試してみましょう。
| 売れない理由 | おすすめの売却方法 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 手入れ不足・内装の古さ | ①リフォームして売却 | ・費用をかけてでも高く売りたい人 ・リフォームで価値が上がる見込みがある物件の所有者 |
| 建物が住めない状態・再建築不可でない | ②古い家を解体して更地として売却する | ・建物の傷みが激しく、修繕費用が高額になる人 ・土地として売却した方が高く売れる可能性がある人 |
| 買い手が限定される・特殊な事情がある | ③ボロ家の売却が得意な不動産会社を見つける | ・一般的な不動産会社に断られた人 ・物件の魅力を引き出す専門的な知識を借りたい人 |
| とにかく早く手放したい・手間をかけたくない | ④古い物件の買取実績が豊富な不動産会社に依頼する | ・すぐに現金化したい人 ・売却活動の手間や時間をかけたくない人 ・ご近所に知られずに売却したい人 |
| 地方・郊外の物件・買い手が見つからない | ⑤自治体が運営する空き家バンクに登録する | ・地方への移住希望者にアプローチしたい人 ・不動産会社が見つからないエリアの物件所有者 |
ただし、どの方法を選ぶにしても「信頼できる・古い物件の売却・買取実績がある不動産会社」との連携は必要不可欠です。
そもそも「どの不動産会社に依頼したらいいか曖昧・今の担当者で本当に売れるのかな」と疑問に感じている方は、無料の一括査定などを活用し「一緒に売却を進めるパートナー」を決めることから始めましょう。
それでは、それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。
内装の古さや多少の傷みが原因で売れない場合、リフォームをして物件の価値を高めてから売却する方法があります。
| メリット | ・物件の価値が高まり、高値での売却が期待できる ・特に水回りなどを新しくすると、買い手の印象が格段に良くなる |
|---|---|
| デメリット | ・リフォーム費用の先行投資が必要になる ・かけた費用以上に売却価格が上がらないと赤字になるリスクがある |
特に、キッチンや浴室、トイレといった水回りを新しくするだけでも、購入希望者に与える印象は大きく変わります。
ただし、最も重要なのは「費用対効果」です。リフォームにかけた費用以上に売却価格が上がらなければ、持ち出しになってしまいます。
| リフォームの内容 | 費用目安 | 主な工事内容 |
|---|---|---|
| 水回り(セット) | 150万~300万円 | キッチン、浴室、トイレ、洗面台の交換 |
| 内装全体 | 200万~500万円 | 壁紙・床の張り替え、建具の交換など |
| 外壁・屋根 | 100万~300万円 | 外壁の再塗装、屋根の葺き替えや補修 |
| 間取り変更 | 50万~400万円 | 壁の撤去・新設、部屋の統合など(規模による) |
| スケルトンリフォーム | 800万~2,000万円以上 | 構造躯体のみを残し、内外装を全面的に刷新 |
例えば、300万円かけてリフォームしても、売却価格が200万円しか上がらなければ、100万円の赤字です。
リフォームをする際は、どの程度の費用をかければ、いくらで売れそうか、不動産会社としっかり相談し、慎重に判断することが重要です。
建物の傷みが激しく、リフォーム費用が高額になる場合や、再建築不可物件でない場合は、建物を解体して「更地」として売却するのも有効な選択肢です。
| メリット | ・買い手が自由に家を建てられるため、土地を探している層に広く訴求できる ・建物の状態を気にする必要がなくなる |
|---|---|
| デメリット | ・解体費用が先行して必要になる ・更地にすると固定資産税の軽減措置が外れ、税金が最大6倍になる可能性がある |
買い手は、建物の状態を気にする必要がなく、自由に新しい家を建てられるため、土地を探している層に広くアプローチできます。
ただし、解体には先行投資が必要です。木造住宅の場合、坪単価で3万円〜5万円程度が相場で、50坪の家なら150万円〜250万円ほどの費用を見込んでおく必要があります。
| 家の坪数 | 解体費用の目安 (坪単価3万~5万円で計算) |
|---|---|
| 30坪 | 90万~150万円 |
| 40坪 | 120万~200万円 |
| 50坪 | 150万~250万円 |
| 60坪 | 180万~300万円 |
また、建物を解体すると、土地にかかる固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が適用されなくなるため、税金が最大で6倍になる可能性がある点も忘れてはいけません。解体は、売却の目処が立ってから行うのが賢明です。
「大手不動産会社に相談したけど、断られてしまった…」そんな経験はありませんか?実は、不動産会社にも得意・不得意があります。一般的な中古住宅を扱うのが得意な会社もあれば、古い家や空き家、いわゆる「ボロ家」の売却を専門的に扱っている会社も存在します。
| メリット | ・一般的な不動産会社では扱えない物件も売却できる可能性がある ・専門的なノウハウで、物件の隠れた価値を引き出してくれる |
|---|---|
| デメリット | ・信頼できる専門会社を見つける手間がかかる ・会社によって提案内容や査定額に差が出ることがある |
また、物件の隠れた価値を見つけ出し、魅力的な形で買い手に提案するノウハウも豊富です。
インターネットで「空き家 売却 専門」や「古家 再生」といったキーワードで検索し、複数の会社に相談してみることをお勧めします。
「とにかく早く手放したい」「面倒な手続きは避けたい」という方には、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「買取」がおすすめです。
| メリット | ・買主を探す必要がなく、スピーディーに現金化できる ・売れ残るリスクがなく、内見対応などの手間も一切かからない ・近所に知られずに売却活動を進められる |
|---|---|
| デメリット | ・売却価格が市場価格の7〜8割程度になることが多い ・仲介で売るよりも高値になる可能性は低い |
通常の売却(仲介)が、不動産会社を通して一般の買い手を探すのに対し、買取は不動産会社自身が買主となります。
そのため、買主を探す期間が必要なく、スピーディーに現金化できるのが最大のメリットです。売却価格は市場価格の7〜8割程度になることが多いですが、売れ残るリスクがなく、内見対応などの手間も一切かかりません。
古い物件の買取実績が豊富な会社を選べば、スムーズな取引が期待できます。
特に地方や郊外の物件で、地域の不動産会社では買い手が見つからない場合に検討したいのが「空き家バンク」です。
| メリット | ・不動産会社が見つからないエリアでも買い手を探せる ・地方への移住希望者など、新たな層にアプローチできる ・自治体によってはリフォームなどの補助金制度を利用できる場合がある |
|---|---|
| デメリット | ・買い手が見つかるまでに時間がかかる場合がある ・必ずしも買い手が見つかる保証はない ・手続きは基本的に自分で行う必要がある |
これは、各自治体が運営している空き家の情報サイトで、空き家を売りたい・貸したい人と、利用したい人をマッチングさせる制度です。
自治体によっては、空き家バンクに登録された物件のリフォーム費用や家財撤去費用に対して補助金を出している場合もあります。
地方への移住を希望している人や、地域に根ざした暮らしをしたい人が閲覧していることが多いため、思わぬ買い手が見つかる可能性があります。
まずは、物件が所在する市町村の役場のウェブサイトを確認してみましょう。
「売るのも大変そうだし、少しこのままにしておこう…」そう考える気持ちも分かります。しかし、その考えが最も危険です。ボロ家を放置し続けることには、金銭的にも精神的にも大きなリスクが伴います。
これらのリスクの中で、最も身近で確実に起こるのが「税金」による家計への負担です。
また、確率は低いものの、万が一、倒壊や行政指導といった事態になれば、経済的に取り返しのつかない損害を被る危険性もゼロではありません。それぞれのリスクについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
家を所有している限り、毎年「固定資産税」と「都市計画税(市街化区域内の場合)」を支払い続けなければなりません。
たとえ誰も住んでいない空き家であっても、この納税義務が免除されることはありません。売却できずにいる間も、確実に出費は続いていくのです。
税額は、自治体が算出する「固定資産税評価額」を基に計算されます。
※税率は自治体によって異なる場合があります。
例えば、土地と建物の評価額の合計が1,500万円の物件であれば、単純計算で年間約25.5万円(固定資産税21万円+都市計画税4.5万円)の税負担が発生します。
現在、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という税金の軽減措置が適用されています。
しかし、管理されずに放置された空き家が、倒壊の危険性などがあると自治体に判断され「特定空き家」に指定されると、この特例が適用されなくなります。
そうなると、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。少し具体的なシミュレーションをしてみましょう。
【シミュレーション】課税標準額2,000万円、面積200㎡以下の土地の場合
このように、年間で23万円以上も負担が増える計算になります。これは非常に大きなリスクと言えるでしょう。
管理されていない古い家は、台風や地震で倒壊したり、放火や漏電によって火災が発生したりするリスクが高まります。
もし、倒壊した家屋が隣家を傷つけたり、通行人に怪我をさせたりした場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性があります。そうなれば、数千万円単位の賠償金を請求されるケースも考えられます。
荒れ果てた空き家は、景観を損なうだけでなく、不法投棄の場所になったり、害虫や害獣が発生する温床になったりすることがあります。
また、不審者が侵入し、犯罪の拠点として利用される危険性も否定できません。近隣住民とのトラブルに発展し、精神的な負担を抱えることにもなりかねません。
自治体から「特定空家」に指定され、改善の助言・指導、勧告、命令に従わなかった場合、最終的には行政が所有者に代わって建物を解体する「行政代執行」が行われる可能性があります。
この措置は「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律に基づいており、以下の段階を踏んで進められます。
もちろん、その解体費用は、後日、所有者に全額請求されます。費用の目安は建物の規模や構造によりますが、木造家屋一軒で100万円~300万円以上かかることも珍しくありません。
所有者が支払いに応じない場合は、預金や給与、その他の不動産といった財産が差し押さえられることになります。
売却に向けて具体的に動き出す前に「どれくらいのお金がかかるのか」あらかじめ知っておくと安心ですよね。
ここでは、売却時にかかる主な費用とその目安をまとめました。売却価格からこれらの費用が差し引かれた金額が、最終的に手元に残るお金になります。
| 費用項目 | 費用の内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 解体費用 | 建物を解体して更地にするための費用。 | 木造:3〜5万円/坪(30坪で90〜150万円) |
| 測量費用 | 土地の境界が不明確な場合に、隣地との境界を確定させるための費用。 | 35〜80万円 |
| 修繕・リフォーム費用 | 雨漏り修繕や水回りの交換など、物件の価値を高めるための費用。 | 内容により数万円〜数百万円 |
| 印紙税 | 不動産売買契約書に貼る印紙代。売買価格によって変動。 | 1万円(売買価格1,000万円超5,000万円以下の場合) |
| 仲介手数料 | 不動産会社に売却を仲介してもらった場合に支払う成功報酬。 | (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税※売買価格400万円超の場合の上限額 |
| 譲渡所得税 | 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金。 | 利益額 × 20.315%(長期譲渡所得:所有期間5年超の場合)※所有期間5年以下の短期譲渡所得の場合は税率が39.63% |
| 登記費用 | 抵当権抹消や住所変更など、登記情報を変更するための費用。 | 1〜5万円程度 |
売却の成功確率をぐっと引き上げるために、プロの視点からの具体的なポイントを7つご紹介します。
これらを一つひとつ実行していくことが、スムーズな売却への一番の近道です。
まずは、信頼できる不動産会社、特に古い家の売却実績が豊富な会社に相談し、プロの視点から「この物件にどんなニーズがあるか」を調査してもらうことが第一歩です。
「古民家として住みたい人」「リフォームして貸し出したい投資家」「土地として利用したい開発業者」など、どんな層がターゲットになり得るのかを把握することで、最適な売り出し方や価格設定が見えてきます。
インスペクションとは、住宅の専門家が建物の状態を客観的に診断することです。費用は5〜10万円程度かかりますが、雨漏りやシロアリの有無、構造上の欠陥などを正確に把握できます。
この診断結果を買い手に提示することで、安心して購入を検討してもらえるという大きなメリットがあります。
また、売却後に欠陥が見つかってトラブルになる「契約不適合責任」のリスクを減らすことにも繋がります。
インスペクションの結果、雨漏りや給排水管の故障といった、生活に支障をきたす大きな欠陥が見つかった場合は、最低限の修繕をしてから売りに出すことを検討しましょう。
全ての箇所をリフォームする必要はありませんが、「安心して住み始められる状態」に整えることで、買い手の印象は格段に良くなります。
建物自体の価値が低くても、土地に魅力があれば売却の可能性は十分にあります。用途地域(商業地域、住居地域など)、建ぺい率・容積率、周辺環境(学校、病院、公園など)といった土地の情報を正確に整理し、アピールポイントを明確にしておきましょう。
これらの情報は、不動産会社が調査してくれますが、自分で法務局で登記簿謄本を取得したり、役所で都市計画図を確認したりすることで、より深く理解できます。
「リフォームして売る」「解体して売る」「そのまま売る」など、どの方法が最も手元にお金が残るのか、必ずシミュレーションを行いましょう。
【シミュレーション例】
このように、かかる費用と予想される売却価格を書き出して比較検討することで、感情に流されず、最も合理的な判断を下すことができます。
不動産会社選びは、売却の成否を左右する最も重要な要素と言っても過言ではありません。タワーマンションの売却が得意な会社もあれば、郊外の古い戸建ての売却が得意な会社もあります。
あなたの物件と似たような条件(エリア、築年数、物件種別など)の物件を過去に扱った実績があるかどうかを、必ず確認しましょう。実績豊富な会社は、独自のノウハウや顧客リストを持っている可能性が高いです。
不動産を売却して利益が出た場合、税金がかかりますが、特定の条件を満たせば税金の負担を軽減できる特例制度があります。
特に、相続した空き家を売却する場合には「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家3,000万円控除)」が利用できる可能性があります。
これは、一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという非常に大きな制度です。(参照元:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁)
適用には細かい条件があるため、利用できるかどうかを不動産会社や税理士に必ず相談しましょう。賢く制度を活用することで、手元に残る金額を大きく増やすことができます。
「ボロ家が売れない」という悩みは、非常に重く、精神的な負担も大きいものです。しかし、売れないのには必ず理由があり、そしてその理由に応じた正しい解決策もまた、必ず存在します。
本記事で解説した6つの理由と5つの売却方法を参考に、まずはご自身の物件がどの状況にあるのかを客観的に分析してみてください。そして、一人で抱え込まず、信頼できる不動産の専門家に相談することから始めてみましょう。
放置すれば資産価値が下がり、リスクが増え続けるだけです。勇気を持って次の一歩を踏み出すことが、長年の悩みから解放されるための道筋となります。
