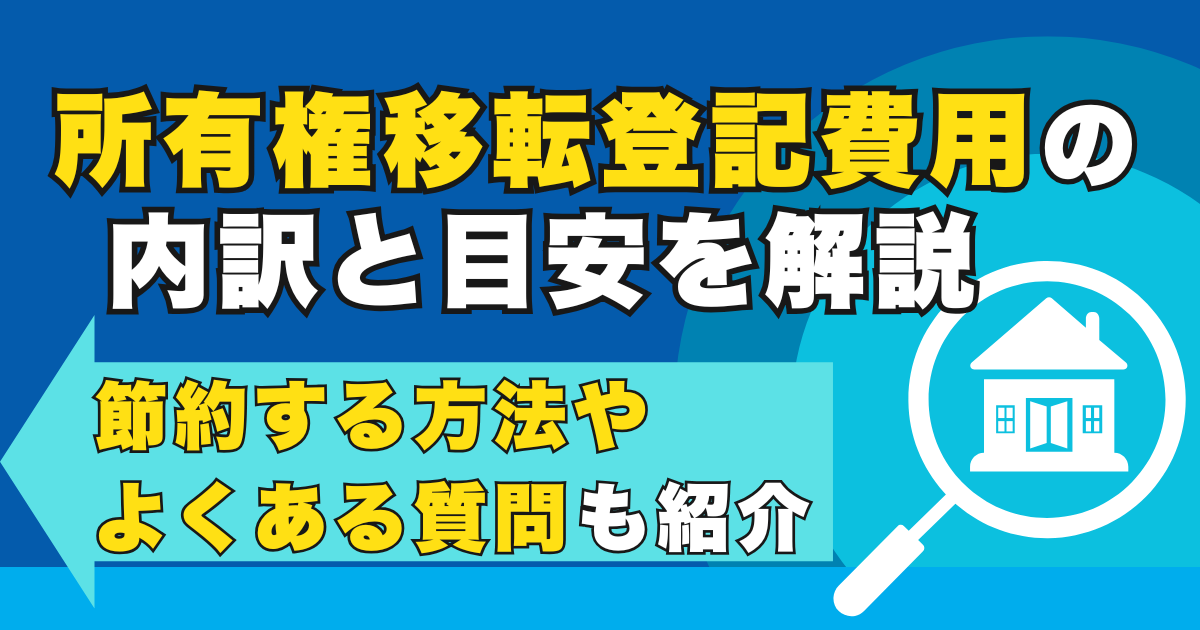
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...

団地の売却方法には「不動産仲介」と「不動産買取」の2種類があり、それぞれにメリットと注意点があります。
できるだけ高値で売却したいなら仲介を、早く確実に現金化したいなら買取を選ぶのが基本です。
特に築年数の古い団地を売る場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、団地売却の実績が豊富な会社を選ぶことが売却を成功させるためのポイントです。
この記事では、団地を少しでも高く売るための方法と注意点、さらに相続時の対応までをわかりやすく解説します。
※本記事では、公的団地で「団地内の分譲住戸(持ち家)」を売却するケースを想定しています。
団地を売却する方法は、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通り。
| 団地の売却方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 仲介 | ・市場価格で売れる可能性が高い・リフォームやリノベーションで価値を高められる場合がある | ・売却完了まで時間がかかる・内覧対応や価格交渉の負担がある・売れない場合もある・リフォームやリノベーションを行なっても、売却価格に反映できないことが多い |
| 買取 | ・現金化までが早い・内覧や広告の手間がかからない | ・売却価格は一般的に市場価格より安くなる・買取対象外になる団地もある・買取業者が限られる地域もある |
仲介は市場価格で売れる可能性が高くなります。ただし、売却までに時間がかかることも少なくありません。
一方で買取は、買主を探す手間がなく早期に現金化でき、内覧や広告の手間が少ない点がメリットです。ただし、一般的に市場価格よりも安くなります。
この章では、「仲介」と「買取」の売却方法を、さらに以下の4つのパターンに分けて詳しく解説します。
1つ目は、リフォームや修繕などを行わず、現況のまま市場に売り出す方法です。
リフォーム費用がかからないため、余分なコストをかけずに売却でき、築年数が古い団地でも、立地や管理状態が良ければ買い手が見つかる可能性があります。
一方で、内覧時の印象や老朽化が理由で、大幅な値引き交渉が発生したり、売却までに時間がかかることもあります。
とはいえ「まずはそのまま売り出して様子を見たい」「なるべく手間なく売りたい」という方には適した方法です。費用負担を抑えつつ、市場の反応を確認しながら売却を検討したい場合におすすめです。
次に、団地をリフォームして仲介で売却する方法です。壁紙の張り替えやキッチン・トイレなどの設備を部分的に新しくしてから売却します。
内装や設備を新しくすることで、購入希望者の第一印象が良くなり、早期の売却が期待できます。
国土交通省の「令和6年度住宅市場動向調査」でも、中古の集合住宅を選んだ理由として「リフォームされてきれいだったから」という回答が31.2%となっています。価格の安さや新築にこだわらないという理由に次いで3番目に高い結果で、リフォームが購入意欲に与える影響の大きさがわかります。
ただし、リフォームには費用が発生するため、費用対効果をしっかり見極めることが大切です。早期に売却を狙いたい場合におすすめの方法です。
団地をリノベーションして仲介で売却する方法では、間取りの変更や内装デザインの一新といった大規模な改修を行い、物件の付加価値を高めたうえで売却します。
築年数が古い団地でも、新築同様の内装や機能性を備えることで、早期売却や高値売却ができるケースがあります。
ただし、せっかく多額の費用をかけてリノベーションを行なっても、多くの買主の好みに合わなければ、かえって売りづらくなってしまいます。
リノベーション再販は、近年、買取り業者が多く取り入れている手法ですが、個人間の売買ではリスクが高すぎるため、おすすめできない手法です。
4つ目は、不動産会社が直接住戸を買い取ってくれる売却方法です。
仲介とは異なり、一般の買主を探す必要がないため、短期間で現金化でき、確実に売却したい場合に向いています。内覧対応や広告活動も不要で、手間をかけずに済むのも大きなメリットです。
また、築年数が古い団地や再建築不可の物件でも買取対象となるケースがあるため、売却が難しい物件の選択肢としても有効です。
ただし、通常は市場価格よりも低い金額での買取になるため、売却価格を重視したい人には向きません。売却価格が低くなってもスピードや確実性を重視したい場合におすすめの方法です。
築年数が古い団地でも、工夫次第で高く売却できる可能性があります。この章では、古い団地を高く売却するための4つのコツを解説します。
古い団地を少しでも高く売却したい場合は、仲介での売却が第一の選択肢となるでしょう。
不動産会社を通じて一般の買主に売却する仲介では、市場価格に近い金額で売れる可能性が高くなります。買取の場合、スピードや確実性に優れていますが、買取事業者が再販するためのリフォーム・リノベーション費用や利益が差し引かれるため、査定額は市場価格の7〜8割程度になるのが一般的です。
ただし、一口に「古い団地」といっても、新耐震基準で建てられたか、旧耐震基準で建てられたかによって、売却難易度が大きく異なるため注意してください。
建築基準法改正前の1981年5月31日までに建築確認を受けた旧耐震基準の団地では、購入希望者が限られるため、売却が長期化したり、大幅な値下げを余儀なくされたりするリスクが高まります。
一方、新耐震基準に適合している団地であれば、仲介で高値で売却できる可能性があります。
関連記事:ボロ家が売れない理由は?高値で売るための方法も合わせて解説
団地を高く売却するには、複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された価格とその根拠を比較することも重要です。
会社によって販売戦略や過去の取扱実績、見込み客の有無なども異なり、提示価格に差が出ることも珍しくありません。また、比較対象とする事例や数など、不動産会社の査定の仕方によっても、査定結果は異なります。
複数の会社を比較し、最も高くかつ根拠がある査定価格を提示した不動産会社を選ぶことで、より高値で売れる可能性が高まるでしょう。
団地の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことも、高く売却するために重要な要素です。
築年数が古い団地は、一般のマンションや戸建てとは異なる管理規約の制限、修繕積立金の状況、住民コミュニティ、耐震基準など、特有の問題を抱えているケースがあります。
実績のある会社は、このような団地特有のポイントを理解しているため、適切なターゲット設定や広告戦略を用いて売却活動を進めてくれます。結果的に成約までの期間や価格にも好影響を与えるでしょう。
自分の団地が持つ魅力を整理し、不動産会社の担当者に正確に伝えることも心がけてください。
「駅近」「買い物が便利」「陽当たりが良い」といった客観的な情報だけでなく、「朝はリビングに柔らかい日差しが差し込む」「敷地内の桜が春に見事に咲く」など、住んでいる人にしかわからない生活実感も価値ある情報となります。さらに、緑豊かな敷地環境やコミュニティの雰囲気、過去のリフォーム履歴などもアピールポイントとして効果的です。
これらの魅力は、販売図面や広告に反映できるものもあり、内覧時の印象アップにもつながるため、高値売却の可能性が高まるでしょう。
団地の売却相場は、単に築年数や面積だけでは語れません。不動産会社は以下のようなさまざまな条件について確認し、近隣の実績や価格帯と照らし合わせて価格の査定を行います。
売却を検討する際は、地域ごとの傾向や市場環境を踏まえ、査定価格の根拠についてもしっかりと把握しておくことが大切です。
団地を売却する時は、トラブルやリスクを回避できるよう、注意点を理解し、準備を整えた上で売却活動を進めましょう。この章では、4つの注意点を解説します。
築年数が古い団地を売却する際は、買い手が住宅ローンの審査で不利になる可能性がある点に注意しましょう。
多くの金融機関では、築年数だけを理由に住宅ローンの利用を制限しているわけではありません。しかし、築古の物件は担保評価が低く算定される傾向があり、その結果、希望額どおりの融資を受けられなかったり、返済期間が15~20年以内に短縮されるケースもあります。
特に1981年(昭和56年)以前に建築された旧耐震基準の建物では、安全性の面から審査が厳しくなる傾向が見られます。購入希望者がいてもローン条件の制約により成約まで時間を要することがあるため、事前に対応策を検討しておくことが大切です。
団地を売却する時は、管理組合が定める「管理規約」に基づく制限があることに注意が必要です。
団地では、住民全体で構成される管理組合が、建物の維持管理や居住環境の保全を目的に独自のルール(管理規約や使用細則)を設けています。
また、専有部分のリフォーム内容に制限があったり、事業用途への転用が禁止されているなど、売却後の活用に影響する可能性もあります。
スムーズに売却を進めるには、売却前に管理規約を確認し、不動産会社にも共有しておくことが大切です。
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた団地は、旧耐震基準で建てられているため、現行の耐震性能を満たしていない可能性があります。
旧耐震基準で建てられた物件は、安全性の懸念から買い手が敬遠しやすく、売却価格や成約スピードに影響します。
また、買い手にとっては、住宅ローンの利用が難しくなったり、税制上の優遇措置を受けられなかったりという金銭的なデメリットもあります。
住宅金融支援機構が提供する長期固定金利ローン「フラット35」には独自の技術基準があり、旧耐震基準の物件は原則利用できません。民間の金融機関も、旧耐震基準の建物は担保価値を低く見積もるため融資には消極的です。
また、マイホーム購入時に受けられる「住宅ローン控除(減税)」「登録免許税の軽減」「不動産取得税の軽減」といった各種優遇措置も、原則として新耐震基準に適合していることが条件です。
例外的に、住宅ローン控除や不動産取得税の軽減の適用を受けるためには、耐震基準適合証明書等の書類が必要です。耐震改修工事を実施している場合は、売却時に重要な材料となるため、事前に確認し、必要に応じて証明書類を準備しておくことをおすすめします。
過去に自殺や事件などがあった場合や、周辺に嫌悪施設(ゴミ処理場、墓地など)が存在する場合は「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」として、買主に事前に伝える義務(告知義務)がある点にも注意が必要です。また、雨漏れや耐震強度不足などの「物理的瑕疵」、建築基準法や消防法違反などの「法的瑕疵」も同様です。告知を怠ると、契約不適合責任により売却後に契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあるので注意しましょう。
これらの瑕疵に該当するケースは、以下の通りです。
| 特徴 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 心理的瑕疵 | そこに住むことに対して、買主が「気味が悪い」と感じるような心理的な抵抗を覚える事柄 | ・物件内での自殺や殺人、事故死など※老衰や転落などの事故死は、告知義務は発生しない |
| 環境的瑕疵 | 物件の周辺に、不快感や嫌悪感を与える状況がある | ・騒音や振動・悪臭・日照や眺望の阻害・嫌悪感や不安感を与える周辺施設(墓地、火葬場、葬儀場、刑務所、暴力団事務所、ゴミ焼却場、風俗店、パチンコ店など) |
| 物理的瑕疵 | 物件そのものに物理的な不具合や瑕疵がある場合 | 雨漏りがあるシロアリが出る |
| 法的瑕疵 | 建築基準法や都市計画法、消防法に対して違反があり使用制限がかかっている状態 | 防災扉や消火器が設置されていないなど |
※参照:全国宅地建物取引業協会連合会|心理的・環境的瑕疵について(下)
心理的瑕疵の告知の範囲や方法については、国土交通省のガイドラインなども参考にして、不動産会社と連携して適切に対応することが重要です。事実を正直に開示することで、トラブル回避と信頼ある取引につながります。
団地の売却は、以下のような流れで進めることが一般的です。
| STEP1 | 相場の調査・査定依頼 | 相場を調査したうえで、複数の不動産会社に査定を依頼し、価格や対応力を比較するのがポイントです。 |
|---|---|---|
| STEP2 | 媒介契約の締結 | 依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約(専属専任・専任・一般のいずれか)を結び、売却活動をスタートします。 |
| STEP3 | 売却活動の開始 | 内覧時はできるだけ室内を清潔に保ち、物件の魅力が伝わるよう配慮しましょう。 |
| STEP4 | 内覧対応 | 買い手が見つかれば、売買契約を締結し、手付金を受け取ります。 |
| STEP5 | 売買契約の締結・手付金の受け取り | 条件がまとまったら手付金を受け取り、売買契約を締結。 |
| STEP6 | 決済・物件の引き渡し | 最終的に残代金の決済と所有権移転登記を行い、鍵を引き渡して売却完了です。 |
なお、以下の書類も必要になります。
団地特有の注意点として、管理組合との手続きが発生することもあるため、管理会社や理事会への確認も忘れずに行いましょう。早めに準備を整えることで、売却をスムーズに進めることができるはずです。
団地を相続した時は、所有権の名義変更の手続き(相続登記)が必要になります。また、相続後に発生する税金や、空き家のまま放置するリスクも押さえておきたいポイントです。この章では、団地を相続する時に知っておきたい3つのポイントを紹介します。
団地を相続したら、故人名義の不動産を相続人名義に変更する「相続登記」を完了させないといけません。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく不動産の取得した日から3年以内に手続きをしなければ、過料が科される可能性もあります。相続登記には、遺言書または遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、固定資産評価証明書などの書類が必要です。
団地を相続した後に空き家として放置すると、さまざまなリスクが発生します。
まず、使っていなくても管理費・修繕積立金・固定資産税などの維持費が継続的にかかり、金銭的な負担はかかり続けます。また、建物の劣化や設備トラブルによって資産価値の低下や近隣住民とのトラブルにもつながります。
団地を相続してから売却するまでには、さまざまな税金が発生します。
| 相続した時 | 相続登記のための登録免許税、相続税もかかる場合もある |
|---|---|
| 保有期間中 | 毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税・都市計画税がかかる |
| 売却した時 | 売買契約書にかかる印紙税や、売却益が出た場合の譲渡所得税・住民税が発生する可能性がある |
「こんなに税金がかかるなんて知らなかった」とならないためにも、どのような税負担が発生するかを正しく理解しておきましょう。
団地の売却難易度は、物件の状態や立地、築年数などによって大きく左右されます。あなたの団地の売却難易度を確認するには以下のポイントを押さえておきましょう。
「いいえ」が多いと難易度が高い可能性があると考えましょう。
築年数が古い団地でも、条件がよければ仲介によって市場価格での売却を目指すことができ、リフォームやリノベーションによって価値を高める選択肢もあります。一方で、築年数が古い団地の売却では、住宅ローンの利用制限、耐震基準、管理組合のルールなど、団地特有の課題も無視できません。
まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、自分の団地に最適な売却戦略を検討することが、高値売却への第一歩となるでしょう。
