
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
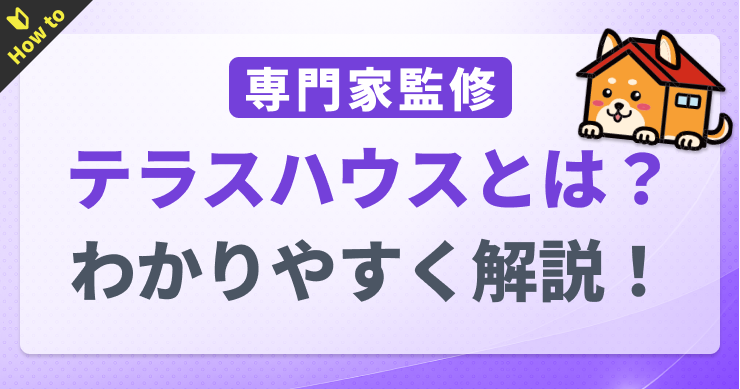
「テラスハウスって何?マンションや戸建てとどう違うの?」と疑問を感じていませんか?
住宅選びに迷っていると、つい見た目や家賃で決めがちですが、実は知らないと損する落とし穴も潜んでいます。
この記事を読むと
テラスハウスとは、隣家と壁を挟んで横に連なる建物で、その上下階を1世帯がまるごと使える住まいのことです。
各住戸が独立した玄関や専用の庭・駐車スペースを持ち、一方でマンションのような共用玄関や廊下はなく、一戸建てに近い住み心地が特徴です。
建物の構造上はタウンハウスと同じ「長屋建」に分類されます。ただ、テラスハウスもタウンハウスも建築基準法などに正式な定義はありません。では「タウンハウスと何が違うの?」と疑問に思いますよね。
テラスハウスとタウンハウスは、見た目(建物の構造)は同じですが、建物が建つ敷地の権利関係の違いにより、不動産実務では区別されます。
タウンハウスでは敷地を共有しているのに対して、テラスハウスでは敷地の境界が明確になっています。そのため、テラスハウスはより自由度のある長屋と言えるでしょう。
【監修者コメント】
長屋建は、国土交通省の建築動態統計調査で「2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、‥‥「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる」と定義されています。
<テラスハウスの特徴>
| 特徴項目 | 内容 |
|---|---|
| 階層構造 | 上下階が1世帯で完結する2階建てが中心 |
| 出入口 | 各住戸が独立した玄関を持ち、共用部はなし |
| 隣接形式 | 両隣の家と壁を共有(片側または両側) |
| 法的分類 | 建築基準法上「長屋」に該当することが多い |
| 普及背景 | 公団住宅や低層集合住宅の供給政策により全国に広がった |
テラスハウスには具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。この記事では賃貸や購入時に注意が必要なポイントも解説します。
テラスハウスの最大のメリットは、上下階を独占できる一戸建てのような暮らしを、マンションよりも手頃な価格で実現しやすい点です。
上下階を専有できるため、集合住宅にありがちな「上の足音」「階下の苦情」といった悩みから解放されやすくなります。
特に小さな子どもがいる家庭や、音に敏感な方にとっては大きな利点となるでしょう。
【テラスハウスに住むメリット】
テラスハウスは子どものいる暮らしや、上下階の音に敏感な人と相性がよいため、音や空間に対するストレスを抑えやすい住宅形式といえます。
戸建ての良さと集合住宅の手軽さを併せ持つ点が、多くの人に選ばれる理由でしょう。
一方で、良いとこ取りに見えるテラスハウスにも見落とされがちな落とし穴があります。
外観が新しくても、法的な制限や隣家との関係性といったリスクは見た目ではわかりません。特に購入する場合、将来的な資産価値については慎重な判断が求められます。
【テラスハウスに住むデメリット】
購入前や入居前には、建築図面や登記簿を確認し、リスクの芽を早めにつぶすことが肝心です。疑問点は必ず不動産会社に質問し、納得のいく説明を得るようにしましょう。
テラスハウスを賃貸や購入で検討する際には、見た目や賃料だけでは判断できない、重要なチェックポイントが5つあります。
契約後に後悔しないためにも、これらのポイントは事前にしっかりと把握しておくことが肝要です。物件の魅力だけでなく、潜在的なリスクにも目を向ける必要があります。
これらのポイントは、入居後の生活の質や将来的なトラブルの回避に直結します。
特に法的な側面や建物の状態は、専門的な知識がないと見落としがちです。不動産会社の説明を鵜呑みにせず、自らも疑問を持って確認することが、失敗しない住まい選びにつながるでしょう。
テラスハウスの賃貸契約では、建物だけでなく土地の権利関係も確認が必要です。テラスハウス物件と紹介されていても、敷地が共有であるタウンハウス物件の可能性もあるからです。敷地が共有であるタウンハウス物件の場合、分譲マンションと同じように原則として区分所有法が適用されます。
特に共有持分や借地権付き物件は、居住や管理、更新のルールに影響を与えることがあります。契約書に記載されている所有形態や借地条件を確認しましょう。
こうした情報は重要事項説明書に記載されているため、契約前の読み込みと不動産会社への確認を丁寧に行うことが大切です。不明瞭な点はそのままにせず、納得できるまで質問しましょう。
テラスハウスでは隣家と壁を共有しているため、防音性の高さが快適な暮らしに直結します。構造によっては生活音が壁越しに伝わりやすいため、日常生活にストレスを感じることもあります。契約前には必ず確認しましょう。
防音性能は、図面だけでは判断しづらいため、現地での体感と具体的な質問がポイントになります。静かな生活環境を求める際は、特に重視すべき項目です。
【監修者コメント】
隣家との間にある壁(界壁)には建築基準法第30条が適用され「隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減する」ための性能が求められます。界壁は原則として、小屋裏または天井裏まで達する必要がありますが、天井の遮音性能が基準を満たす場合はこの限りではありません。
この項目は主に、物件を購入する際のポイントです。テラスハウスの中には、建築基準法上の接道義務を満たしていないために、再建築が認められない物件もあります。
接道義務とは、建物を建てる敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定のことです。外観や間取りに魅力を感じても、再建築不可であると、将来的な売却や改築に大きな制限がかかります。
再建築の可否は、将来の資産価値や自由な住み方に直結します。契約前には、接道条件や都市計画の確認を怠らず、具体的な制約事項を把握しておくことが大切ですS。
テラスハウスは戸建てに近い居住スタイルである一方、近隣との距離が近いため、共有スペースや敷地内ルールの存在が生活に影響します。
明文化されていない運用ルールがあることも多いため、事前の確認が重要です。特に、敷地が共有であるタウンハウス物件だった場合、区分所有法に基づいて規約が定められている場合があります。
テラスハウスでは、隣人との適度な距離感と明確なルールが快適さを左右します。契約前には、現地だけでなく管理者やオーナーの説明にも注意を払いましょう。
この項目は主に、物件を購入する際のポイントです。テラスハウスは原則として、建築基準法上は「長屋建」として扱われます。長屋扱いの住宅は、火災保険や住宅ローンの審査において、一戸建て住宅に比べて不利になる可能性があります。
火災保険料には築年数や耐火性能の方が大きく影響しますが、隣家と壁を共有しているテラスハウスは延焼リスクが高いという理由で火災保険料が高く設定されるかもしれません。
こうした制約は、実際の申し込み段階で初めて問題になるケースもあります。安心して入居するためには、事前に保険会社や金融機関への相談を行い、条件を把握した上で契約を判断することが望まれます。
テラスハウスは、賃貸にも購入にも向いた中間タイプの住まいとして人気があります。
ただし、法律上の制限や、音・採光といった物理的な問題を軽視してはいけません。メリットとデメリットを正しく理解し、自身のライフスタイルに合っているかを見極めることが重要です。
家は、暮らしの基盤になる場所です。外観や賃料だけで判断せず、「自分たちの生活に合っているか」「将来も安心できるか」を考えて選ぶことが、満足度の高い住まい選びにつながるでしょう。
