
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
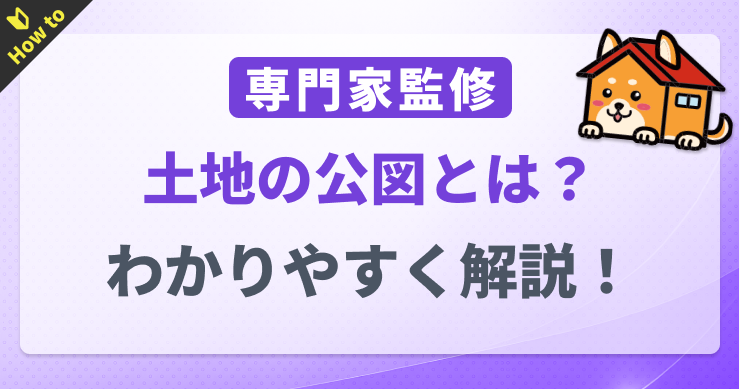
土地や不動産の調査で「公図の見方や取得方法がわからない…」と悩んでいませんか?はじめて公図に触れる方や、境界や地番の確認が必要な場面で戸惑っている方に向けて、この記事をお届けします。
<この記事でわかること>
公図とは、土地の位置や形状、隣接関係などを示した図面のことで、不動産取引や登記の場面で広く利用されます。地図に準ずる図面と呼ばれることもあります。
登記簿の読み取りや境界確認において、 公図の定義を正確に理解することは「非常に重要」です。
公図の基本概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公図とは | 土地の位置・形状・境界関係などを示す図面(地図に準ずる資料) |
| 法的根拠 | 不動産登記法第14条などに基づいて、地図に準ずる図面として法務局が備え付けている |
| 作成主体 | 法務局または登記所が管理・作成 |
| 用途 | 境界確認、売買時の参考、地番調査、権利関係の確認など |
| 正式名称 | 地図に準ずる図面(公図) |
公図は、土地に関するさまざまな情報を読み解くための出発点となる資料といえます。ただし、土地の参考図面であるため、必ずしも現況と一致するとは限りません。
特に古い地域では測量精度が低い場合もあるため、あくまで位置関係の目安として使用されることが多いです。
公図は、不動産登記における補助的な図面として、土地の所在や形状、地番の配置を確認するために利用されます。
ただし、地図とは異なり、必ずしも現況を正確に反映しているわけではないため、登記情報の一部としての性質が強い点に注意が必要です。
【公図の主な特徴と目的】
公図の目的は単に土地の図を示すことではなく、登記簿と一体となって不動産情報を補完することにあります。
現地の正確な測量図とは異なる点を理解したうえで、登記実務や権利調査の判断材料として活用するのが適切です。
「公図」と「地図」は、どちらも土地の位置や形状を表す資料ですが、その目的や精度、作成主体には明確な違いがあります。
公図は、不動産登記のために法務局が備え付けているもので、登記簿に記載された地番や筆界を図面として表現しています。
一方、一般的な地図は、主に位置の把握や移動のために作られたもので、公的な登記の根拠とはなりません。
公図と地図の比較表
| 項目 | 公図 | 地図 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 法務局 | 国土地理院、自治体、地図会社など |
| 精度 | 古いものは精度が低い場合あり | 現況に近い情報が多い |
| 用途 | 登記の補足資料、筆界・地番の確認 | 位置確認、移動、ナビゲーションなど |
| 法的効力 | 原則なし(参考資料扱い) | なし |
| 基準 | 登記簿記載情報に基づく | 実測・航空写真・GISなどに基づく |
また、法務局が備え付ける「地図」にはいくつかの種類があります。
たとえば、「地図に準ずる図面」や「14条地図」などがあり、それぞれ作成の根拠や精度が異なります。
縮尺も一般的には600分の1(1/600)や、地域によっては1/2など複数のパターンが存在し、土地の詳細確認には向いていない場合もあります。
はじめて公図を見ると、複雑な線や記号に戸惑うかもしれません。しかし、基本的な構成を理解すれば簡単に読み解けるようになるはずです。
公図には、土地の地番や筆界(境界線)、赤線・青線などの記号が示されており、それぞれ意味があります。
これらの情報を正しく読み取ることで、土地の範囲や隣接関係を把握することができます。
公図を読み解く際に重要なのが、「地番」と「筆界(ふひかい)」の理解です。
地番とは、土地ごとに割り振られた番号で、登記簿と照合する際の基本情報となります。一方、筆界は隣接地との境界線を指し、土地の権利範囲を確認するうえで非常に重要です。
ただし、筆界と実際の境界(現況境界)が一致するとは限らないため、公図の読み方には注意が必要です。
地番と筆界の違いと見分けるポイント
| 項目 | 地番 | 筆界 |
|---|---|---|
| 意味 | 各筆(区画)に割り振られた番号 | 各筆を区切る境界線 |
| 表示 | 公図上に「○○番」などと記載 | 直線や点線で区画を分ける線 |
| 目的 | 登記記録と一致させるための識別 | 土地の権利範囲を明確にするため |
| 注意点 | 同一番地内に複数の筆がある場合も | 実際の現地境界とずれる可能性がある |
筆界の正確な位置は公図だけでは判断できないことがあるため、境界確認の際は隣接地の所有者との立会いや現地調査が必要になる場合もあります。
とはいえ、公図上の地番や筆界の理解はその第一歩です。境界をめぐるトラブルの予防策としても有効な知識といえるでしょう。
公図には、通常の地番や筆界線のほかに、「赤線」「青線」「無地番地」といった特殊な表記が含まれていることがあります。
これらはすべて公共用地の可能性がある土地を示す記号であるため、土地取引や開発において注意が必要です。
公図上における特殊表記の意味
これらの土地は登記簿に記載されていないことがあり、民間での所有・売買が制限されるケースもあります。
そのため、赤線・青線・無地番地が含まれるかどうかを確認することは、土地の購入や境界確認時における重大なチェックポイントとなります。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
不動産の調査や土地取引を行う際、公図を取得して内容を確認することは非常に重要です。
公図の取得方法は大きく分けて3つの手段があります。
どの方法にもメリット・注意点があり、目的や手間、費用に応じて選択するのが一般的です。
最もオーソドックスな公図の取得方法は、法務局の窓口で直接申請する方法です。
公図が必要な土地の地番をあらかじめ調べておき、申請書に必要事項を記入して提出すれば、その場で取得することができます。登記所の管轄を事前に確認しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
法務局で公図を取得する流れ
法務局での申請は、担当者に直接相談できるという安心感があります。
ただし、平日の日中に限られるため、時間の都合がつきやすい人向けの方法といえるでしょう。
法務省が提供する「登記情報提供サービス」を通じて、インターネットからも公図は取得することができます。
オンライン申請は、時間や場所を問わずアクセスできる点が最大の利点で、遠方の土地や急ぎの確認にも適しています。
ただし、提供されるのは閲覧用のPDFファイル(正式な登記簿ではない)である点に注意が必要です。
オンライン申請での取得の手順(登記情報提供サービス)
オンライン申請での取得は非常に便利ですが、出力した公図は正式な証明文書ではありません。そのため、提出用として法務局発行の原本が求められる場合もあります。
用途に応じて、閲覧用か証明用かを判断しながら使い分けることが大切です。
法務局への郵送申請によっても公図は取得できます。郵送申請は、法務局が遠方にある場合や、窓口に行く時間が取れない場合に有効な手段です。
ただし、必要な書類を揃える手間や、到着までの時間がかかるため、申請ミスを避けるための慎重な準備が求められます。
郵送取得の手順と注意点
郵送申請は誰でも利用できる汎用性の高い方法ですが、ミスがあった場合は再申請となります。そのため、事前の地番確認と記入内容のチェックが特に重要です。
急ぎの案件には不向きなため、時間に余裕を持った利用をおすすめします。
公図は、不動産登記の補足資料としてだけでなく、さまざまな実務的なシーンでも活用されています。
特に土地の売買、相続、境界確認といった場面では、公図が重要な判断材料となることも多いです。
ただし、利用の際にはいくつかの注意点があり、誤解やトラブルを防ぐためには正しい理解が不可欠です。
【公図を利用する際の主な注意点と対処法】
| 注意点 | 理由 | 対処法 |
|---|---|---|
| 公図は測量図ではない | 公図は簡易図で、現地形状とズレることがあるから | 必ず確定測量図と突き合わせて形状を確認する |
| 筆界は境界を完全に示さない | 公図の筆界線は参考情報に過ぎず、法的な境界確定力を持たないから | 境界確認書や隣接地権者との立会いで境界を確定する |
| 地番と住所は一致しないことがある | 地番は登記上の番号で、行政上の住所とは異なるから | 登記簿や地番図を参照し、実際の土地と照合する |
| 古い公図は精度が著しく低い場合がある | 明治期の地租改正図を踏襲していることがあり、現況と大きく異なるから | 最新の図面や現地調査結果と比較して誤差を確認する |
公図には地域によって、「あだ図」と呼ばれる古い図面が用いられている場合があります。
こうした図面は作成時期や精度に大きなばらつきがあるため、登記の判断資料として用いる際は特に注意が必要です。
本記事では、「公図とは何か」という基礎から、見方・取得方法・活用時の注意点までをわかりやすく解説しました。
公図は、不動産登記を補助する資料として非常に便利ですが、その精度や内容には限界があるため、現況や他の資料との併用が欠かせません。
公図に関する重要なポイントまとめ
公図は「知っておくと役立つ」だけでなく、「知らずに使うと危ない」資料でもあります。
正確な知識と適切な運用で、安心・安全な不動産取引や土地調査につなげましょう。
