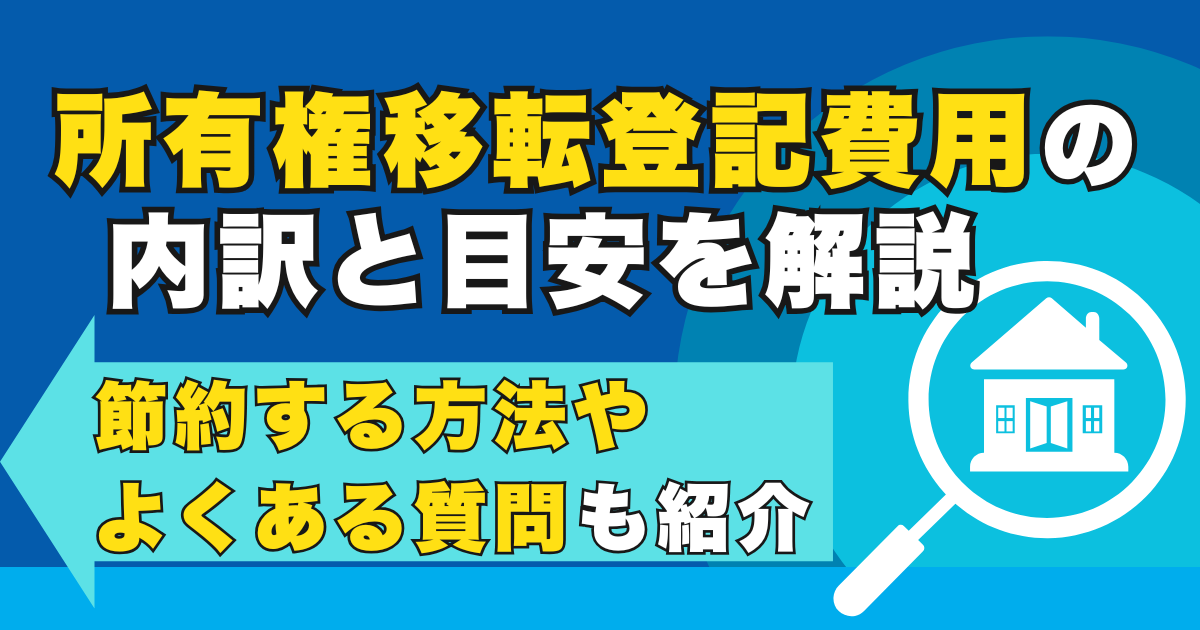
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...
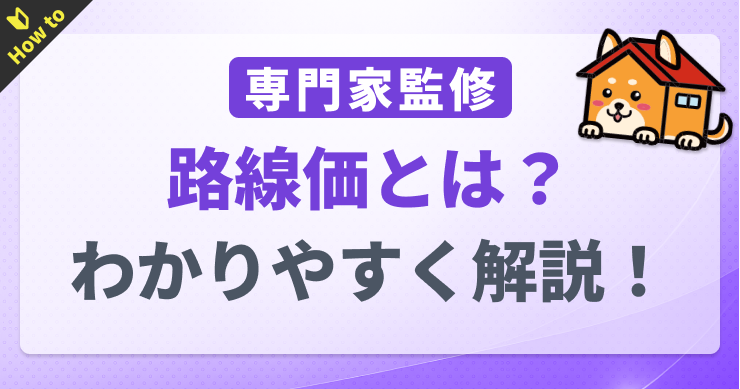
路線価は、相続税や贈与税を計算するうえで重要な指標ですが、その仕組みや見方を誤解している人も少なくありません。
知らないままにしておくと、税額が本来とは異なる額となり、「申告漏れ」と指摘される可能性もあります。
この記事では、路線価の基礎知識から路線価図の見方、計算手順、固定資産税評価額との違いまでを、わかりやすく解説します。
【記事でわかること】
路線価(ろせんか)とは、国税庁が毎年 7 月に公開する「道路ごとに定められた標準宅地 1 ㎡当たりの評価額」です。
主に、相続税や贈与税を計算するときの課税評価に用いられます。公示価格(国が発表する地価公示価格)の 約 80 %を目安 に設定されており、一般的な取引価格である「実勢価格」とは異なります。路線価の単位は千円/㎡で表示されており、たとえば、路線価図に「250D」と記載されている場合、1㎡あたりの路線価は、250,000円となります。
| 価格の種類 | 公表主体 | 使い道 | 金額の目安(公示地価との比較) |
| 路線価 | 国税庁 | 相続税・贈与税の課税評価 | 約 80% |
| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 固定資産税・都市計画税 | 約 70% |
| 実勢価格(市場価格) | 市場(売主と買主) | 実際の売買・投資判断 | ほぼ 100 % |
それぞれの価格を言い換えると、以下のように表現することができます。
【例】公示価格が 1 ㎡あたり10 万円の土地の場合
路線価は標準的な宅地を前提とした価格であるため、個別の土地形状(奥行きや間口・形状・高低差など)によって、補正率を掛けて評価額を調整します。
たとえば、奥行きが短い狭小地や不整形な土地は、補正率を適用して評価額を下げる仕組みとなっています。
路線価は、国税庁のサイト(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表)で、誰でも閲覧できます。自宅や相続予定地の評価額の目安を確認しておけば、専門家に相談する際もスムーズに進められるでしょう。
【監修者コメント】相続税申告の際に路線価を見落としたまま実勢価格で評価してしまい、あとから追徴課税を受けるケースが毎年のように報告されます。国税庁が監修する『財産評価基本通達(土地)』 には「路線価方式を原則とする」旨が明記されており、実勢価格を採用するなら合理的な根拠が不可欠です。
路線価と固定資産税評価額では、管轄する機関や目的などが異なります。
路線価は国税庁が相続税や贈与税を算出するために定めた指標で、公示価格のおおむね 8 割に設定されます。一方、固定資産税評価額は、市区町村が固定資産税・都市計画税を算出するための評価額で、公示価格の 7 割程度になります。
| 項目 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
| 管轄 | 国税庁 | 市区町村 |
| 主な税目 | 相続税・贈与税 | 固定資産税・都市計画税 |
| 水準目安 | 公示価格の約 8 割 | 公示価格の約 7 割 |
| 更新頻度 | 毎年(7 月公表) | 3 年ごとに評価替え |
| 公開方法 | 路線価図 | 課税通知書・全国地価マップ |
路線価と固定資産税評価額は、どちらも評価額が低いほど課税額が下がります。ただし、固定資産税評価額は 3 年間据え置かれるため、市況の変動をリアルタイムで反映していません。相続税評価では、毎年更新される路線価がより現況を反映します。
相続税では、土地の評価額が課税額に直結します。国税庁が毎年発表する路線価をもとに算出することで、相続人ごとに結果がばらつきません。税務署も、路線価をもとにチェックするため、申告額を一致させるには路線価の確認が欠かせません。
路線価を無視して相続税額を算出すると、低すぎる評価になり「申告漏れ」と指摘されるおそれがあります。反対に、高すぎる評価をもとに申告してしまうと、後から減額請求(更正の請求)が必要となり、余計な手間が発生してしまいます。
相続開始から申告期限(10か月以内)までの限られた期間でスムーズに評価作業を進めるには、路線価図を早めに取得し、補正率を含めた正確な計算を行ったうえで評価額を算出することが大切です。
国税庁が毎年7月上旬に更新する「路線価図・評価倍率表」は、パソコンやスマートフォンから無料で閲覧できます。相続税・贈与税の申告時の土地評価、相続対策の試算、保有資産の現状把握など、さまざまな用途に活用できます。
路線価図は、以下の方法で検索することができます。
【検索手順】
国税庁の「路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)にアクセス
【監修者コメント】
住所と地番のズレが大きい地域では、事前に市区町村の固定資産税課で 固定資産評価証明書( 300~400 円ほど)を取得してから検索すると、路線価図の町字特定が早くなるでしょう。
「全国地価マップ」は(一財)資産評価システム研究センターが提供する無料の地図ツールです。路線価のほか、固定資産税評価額、地価公示価格、都道府県地価調査価格を閲覧できます。
【検索手順】
※調査地の道路の路線価を確認※固定資産税評価額も確認可
全国地価マップでは、直接検索窓に住所を入力するほか、住所一覧から検索することもできます(「都道府県→市区→町→番地」と順に検索)。
参照:一般財団法人 資産評価システム研究センター|全国地価マップ
【監修者コメント】
司法書士や税理士は、申告書に添付する「土地及び家屋の評価明細書」に国税庁の路線価図データ と地価マップの両方を引用することが多いです。評価額の裏付け資料が二つそろうことで、税務調査での照会事項が減り、審査がスムーズになります。
国税庁のサイトで閲覧する路線価図には、該当する道路に「250D」などの記号が付されています。路線価は、1㎡あたりの価格を千円単位で表示しているため、これは「1㎡あたり25万円」の路線価を示していることになります。
また、末尾のアルファベットは、借地権割合を表しています。借地権割合とは、その土地の評価のうち借地権がどれくらいの割合を占めるかを示すものです。
借地権割合はA~Gまであり、それぞれの借地権割合は次のとおりです。
| 記号 | 借地権合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
借地権割合が高いほど、その土地の借地としての評価が高くなります。
つまり、路線価図で「250D」と表示されている場合、その土地は、路線価が250000円/㎡、借地権割合が60%であることがわかります。
路線価は「数字+記号」の構成で表示されています。数字が1㎡あたりの路線価、記号が借地権割合を示します。路線価は、千円単位の表示 です。
| 符号例 | 意味 |
| 250D | 路線価25万円/㎡・借地権割合60% |
| 200B | 路線価20万円/㎡・借地権割合80% |
| 150G | 路線価15万円/㎡・借地権割合30% |
数字部分は、そのまま円換算できるので、1,000円単位の表示であることを忘れなければ間違えないでしょう。
国税庁のサイトには、奥行の長さや角地など、土地の形状の違いを評価額で調整するための調整率表が用意されています。
土地の状況によっての補正率を考慮し忘れると評価額がずれるため、評価額の確認だけで終わらせないことが重要です。
【主な補正率の種類】
たとえば、奥行価格補正率では、普通住宅地の場合、奥行距離が4メートル未満の土地は、0.90の補正率を乗じて土地を評価します。
一方で、奥行が長い土地(たとえば24メートル以上28メートル未満)の場合は、0.97の補正率を乗じて評価額を算出します。補正率を考慮することで、土地の評価額が下がれば、相続税額も少なくできるため、重要な指標といえます。
補正率の種類は複数ありますが、該当するものがあれば併用することが可能です。
参照:国税庁|土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31 年1月分以降用)
【監修者コメント】
路線価図を PDF で保存しただけでは根拠が弱いと指摘されることがあります。補正率を適用した計算シート(Excel など)と、当該区分の通達該当ページを一緒に提出すると、税務署からの照会が激減します。
相続や贈与の申告では、対象地の評価額を「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかで算出します。「路線価方式」は路線価が設定されている地域で使用し、「倍率方式」は路線価が設定されていない地域(倍率地域)で用います。
【相続税評価額を確認する手順】
どちらの方式でも、評価額や倍率が毎年見直されるため、最新データの確認が不可欠です。土地の評価額は1円単位で課税額に直結するため、小数点以下の端数処理にも注意しましょう。
路線価方式では、国税庁の路線価図で確認した路線価に、土地の形状によって適用する補正率を掛け合わせ、最後に地積(㎡)を乗じて算出します。
| 計算ステップ | 具体的な式 | 補足 |
| 基本単価 | 路線価(円/㎡) | 例:25万円/㎡ |
| 補正 | 路線価 × 各種補正率 | 奥行補正0.96 × 角地補正1.05 など |
| 評価額の計算 | 補正後の単価 × 地積(㎡) | 端数処理は評価通達に準拠 |
補正率が重複した場合でも、順序の影響を受けません。たとえば、複数の補正率を乗じる場合でも、25万円/㎡×0.96×1.05=25万2,000円/㎡となります。土地面積は、登記事項証明書や固定資産税課の評価証明書などで、正確な地積を把握しましょう。
倍率方式は、路線価が設定されていない郊外や山間部などで使われます。市区町村が定める固定資産税評価額に、国税庁が公表する評価倍率を乗じて算出します。
【計算の手順】
倍率は地区によって0.7〜1.3程度と幅があり、路線価とともに毎年更新されます。
また、固定資産税評価額は3年に1度の評価替えとなるため、必ず「申告基準日に有効な評価額か」を確認しましょう。【監修者コメント】
倍率方式地域でも、新たに都市計画道路が整備されるなど環境が急変すると、固定資産税評価額が大きく変わるケースがあります。相続発生前後で通知書を取り直し、評価替えを確認すると、過少申告リスクを回避できるでしょう。
路線価は、相続税・贈与税の土地評価で必ず必要となる重要な指標です。本記事では、以下の流れで路線価の基本から活用方法まで解説しました。
路線価は、単に「数字を読むだけ」では完結しない、奥深い評価制度です。しかし、調べ方や仕組み、計算手順を理解すれば、自宅や相続予定地の評価額の大まかな目安を把握することは可能です。
最終的な申告書作成や節税対策においては、税理士など専門家のサポートを受けると安心ですが、事前に路線価評価の仕組みを理解しておくことで、専門家との打ち合わせもスムーズに進むでしょう。
