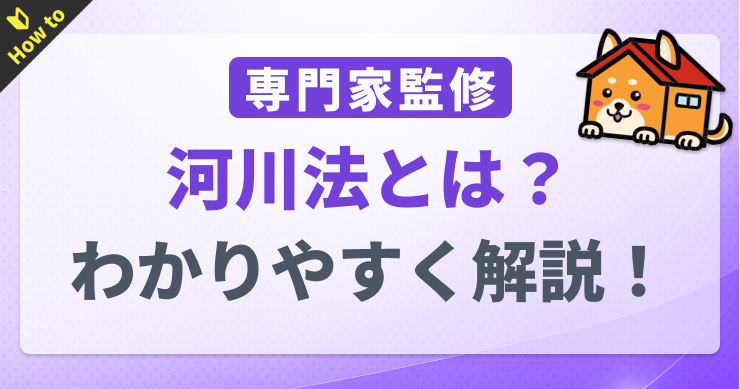
-
河川法とは?建築制限や規制内容をわかりやすく解説
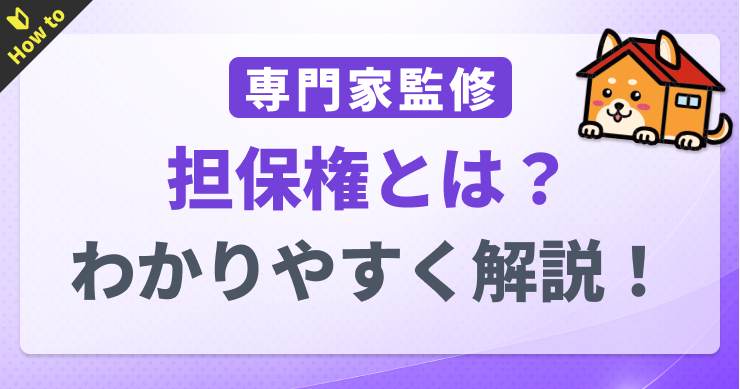
銀行から「担保」の話が出ると、専門用語が多くて内容がわかりにくく、「大切な資産を失ってしまうのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。担保権は、仕組みとリスクを正しく理解すれば、事業を守り、成長させるための心強い味方になります。
この記事を読めば、銀行担当者と対等に話せるだけの知識が身につきます。
この記事でわかること
「担保権」とは、万が一お金を返せなくなった場合に備えて、銀行などが貸したお金を回収しやすくするための「保険」のような権利です。
事業の運転資金や設備投資で融資を考えるとき、「担保」という言葉は避けて通れません。
お金を貸す側(銀行など)を「債権者」、お金を借りる側(あなた)を「債務者」と呼びます。
| ひとことで言うと | 具体的な役割・関係性 | |
| 債権者(銀行など) | お金を貸す側 | あなたに融資金を渡し、その見返りとして担保物件に対する担保権を持つ。 |
| 債務者(あなた) | お金を借りる側 | 銀行から融資金を受け取り、返済を約束する。万が一に備え、自身の担保物件を提供する。 |
| 融資金 | 借りるお金のこと | 銀行からあなたへと渡される、事業のための資金。 |
| 担保物件(例:不動産) | 返済の「保険」となるモノ | あなたが所有する資産。返済が困難になった場合に、銀行がこの物件からお金を回収することになる。 |
| 担保権 | 銀行が持つ「優先回収権」 | 銀行が担保物件に対して持つ法的な権利。この権利があるため、銀行は他の人より優先的に、かつスムーズに資金を回収できる。 |
債権者は、債務者が約束通りにお金を返してくれることを信頼して融資を行いますが、ビジネスには予期せぬ事態がつきものです。
万が一、返済が滞ってしまった場合に備えるのが担保権の役割となります。
銀行が担保を求める最大の理由は、貸したお金(債権)が回収できなくなるリスクを避けるためです。
もし担保がなければ、債務者の返済が滞った場合、債権者は法的な手続き(裁判など)を経て資産を差し押さえる必要があり、時間も手間もかかります。
しかし、あらかじめ担保権を設定しておくことで、他の債権者よりも優先的に、そしてよりスムーズに貸したお金を回収できるのです。
これは、あなたにとっても、担保を提供することで銀行の信頼を得て、より大きな金額の融資を受けられる可能性が広がるという側面もあります。
なお、債務者が複数の債務を抱えている場合には、「クロスデフォルト条項」を契約に盛り込むことで、債権者は他の契約上の債務不履行があった際にも対応できるようになり、リスク管理の強化につながります。
担保権と一言で言っても、その種類は一つではありません。まずは全体像を掴むために、大きな分類から見ていきましょう。担保権は、何を「保険」にするかによって、大きく2つに分けられます。
【担保権の種類と分類】
| 大カテゴリー | 中カテゴリー | 小カテゴリー |
| 担保権 | 物的担保 | 抵当権 |
| 質権 | ||
| 先取特権 | ||
| 留置権 | ||
| 人的担保 | 保証・連帯保証・根保証など |
「物的担保」は、土地や建物といった「モノ」を担保にする方法です。もし返済が滞った場合、銀行はそのモノを売却するなどして、貸したお金を回収します。
この記事で主に解説する抵当権や質権は、この物的担保に含まれます。
代表的な物的担保
まずは、「融資でよく使われるのは抵当権と質権」と、頭に入れておくと良いでしょう。 ちなみに、複数の担保権が設定されている場合は、優先順位によっては回収不能となってしまうケースも考えられます。
「人的担保」は、社長の家族や友人など、「ヒト」に保証人になってもらう方法です。債務者本人が返済できなくなった場合に、その保証人が代わりに返済義務を負うことになります。
中でも代表的なのが「連帯保証人」です。
通常の「保証人」は、債務者の支払が難しい状況になった場合に責任を負いますが、「連帯保証人」は債務者と同等の責任を負うため、債権者は請求開始と同時に連帯保証人に請求することもできます。
ただし、人的担保は保証人個人の資力に依存するリスクがあり、近年は極度額の定めにより回収が制限されることも考慮しなければなりません。
この章では、「物的担保」の中でも特に重要な、抵当権と質権について解説します。
数ある担保権の中でも、事業のための融資で最もよく利用されるのが、「抵当権」です。
抵当権の最大のポイントは、担保として提供した不動産を、これまで通り自分で使い続けられる点にあります。
たとえば、ご自宅を担保に融資を受けたとしても、そのまま家族と住み続けることができます。これが抵当権の大きなメリットです。
法律の世界では、抵当権について以下のように定められています。
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出典: 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十九条
少し難しい言葉ですが、要するに「担保にする不動産は手元に置いたままでOK。でも、万が一の時は、その不動産から優先的にお金を回収できますよ」ということです。
ただし、債務者側のリスクとして、担保不動産の価値が下落した状況で売却した場合、不動産を手放したのに残債が残る「担保割れ」が発生する可能性もあります。
抵当権とよく比較されるのが「質権」です。質権は、質屋をイメージすると分かりやすいでしょう。時計や宝石といった品物を店に預けて、その品物の価値の範囲内でお金を借ります。この場合、返済が終わるまで品物は手元に戻ってきません。
なお、質権の設定により品物を預けても、所有権そのものは移転しません。あくまで債権の担保として、目的物を債権者が占有する点が特徴です。
この「占有(モノを直接支配している状態)」が移るかどうかが、両者の決定的な違いです。
| 項目 | 抵当権 | 質権 |
| 主な対象 | 不動産(土地、建物など) | 動産(時計、宝石など)、権利(株式など) |
| 占有の移転 | 不要(設定後も所有者が使用を続けられる) | 必要(目的物を債権者に引き渡す必要がある) |
| 主な利用シーン | 住宅ローン、事業資金融資など | 質屋での借入れなど |
【監修者コメント】
抵当権で最も注意すべきは、万が一の時の「実行スピード」です。返済が滞ると、銀行はあなたが思っているよりもずっと早く、淡々と法的な手続きを進めます。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
さて、ここからは、あなたが最も不安に感じているであろう「万が一」の話をします。
もし、どうしても返済が続けられなくなってしまった場合、銀行は設定した担保権を「実行」に移します。
これは、担保にとった不動産などを売却し、その代金から貸したお金を回収する最終手段です。売却代金が残債以上であれば債務者へ支払われ、足りない場合は不足分の請求が継続されます。
担保権の実行は、ある日突然行われるわけではありません。通常、以下のようなステップで進んでいきます。
このプロセスは、精神的にも非常に辛いものです。
だからこそ、こうなる前に手を打つことが何よりも重要なのです。
【監修者コメント】
最も重要なのは、返済が苦しくなる「前」に、正直に銀行へ相談することです。「まだ大丈夫」ではなく「このままだと厳しくなりそうだ」という段階で相談してください。
銀行が最も困るのは、何も連絡がないまま返済が止まってしまうことです。事前に「来月の返済が少し厳しそうだ」と相談すれば、返済計画の見直し(リスケジュール)など、様々な選択肢を検討してくれる可能性があります。一人で抱え込まず、誠実に向き合う姿勢が、最悪の事態を避けるための最善策です。
ここまでで、担保権の基本とリスクについてご理解いただけたかと思います。最後に、経営者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
A. 抵当権を設定する場合、銀行との間で「抵当権設定契約」を結び、その内容を法務局で「登記」する必要があります。登記手続きには、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、実印などが必要となり、司法書士が代理人として手続きを行うのが一般的です。
A. 根抵当権は、何度も借入れと返済を繰り返す事業性融資でよく使われます。あらかじめ「極度額」という利用限度額を設定しておくことで、その範囲内で何度も融資を受けられる便利な仕組みです。一度きりの住宅ローンで使われる抵当権とは、その「繰り返し使えるか」という点で異なります。
A. はい、可能性は十分にあります。近年は、経営者本人以外の保証人を求めない「経営者保証ガイドライン」の運用が進んでいます。また、信用保証協会の保証を利用することで、保証人がいなくても融資を受けられる場合があります。まずは金融機関に相談してみてください。
今回は、担保権の基本、特に経営者に深く関わる抵当権について解説しました。
この記事のおさらい
担保権は、決して怖いだけのものではありません。その仕組みとリスクを正しく理解し、管理することで、あなたの事業を大きく成長させるための力強い資金調達手段となります。
この記事を読んで、ご自身の契約内容や返済計画に少しでも不安を感じたなら、どうか一人で抱え込まないでください。
お近くの司法書士会や法テラスなどでは、専門家への相談窓口を探すことができます。早期の相談が、あなたと、あなたが大切に育ててきた事業を守ることにつながるでしょう。
