
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
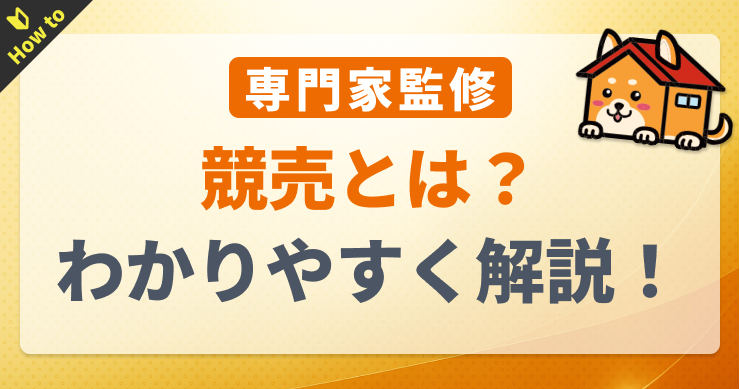
住宅ローンの返済が滞ると、最終的に不動産が「競売」にかけられる可能性があります。
競売とは、債務者が所有する不動産を裁判所が強制的に売却し、債権者が貸付金を回収するための法的手続きです。滞納をきっかけに、差押え、現地調査、情報公開を経て、最終的には入札・落札・明け渡しへと段階的に進行します。
全国競売評価ネットワークが公表しているデータによると、2023年4月から2024年3月の全国の競売件数は11,875件で、売却率は80.7%でした。(引用元:不動産競売の動向2024|全国競売評価ネットワーク)
競売には、売主が自ら売却活動を行う必要がなく、費用の負担も少ないというメリットがあります。一方で、市場相場よりも売却価格が低くなりやすく、情報公開によるプライバシーの侵害や、強制退去のリスクといったデメリットも伴います。
本記事では、競売の流れやそのメリット・デメリットに加え、任意売却などの回避策についても、わかりやすく解説します。
不動産における「競売(けいばい)」とは、住宅ローンなどの返済を長期滞納した場合に、貸した側(債権者)が裁判所に申し立てを行い、その不動産を強制的に売却することで、貸したお金を回収する制度です。
一度、裁判所によって「競売開始」が決定されると、その家に住み続けることができず、落札した人から立ち退きを求められます。
また、競売では相場の6〜8割程度で安く落札されるのが一般的であるため、売却代金を債務返済に充てても、借金が残る可能性があります。
なお、競売物件は、裁判所の入札に参加すれば一般の人でも購入が可能です。自宅用以外にも、不動産投資目的で購入されるケースもあります。
| 担保不動産競売 | 強制競売 | |
| 担保の有無 | あり | なし |
| 申立人 | 担保権者(金融機関など) | 債権者(貸金業者など) |
| 主な原因 | 住宅ローンなどの滞納 | 借金、クレジットカード利用分などの滞納 |
| 目的 | 担保権(主に抵当権)を実行して債権を回収 | 金銭債権の回収手段として不動産を処分 |
| 手続き | 抵当権に基づく競売 | 裁判で債務が認められた後に申立が可能 |
※参照元:競売ファイル・競売手続説明書 – BIT 不動産競売物件情報サイト
不動産の競売には、大きく分けて「担保不動産競売」と「強制競売」の2種類があります。
「担保不動産競売」は、住宅ローンなどの返済が滞納した場合に、債権者(金融機関など)が担保となっている不動産を、裁判所を通じて売却するものです。
一方、「強制競売」は、借金やクレジットカードの利用分などの金銭債権が滞納した場合に、債権者(貸金業者、個人など)が裁判所に申し立て、担保のない不動産を差し押さえて売却する手続きです。
どちらも裁判所を通じて不動産を売却する手続きですが、「担保の有無」や「債権者の種類」が主な違いとなります。
「担保不動産競売」と「強制競売」では、住宅ローンを担保にした「担保不動産競売」の方が一般的であるため、本記事ではこちらを主に扱います。
| 競売 | 任意売却 | |
| 売却の主体 | 裁判所 | 債務者本人(債権者の同意が必要) |
| 手続きの主導者 | 債権者と裁判所 | 債務者と不動産会社(+債権者) |
| 売却価格 | 相場より安い傾向 | 相場に近い価格で売却できる可能性あり |
| 引っ越し時期の調整 | 難しい(強制退去の場合あり) | 調整しやすい |
| 手続きの柔軟性 | なし(強制的に進行) | あり(条件交渉が可能) |
※参照元:任意売却の手続について(パンフレット、任売書式1~12)|独立行政法人住宅金融支援機構
「競売」と「任意売却」は、どちらも住宅ローンの返済が困難になった際に、不動産を売却して債務を整理する方法ですが、大きな違いは「売却の進め方」です。
金融機関が裁判所に申し立てて不動産を強制的に売却する「競売」は、市場価格より安く売られることが多く、所有者の意思は反映されません。
一方で、債権者の同意を得て自主的に不動産会社などを通じて市場で売却する「任意売却」は、相場に近い価格で売却できる場合があります。また、引越し時期の調整がしやすく、状況によっては残債務の相談に応じてもらえる可能性もあります。
「競売物件=やばい」とは一概にはいえません。競売物件が「やばい」といわれる理由は、売る側・買う側それぞれに特有のリスクがあるためです。
売る側は、売却価格が安くなりやすく、プライバシーの侵害や強制退去といった精神的・物理的なリスクが伴います。
一方で買う側には、内覧ができない、瑕疵担保責任がない、占有者が退去しない可能性があるなどのリスクがあります。
このようなリスクはありますが、内容を正しく理解すれば適切に対処できるでしょう。したがって、競売物件は「やばい」のではなく、「正しい知識と入念な準備が必要となる取引」といえます。
競売は、民事執行法に基づいて手続きが進められ、滞納から明渡しまでにかかる期間は約1年です。
ここでは、競売の具体的な流れと、回避するためのポイントを解説します。
住宅ローンなどの返済が一定期間遅れると、まずは金融機関などの債権者から電話や書面による督促が行われます。それでも支払いがされない場合、催告書が届き、一定の期間内に支払うことを正式に求められます。
Point
この段階は、民法第412条における「履行遅滞」の状態で、まだ競売が確定したわけではありません。つまり、まだ競売を回避できる余地があるということです。
返済条件の変更(リスケジュール)交渉や、債務整理、支援制度の相談も可能です。また、任意売却を検討・開始する絶好のタイミングでもあります。
滞納が続くと、金融機関などの債権者から「期限の利益喪失通知」が届きます。これは、分割払いの権利を失い、一括返済を求められる状態を意味します。
Point
民法第137条における「期限の利益の喪失」の状態で、通知が届くと支払い猶予が実質的に消滅し、法的な債務履行が強く求められる段階に入ります。
そのため、ここが競売回避の最終ラインともいえる重要なタイミングです。一括返済が難しい場合は、速やかに任意売却の手続きを進める必要があります。また、債務整理(個人再生や自己破産など)を視野に入れた専門家への相談も急務です。
一括返済ができずに放置すると、金融機関などの債権者は裁判所に競売開始の申し立てを行い、担保不動産に対する「差押え」が実行されます。差押えは、債務者が勝手に売却や処分できないようにする法的措置です。
Point
差押えが実行された時点で、物件は競売に向けた準備段階へと進みます。
この段階でも、任意売却による競売の回避は可能ですが、差押え後は債権者(金融機関など)の承諾が必要となるため、交渉のハードルがやや上がります。時間が限られているため、速やかに不動産会社や専門家に相談し、売却活動の準備を始めることが重要です。
差押えが完了すると、裁判所から「競売開始決定予告通知書」が届きます。これは、正式に競売手続きが始まることを意味する通知です。同時に、登記簿上にも「競売開始決定」が記載されます。
Point
正式に競売手続きが始まり、物件が市場に出される準備段階に入ります。
ただし、入札公告がされる前であれば、債権者と協議のうえで任意売却に切り替えることも可能です。債権者の同意を得られれば、裁判所へ競売取り下げの申請が可能なケースもあります。競売を避けたい場合は、ここが実質的に最後のタイミングです。
競売手続きが始まると、裁判所の依頼を受けた「執行官」や「評価人」が物件の調査に訪れます(民事執行法第57条・58条)。物件の状況や占有者の有無、物理的な状態などを確認し、「評価書」「現況調査報告書」「物件明細書」が作成されます。
Point
この時点になると、物件の情報が裁判所により詳細に把握されるため、債権者が競売を選択する意向を強めるケースが多くなります。そのため、任意売却による競売の回避は現実的に難しくなり始める段階です。
まだ交渉の余地はあるものの、スピードと専門的な対応がより重要になります。
物件の詳細情報が「BIT(不動産競売物件情報サイト)」に公開され、間取り図や評価額、調査報告書などが誰でも閲覧可能となります。一般公開されたことで、物件の競売が公に知られるため、所有者や近隣への影響も出やすくなります。
Point
物件の競売手続きは実質的に終盤を迎え、任意売却はほぼ不可能です。また、たとえ全額返済したとしても、債権者の同意や裁判所の許可がない限り、競売の取り下げは困難です。
定められた期間内に購入希望者が入札を行い、裁判所で開札・落札が行われます。最も高い金額を提示した人が「落札者」として決定します。
Point
開札日に落札者が決まると、元の所有者の権利は事実上ここで終了します。以降は「買受人」に対する所有権移転と引渡し義務が発生し、競売の回避はほぼ不可能になります。
落札者が代金を納付すると、所有権が正式に移転し、元の所有者(占有者)は物件の明渡し義務を負います。
新しい所有者は任意の退去を求め、応じなければ裁判所を通じて強制執行(断行)を申し立てることが可能です。
Point
円満な退去を目的に「引っ越し支援金(立退料)」の支払いを提案されるケースもあります。この段階では競売の回避はできませんが、立退き交渉によって負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、競売のメリットについて解説します。
競売は、民事執行法に基づいて裁判所が主導する手続きなので、所有者自身が不動産会社に売却を依頼したり、購入希望者と交渉を行う必要はありません。物件の評価、公告、入札の管理などはすべて裁判所とその指名を受けた執行官・鑑定人が担当します。
一般的な売却に必要な広告活動や内覧対応、価格交渉といったプロセスが不要であり、売主にとって精神的・時間的負担が大きく軽減されます。
競売では、裁判所が作成・管理する「評価書」「物件明細書」「現況調査報告書」のほか、入札結果や買受人の決定などの情報が、「BIT(不動産競売物件情報)」を通じて誰でも閲覧できます。
不動産鑑定士による適正な評価額をもとに入札による市場原理で価格が決定されるため、価格操作が起きにくく、公平性も保たれます。
価格や売却条件が第三者にも明らかになる仕組みにより、民間の不動産売買と比べて「知らないうちに損をする」といったリスクが少なく、手続き全体が透明に進められる点が競売のメリットです。
競売では、売却活動を裁判所が主導して行うため、不動産会社に仲介を依頼する必要がなく、宅建業法46条に基づく仲介手数料も発生しません。また、広告費や現地調査に関する費用も裁判所の管理下で処理されるため、売主側がこれらの出費を負担することもありません。
任意売却では通常、仲介手数料や登記費用、広告費が必要になりますが、競売ではこれらのコストを抑えられます。
ただし、滞納した税金や抵当権の抹消に伴う費用は、売却代金から差し引かれる場合があるため注意が必要です。
競売は、民事執行法に基づく法的手続きを段階的に進める仕組みのため、任意売却などに比べて、売却・退去までにある程度時間の猶予があります。一般的には「競売開始決定通知」から「入札・落札」「明け渡し」まで、少なくとも6か月以上かかるケースが多いです。
急な退去を迫られないため、転居先の確保や生活再建の準備などを計画的に進められるでしょう。精神的な余裕を持って対応できる点が、競売の意外なメリットともいえます。
競売には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。本章ではデメリットについて解説します。
一般的に競売物件の落札価格は、相場の60〜80%程度になるケースが多く、売主にとっては残債が多く残るリスクがあります。
大幅に安くなる理由は、内覧ができないことや瑕疵担保責任が免除されている点など、買主にとっての不確定要素が価格に反映されるためです。また、入札による価格決定方式のため、必ずしも高値で売却されるとは限りません。
競売にかけられると、物件に関する詳細な情報が裁判所の公告を通じて一般公開されます。具体的には「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」などが作成され、住所、間取り、外観・内観の写真、占有状況、修繕の必要性などが「BIT(不動産競売物件情報)」に掲載されます。
近隣住民や知人に競売の事実が知られる可能性があるので、人目を避けて問題を解決したい方は、精神的な負担が大きくなるかもしれません。
物件が落札されると、新しい所有者(買受人)から退去を求められます。退去に応じない場合、裁判所は、民事執行法第168条の2に基づいて「明渡し命令」を発令します。履行されなければ「明渡しの強制執行」が行われ、執行官が立ち会い、荷物の搬出や鍵の交換などが実施されます。
競売では、明渡しを行うために転居先の確保や引っ越しの準備が必要です。精神的・物理的な負担が大きい点がデメリットといえます。
| 回避方法 | 特徴 | 向いている人 |
| 任意売却 | 家を自分で売ってローンを返す | まだ競売手続きが始まっていない人 |
| リースバック | 家を売ったあとも賃貸で住み続けられる | 引き続き同じ家に住みたい人 |
| 返済のリスケジュール | 毎月の返済額や支払い期限を見直す | 一時的な収入減や支出増で返済が難しい人 |
| 債務整理 | 弁護士などを通じて借金を減らしたり整理する | 多重債務や収入での返済が根本的に困難な人 |
競売を回避するためには、状況に応じてさまざまな手段があります。それぞれ特徴や向いているケースが異なるため、自身の経済状況や今後の生活設計に合った方法を選ぶことが重要です。
任意売却は、債権者の同意を得て不動産を市場で売却し、競売を回避する手段です。入札前であれば競売開始決定後でも可能な場合があります。
また、市場価格に近い金額で売却できるため、競売よりも高く売れる傾向があり、残債を減らせるメリットがあります。一方で、債権者との交渉や手続きが複雑なため、不動産会社や弁護士、司法書士など専門家のサポートが欠かせません。
リースバックは、自宅を第三者に売却し、その後は賃貸契約を結んで同じ家に住み続ける方法です。物件の所有権が移転することで差押えや競売の根拠がなくなり、手続きを取り下げてもらえる可能性があります。
住み慣れた家を手放さずに済む点が大きなメリットですが、売却価格が低くなることや将来的に再購入できないケースもあります。そのため、リースバックの契約条件を十分に確認した上で検討しましょう。
返済のリスケジュールは、金融機関に返済猶予や返済額の減額を申し出ることです。一時的に競売手続きを停止できる可能性がある方法ですが、実現には債権者の同意が欠かせません。
成功すれば住み続けることができる反面、審査は厳しく長期的な解決にはなりにくい点がデメリットです。収入が一時的に落ち込んでいるケースでは、有効な手段といえます。
債務整理は、法的手続きによって借金を減額または免除し、返済の負担を軽減する方法です。
中でも「民事再生(住宅資金特別条項付き)」は、住宅を手放さずに借金整理ができる可能性があります。また、自己破産でも裁判所に「執行停止」を申し立てることで、競売を一時的に中止できる場合があります。
ただし、手続きは複雑です。弁護士の介入がほぼ必須となり、信用情報に傷がつくデメリットもあります。
競売とは、住宅ローンなどの返済が滞った際に、裁判所の手続きによって不動産が強制的に売却される制度です。売却活動を自分で行う必要がなく、費用負担も抑えられるといったメリットがある一方で、売却価格が市場よりも低くなりやすく、物件情報が公開されプライバシーが侵害されるといったデメリットも存在します。
ただし、任意売却やリースバック、返済条件の見直し(リスケジュール)、債務整理などを早期に検討・実行することで、競売を回避できる可能性も十分にあります。
競売の仕組みとその回避策について正しく理解し、自分に合った対応を早めに検討することが大切です。
