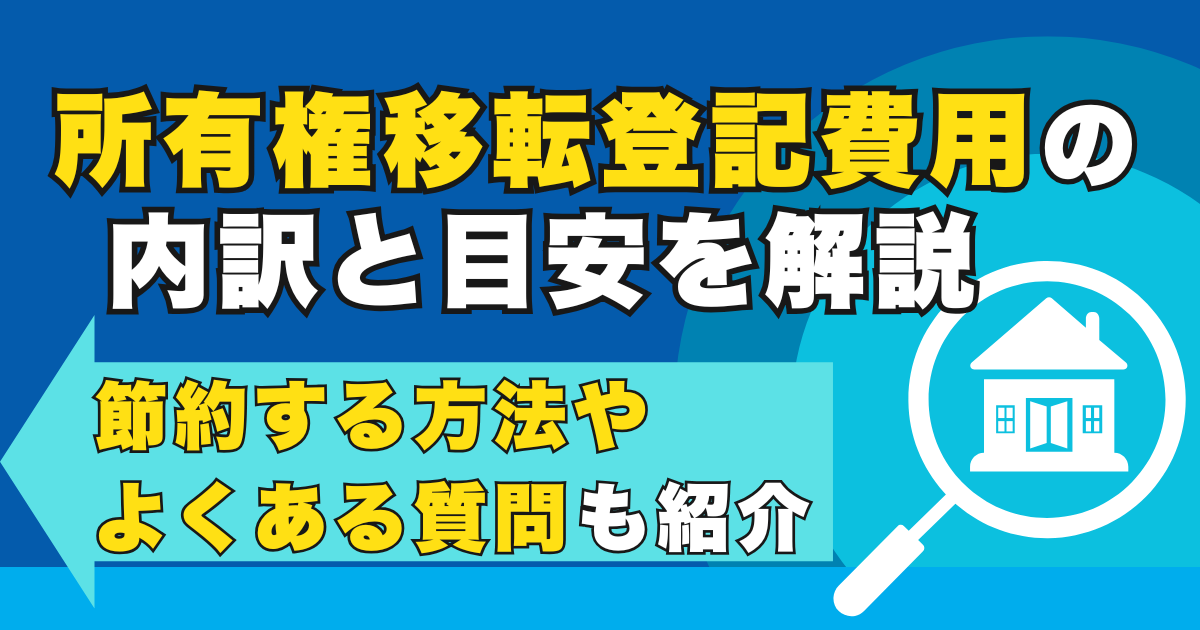
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...
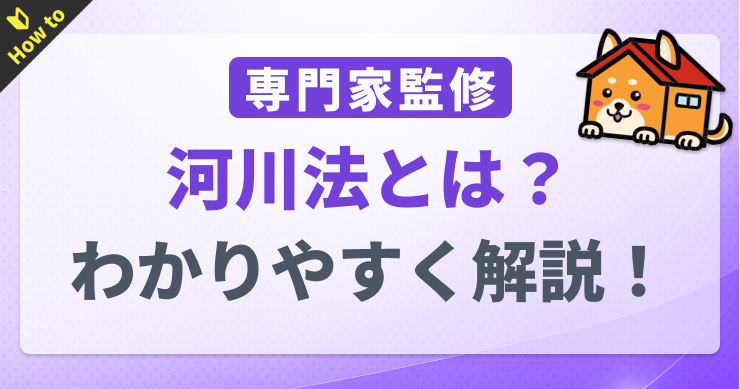
河川から近い会社の敷地で、倉庫の建設や駐車場の整備などを計画していませんか?
本記事では、企業の担当者が押さえるべき「河川法」について、基本的な内容や規制対象となる行為、罰則、そして許可申請の具体的な流れについて、法律の専門家である私・八木が分かりやすく解説します。
この記事を読めば、上司への報告や行政との事前相談に必要な知識が身につき、法務リスクを回避することができます。
<この記事でわかること>
【このパートをまとめると】
河川法は、「治水」「利水」「環境整備・保全」の3つを目的とし、公共の安全と利益を守る法律です。企業の活動もこれらの目的に沿う必要があります。
企業のコンプライアンス担当者として河川法を理解する上で、まず押さえるべきは、この法律が持つ「治水」「利水」「環境整備・保全」という3つの大きな目的です。
なぜなら、行政があなたの会社の計画を審査する際、「その計画がこれらの目的を阻害しないか」という視点で判断するからです。法律の条文をただ暗記するのではなく、この「精神」を理解することが、円滑な手続きへの第一歩となります。
最も重要な目的は「治水」です。これは、大雨による洪水や高潮といった水害から、国民の生命や財産を守ることを指します。
堤防の整備や川底の掘削などの事業がこれにあたりますが、同時に、堤防の強度を弱らせるような行為や、水の流れを妨げるような建築物を規制することも、「治水」の重要な役割です。
次に「利水」です。川の水は、生活用水や農業用水、そして企業の生産活動に必要な工業用水など、社会にとって不可欠な資源です。
「利水」は、この貴重な資源を特定の誰かが独占することなく、社会全体で公平かつ安定的に利用できるように調整する役割を担っています。
最後は「環境整備・保全」です。「環境整備・保全」は、1997年の法改正で追加された比較的新しい目的で、川を単なるインフラではなく、動植物の生息地や人々の憩いの場となる豊かな自然環境として保全・整備していくことを目指しています。
このように、あなたの会社の計画が、「災害を誘発しない」「水の利用を妨げない」「環境を損なわない」ことを示す必要があるのです。
【このパートをまとめると】
「一級・二級河川」に隣接し、「河川区域・河川保全区域」内での工事は、河川法の規制対象となる可能性が高くなります。まずはこの2点を確認することが重要です。
法律の目的を理解したら、次に確認すべきは「自社の計画が規制対象となるかどうか」です。
企業担当者が最初に確認すべきポイントは以下の2点です。
この2点を確認しておけば、その後の調査や相談が格段にスムーズになります。
まず、計画地に面している川が、どの種類の河川に分類されるかを確認しましょう。河川法が適用される川は、「一級河川」「二級河川」「準用河川」の3つです。
| 河川の種類 | 管理者 | 特徴・判断のポイント |
|---|---|---|
| 一級河川 | 国(国土交通大臣) | 国土保全上、特に重要な水系。国が直接管理する、いわば「メジャーリーグの川」です。 |
| 二級河川 | 都道府県知事 | 一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川。地域の主要な川がこれにあたります。 |
| 準用河川 | 市町村長 | 一級・二級河川以外で、市町村長が指定し管理する川。一級・二級ほど重要ではないものの、地域の発展に欠かせない河川です。 |
| 普通河川 | (管理義務なし) | 上記以外の川。水路など。河川法の適用を受けません。 |
重要なのは、計画地横の川が「普通河川」であれば、河川法の許可申請は不要になるという点です。 川の種類は、都道府県や市町村のウェブサイト、または直接の問い合わせにより確認できます。
河川法の対象となる川だと分かったら、次は計画地が「河川区域」または「河川保全区域」に含まれるかを確認します。
国土交通省の定義によれば、河川区域とは「河川を管理するために必要な区域で、堤防と堤防に挟まれた間の区間」を指します。
簡単に言うと、川の水が流れている部分と、それを囲む堤防敷地を含めたエリアのことです。専門用語では、堤防より川側の土地を「堤外地(ていがいち)」と呼びます。
一方で河川保全区域は、「堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域」です。
もし、あなたの会社の計画地が堤防に守られている宅地側(堤内地)であっても、この河川保全区域に指定されていれば規制の対象となります。
これらの区域は、自治体が公開している「河川現況台帳」などで確認できますが、最も確実なのは、管轄の土木事務所などに直接問い合わせることです。
【このパートをまとめると】
倉庫の建設や資材置き場の設置、土地の掘削など、河川区域内での土地の形状を変える行為や独占的な利用は、原則として許可が必要です。
あなたの会社の計画が「河川区域内」で行われる可能性があると分かった場合、具体的にどのような行為に許可が必要となるのでしょうか。
法律の条文と、企業の具体的な活動を結びつけて理解していきましょう。この章では、多くの企業担当者が直面する「倉庫建設」を代表例として解説します。
「占用」とは、独占的・継続的に使用することを指します。
たとえば、倉庫を建てる工事期間中、資材を置いたり、作業ヤードとして利用したり、仮設の通路を設置したりする行為は、この「土地の占用」に該当し、河川管理者(国や都道府県)の許可が必要です。
「工作物」とは、土地に定着する人工物のことです。
倉庫や事務所といった建物を新築・改築する行為は、この条文の対象となります。また、建設計画に伴って駐車場を整備したり、敷地を囲うフェンスを設置したりする行為も、「工作物の新築」と見なされるのが一般的です。
土地の形状や性質を変更する行為も、許可の対象です。
倉庫を建てるための基礎工事(土地の掘削)や、駐車場として利用するために地面を平らにする造成工事(盛土・切土)などが該当します。これらの工事は、水の流れや堤防の強度に影響を与える可能性があるため、厳しく審査されます。
<監修者からの一言アドバイス>
「一時的な利用だから」「小規模な工事だから」といった自己判断は絶対に避けてください。判断に迷う場合は、どんなに些細なことでも、必ず行政に確認しましょう。
【このパートをまとめると】
申請の成否は「事前協議」で9割方決まります。完璧な書類準備より、計画の初期段階で管轄の土木事務所に相談することが成功への近道です。
許可が必要だと分かったら、申請手続きをします。この章では、申請から許可までの流れについて解説します。
まずは、申請から許可までの全体像を掴みましょう。
申請から許可までのステップの中で、あなたの会社のプロジェクトの成否を分ける最も重要なポイントは、ステップ1の「事前協議」です。
<監修者からの一言アドバイス>
申請の成否は「事前協議」で9割方決まります。完璧な書類を準備する前に、まず計画のラフな図面だけを持って担当窓口に相談へ行きましょう。
なぜなら、この段階で「こういう計画ですが、行政として特に懸念される点はどこですか?」と率直に尋ねることで、審査のキーポイントや担当者の本音を引き出すことができるからです。
事前協議を経て、計画の方向性が固まったら、以下の書類を準備して申請に臨みます。(※自治体により異なる場合があります)
申請窓口は、川の種類によって異なります。
一級河川でも、国土交通大臣が管理していない「指定区間」で工事する場合は、都道府県を経由して申請するケースもあります。そのため、直接自治体に電話で問い合わせるのが確実です。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
【このパートをまとめると】
無許可行為には、懲役や罰金といった厳しい罰則や、工事の中止命令や原状回復費用など、事業継続を揺るがすリスクが存在します。
コンプライアンス担当者として、万が一、河川法に違反してしまった場合のリスクも正確に把握しておく必要があります。
無許可で工作物の新築(第26条違反)などを行った場合、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という厳しい罰則が科される可能性があります。これは、担当者個人だけでなく、法人にも適用される(両罰規定)ことがある、重い罰則です。
罰則以上に企業にとって大きなダメージとなるのが、事業そのものへの影響です。
違反が発覚した場合、河川管理者は工事の中止命令や、設置した工作物の撤去(原状回復)命令を出すことができます。これにより、プロジェクトが完全に頓挫するだけでなく、多額の損失が発生します。
さらに、「法令を遵守しない企業」というレッテルは、企業の社会的信用を大きく損なうことにもつながりかねません。
最後に、これまで多くの担当者の方から寄せられた、よくある質問にお答えします。
A. 申請手数料自体は、多くの自治体で無料または数千円程度です。ただし、申請に必要な図面作成などを外部の専門家(測量士や行政書士)に依頼する場合は、その分の費用が発生します。
期間については、事前協議から許可が下りるまで、スムーズに進んだ場合でも3ヶ月は見込んでおくとよいでしょう。行政の繁忙期や計画の複雑さによっては、それ以上かかる場合もあります。
A. まず、不許可となった理由を必ず書面で確認してください。その上で、指摘された問題点をクリアできるような代替案を検討し、再度、事前協議からチャレンジすることになります。重要なのは、一度の不許可で諦めないことです。行政側も、適法な計画であれば許可しない理由はありません。粘り強く対話を重ねることが大切です。
A. 許可が必要となる可能性が高いです。特に、工作物の規模や形状、構造が変わるような大規模な修繕は、新規の設置と同様に「改築」と見なされます。元の状態と全く同じように直す「維持・修繕」であれば許可が不要な場合もありますが、自己判断せず、必ず事前に管轄窓口に確認してください。
A. 掃除や散水、簡単な洗い物といった、他の人の利用や環境にほとんど影響を与えない一時的な水の利用は、「自由使用」として許可は不要とされています。ただし、ポンプを設置して継続的に大量の水を汲み上げるような場合は、「流水の占用」として許可(水利権)が必要となります。
ここまでお疲れ様でした。最後に、企業の担当者として河川法に対応するための要点を改めて確認しましょう。
お分かりいただけたように、河川法への対応は、決して担当者一人で抱え込めるものではありません。しかし、正しい知識と手順を踏まえ、行政というパートナーと対話することで、必ず道は拓けます。
会社の建設計画が河川法に該当するか不安なまま進めるのは、大きなリスクを伴います。
まずは、本記事を参考に、自社の計画をセルフチェックしてみてください。
そして、少しでも該当する可能性がある場合は、計画の初期段階で管轄の土木事務所に事前相談のアポイントを取りましょう。
