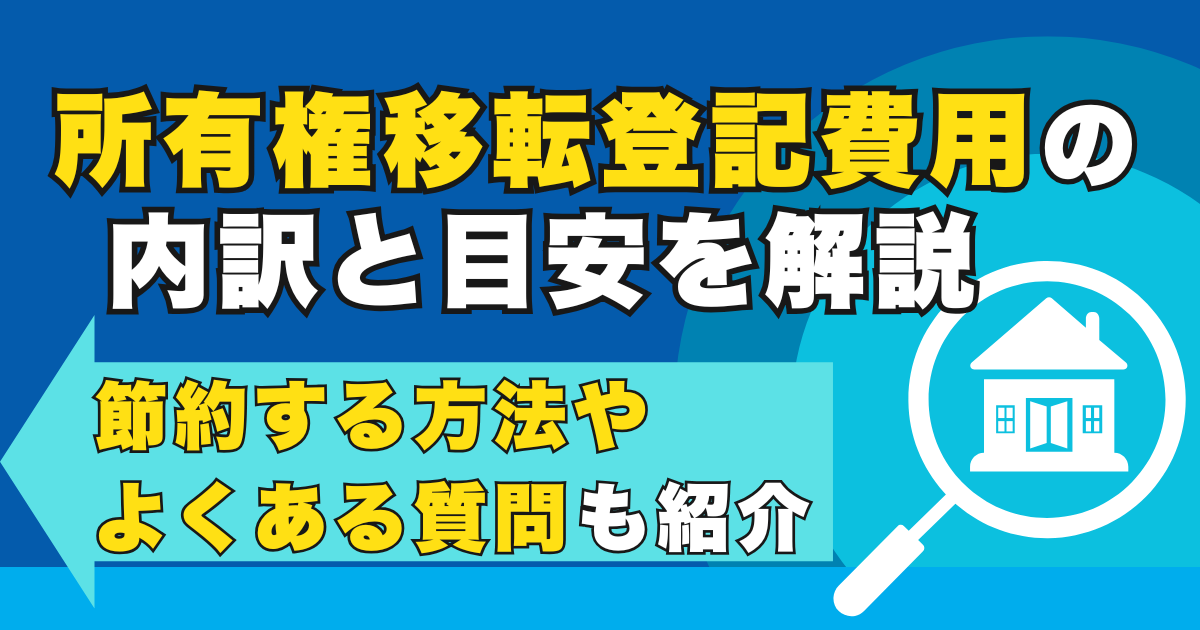
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...
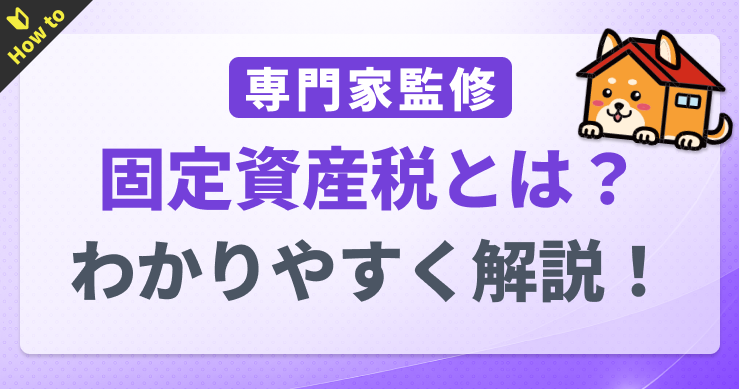
固定資産税は、土地や建物といった「固定資産」に対して課される市町村税(東京23区の場合は都税)です。
税額は、基本的に「固定資産税評価額 × 税率」で算出しますが、特に新築の住宅には税の負担を大きく減らしてくれる「軽減措置」が用意されています。
この記事では、固定資産税の基本的な知識から税額の計算方法まで、専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく解説していきます。
読み終わる頃には、固定資産税に対する「難しそう」「不安」といった漠然とした印象はなくなり、計画的に対応できるようになっているはずです。
【免責事項】
本記事は2025年7月現在の情報に基づき作成しています。税制改正等により、内容が変更される可能性があります。正確な情報については、必ずお住まいの市町村にご確認ください。
この章では、固定資産税の基本的な仕組みや目的を確認していきましょう。「そもそも何のための税金で、どのような資産に対してかかるのか」を知ることで、税制への理解が深まります。
「そもそも、なぜ、固定資産税を払わなければいけないのだろう?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
総務省のウェブサイトでも説明されている通り、固定資産税は、私たちが暮らす市町村の重要な財源となっています。
たとえば、毎日使う公園や道路の整備、小中学校の運営、ゴミ収集や介護・福祉などの行政サービスの多くが、この固定資産税によって支えられています。
つまり、固定資産税を納めることは、あなたが暮らす地域コミュニティを豊かにするための大切な会費のような性質を持つ、と考えるとわかりやすいでしょう。
固定資産税が課される対象は、その名の通り「固定資産」です。
具体的には、以下の3つに分類されます。
一般的な住宅を所有する場合は、「土地」と「家屋」の2つが課税対象になると考えておきましょう。
納税通知書には、「都市計画税」という税金が固定資産税とあわせて記載されている場合があります。
都市計画税は、主に市街化区域内の土地や家屋に対して課されます。公園や下水道、道路の整備といった都市計画事業や土地区画整理事業に使われる目的税です。
すべての市町村で課税されるわけではなく、市街化区域以外の土地・家屋には課税されません。課税対象地域に該当する場合は、固定資産税と併せて納付することになります。
税金の概要を理解したうえで、次は、実際の納税方法について見ていきましょう。「誰が、いつまでに、どのように支払うか」は、家計管理をするうえでも重要です。
固定資産税を納める義務があるのは、毎年1月1日に、土地や家屋を所有している人です。この基準日を賦課期日といいます。
ここで注意したいのが、1年の途中に不動産を売却した場合でも、その年度分の納税義務は1月1日時点の所有者(売主)にある点です。
たとえば、あなたが2025年の3月に家を売却したとしても、2025年度の固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の所有者である「あなた」になります。
ただし、不動産取引の実務では、売主と買主との間で、所有期間に応じて税額を日割り計算し、売買代金とは別に清算(按分)するのが一般的です。
固定資産税を納めるためには、市町村から送られてくる「納税通知書」と「納付書」が必要です。これらの書類は、毎年4月から6月頃にかけて送られてきます。
発送時期は自治体によって少し異なりますが、ゴールデンウィークを過ぎたあたりから郵便受けを気にかけておくと良いでしょう。初めて納税通知書を受け取るときは、税額に驚く方もいるかもしれませんが、スケジュール通りに納付できるよう準備を進めましょう。
固定資産税の支払いは、通常、1年分を4期に分けて支払います。納付期限は自治体によって異なりますが、たとえば令和7年度分の東京23区内の固定資産税・都市計画税の納付期限は、次のようになっています。
第1期の納付期限までに1年分をまとめて支払う「全期前納」も可能です。ただし、一括納付による割引があるわけではないので、家計の状況に合わせて、分割か一括かを選ぶと良いでしょう。
この章からはいよいよ、この記事の核心である「税額の計算」に入ります。一見、複雑に感じるかもしれませんが、3つのステップでわかりやすく解説していきます。
| ステップ | やること | ポイント・説明 |
|---|---|---|
| Step 1 | 固定資産税評価額を調べる | 固定資産税評価額は、実際の売買価格とは異なります。市町村が決定する公的な価格(評価額)であり、納税通知書の「課税明細書」で確認できます。 |
| Step 2 | 課税標準額を出す | 評価額から軽減措置(特例)を適用した後の金額です。税額を計算する基になります。 |
| Step 3 | 税率(標準1.4%)を掛けて税額を算出 | 「課税標準額 × 標準税率1.4% 」で 固定資産税額を計算します。これが、最終的な固定資産税額となります。 |
固定資産税の税額を計算するうえで出発点ととなるのが「固定資産税評価額」の確認です。
自宅の評価額は、毎年送られてくる納税通知書に同封されている「課税明細書」で確認できます。
次に、Step1で確認した「固定資産税評価額」から、さまざまな軽減措置(税の割引制度)を適用し、「課税標準額」を算出します。課税標準額は、税率をかけるベースとなる金額です。
課税標準額は、軽減措置の内容によって大きく変わる可能性があります。
住宅用地の特例や新築住宅の減額措置など軽減措置については、この後の章で詳しくご説明します。
最後に、Step2で算出した課税標準額に税率を掛けて、固定資産税の税額を算出します。
多くの市町村では、この「標準税率(1.4%)」を採用していますが、条例により異なる税率を定めている自治体もあります(1.5%など)。
納税通知書や自治体のホームページで実際に適用される税率を確認しておくとよいでしょう。
これまでのステップを、具体的なモデルケースで見てみましょう。
まず、土地の税額を計算します。
この土地は、住宅用地として使われているため、「住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が評価額の1/6(200㎡以下の部分)に軽減されます。
この課税標準額に税率を掛けて、土地の税額を求めます。
次に、建物にかかる税額を計算します。
まず、軽減措置を適用する前の税額を計算します。
この家は新築住宅なので、「新築住宅の減額措置」が適用され、税額が3年間、1/2に減額されます(居住部分で120㎡/戸を限度として)。
最後に、土地と建物の税額を合計して、このモデルケースでの年間の固定資産税額を算出します。
シミュレーションの結果、このモデルケースで最初の3年間に支払う固定資産税の年額は約15万4千円が目安となります。
制度を正しく理解して活用すれば、数万円から数十万円単位で税負担を軽減できる場合もあります。ここでは、代表的な軽減措置を一覧で整理しながら解説します。
| 軽減措置の種類 | 対象 | 減額の内容 | 適用期間 | 手続き要否 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅用地の特例 | 住宅が建っている土地 |
|
建物が存続する限り | 原則不要 |
| 新築住宅の減額措置 | 一定要件を満たす新築の家屋 | 固定資産税額が1/2に減額(上限120㎡/戸) | 原則3年度分(マンション等は5年度分) | 原則不要 |
| 認定長期優良住宅の特例 | 長期優良住宅の認定を受けた新築の家屋 | 固定資産税額が1/2に減額(上限120㎡/戸) | 原則5年度分(マンション等は7年度分) | 要申告(認定書の提出など) |
住宅が建っている土地については、その広さに応じて課税標準額が大幅に軽減される「住宅用地の特例」が適用されます。これは新築・中古にかかわらず適用される、最も基本的な軽減措置です。
たとえば、100㎡の土地に住宅が建っている場合、土地全体が小規模住宅用地に該当し、評価額の1/6まで税額が軽減されます。
一定の要件を満たす新築住宅には、建物の固定資産税が半額になる特例があります。
この制度により、新築後の出費がかさむ時期の負担を大きく軽減できます。
ただし、軽減期間終了後の4年目からは、税額が元の水準に戻る(上がる)点には注意が必要です。
また、数年間は税金の負担が軽くなりますが、建築費そのものを抑える工夫も重要です。
家づくりの初期に複数のハウスメーカーや工務店から提案を比較できる注文住宅の一括見積もりサービスを利用しておくと、総費用を抑えやすくなります。
購入した新築住宅が、耐震性や省エネ性などに優れた「認定長期優良住宅」として認定されている場合、減額期間が延長されます。
納税通知書(課税明細書)のチェックポイント
| チェック番号 | 確認する項目(明細書上の名称例) | 内容とチェックポイント |
|---|---|---|
| ① | 「所有者」の氏名・住所 | まずは基本情報である名前や住所に誤りがないかを確認しましょう。 |
| ② | 土地・家屋の「価格」または「評価額」 | 固定資産税の算定基礎となる金額で、市町村が評価した公的価格です。購入価格とは異なるため注意が必要です。 |
| ③ | 「課税標準額」 | 評価額から軽減措置が適用された後の金額です。特に住宅用地では、評価額よりも大幅に下がっているかを確認しましょう。 |
| ④ | 「課税標準の特例」や「減額」に関する欄 | 「住宅用地特例」や「新築住宅の減額措置」などが正しく適用されているかを確認します。不明な点や適用漏れが疑われる場合は、市町村の税務担当に問い合わせましょう。 |
固定資産税の納税通知書には、「納付書」のほかに「課税明細書」という重要な書類が同封されています。
この課税明細書には、あなたが所有する土地や建物ごとの情報が細かく記載されており、税額がどう算出されているかがわかります。
課税明細書に、「価格」または「評価額」と書かれた欄があります。
これが、市町村が算定した「固定資産税評価額」です。
固定資産税や都市計画時の税額を計算する際のスタート地点となる重要な数字です。
次に確認したいのが、「課税標準額」の欄です。
「課税標準額」とは、評価額から軽減措置を適用した後の金額で、実際に税率がかけられる基準となる金額です。
この記事の前半で解説した、住宅用地に対する軽減措置が正しく適用されていれば、土地の課税標準額は、「価格」または「評価額」の欄の数字よりも大幅に小さくなっているはずです。
たとえば、土地の評価額が1,200万円に対して、課税標準額はその1/6である200万円になっていれば、住宅用地の特例が適用されていると判断できます。
なお、新築住宅(建物)の減額措置は、税額そのものを減額する特例のため、この欄には反映されず、税額欄で確認する必要があります。
軽減措置が適用されている期間の税額が1/2になっているかも確認しましょう。
もし、課税明細書の内容を見て「評価額が高すぎるのでは?」「軽減措置が適用されていないのでは?」といった疑問を感じた場合は、納税通知書に記載されている市町村の担当課(資産税課など)に問い合わせてみましょう。
手元に納税通知書や課税明細書を用意して相談すれば、丁寧に説明してもらえるはずです。
納税額が確定したら、あとは実際に納付するだけです。
最近では、私たちのライフスタイルに合わせて、さまざまな支払い方法が選べるようになっています。
それぞれのメリット・デメリットを比較して、あなたに合った方法を選びましょう。
| 支払い方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 納付書払い(窓口・コンビニ) |
|
|
|
| 口座振替 |
|
|
|
| クレジットカード |
|
|
|
| スマホ決済(PayPay・LINE Payなど) |
|
|
|
納税通知書に同封された納付書を使って、金融機関や郵便局、市役所などの窓口、またはコンビニエンスストアで現金で支払う、最もオーソドックスな方法です。
支払いを証明する領収書がその場で受け取れる安心感があります。
口座振替は、一度手続きをしておけば毎年納期ごとに指定した口座から自動で引き落とされるため、払い忘れの心配がなく、もっとも手間がかからない方法といえるでしょう。
忙しい方や支払い管理をシンプルにしたい方におすすめです。
自治体によっては、専用の「公金支払いサイト」を通じてクレジットカードで納付できます。
カードのポイントが貯まるのが最大のメリットですが、一方で、決済手数料がかかる場合が多い点には注意が必要です。
自宅にいながら、スマートフォンの決済アプリを使って24時間いつでも支払える、近年急速に普及している方法です。PayPay・LINE Pay・楽天ペイなどに対応する自治体が増えています。
納付書に印刷されたバーコードやQRコードを読み取るだけで簡単に手続きが完了し、スマートフォンに慣れている方であれば時間や手間をかけずに支払いが可能です。原則として、支払い手数料はかかりません。
この章では、多くの方が疑問に思いやすい細かいポイントについて、Q&A形式でお答えします。
A. はい、計算の基本的な考え方は、新築・中古、一戸建て・マンションにかかわらず同じです。
ただし、新築住宅に適用される「新築住宅の減額措置」は中古住宅には、原則として適用されません。
また、マンションの場合は土地が共有であるため、通常、敷地全体の評価額を専有面積の割合で按分した金額が土地の課税対象になります。この点が戸建てとの違いです。
A.共有名義の不動産については、納税通知書は、通常、代表者1名に送付されます。ただし、共有者全員が連帯して納税義務を負う仕組みになっており、共有者全員に支払い義務があります。誰が支払うかは、夫婦間で話し合って決めると良いでしょう。
A. 納付期限を過ぎてしまうと、延滞した日数に応じた延滞金が加算されてしまいます。
延滞金の利率は、年度ごとに変わる可能性があり、年7%を超える延滞金が発生する場合もあるため注意が必要です。
また、長期間滞納した場合には、
といった強制的な徴収措置に進むこともあります。
万が一支払いが難しい場合は、早めに市町村の窓口に相談することが重要です。
A. 都市インフラを整備するための目的税で、道路や公園、下水道などの都市基盤を整備する費用に充てられます。
市街化区域内に不動産を所有する人を対象として課税され、固定資産税とあわせて納付します。
ここまで、固定資産税について、基礎から支払い方法、注意点まで幅広く解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
最後に、本記事の要点を振り返っておきましょう。
固定資産税は、マイホームを持ち続ける限り、毎年関わることになる税金です。
しかし、その制度を正しく理解し、評価額や活用できる軽減措置を把握しておけば、なんとなく不安な存在から、家計に組み込んで対応できるコストへと変わるはずです。
もし、「うちの場合どうなるの?」という具体的な不安や疑問がある場合は、一人で抱え込む必要はありません。市町村の担当窓口のほか、税理士や不動産会社などの専門家へ相談することも有効な選択肢の一つです。
