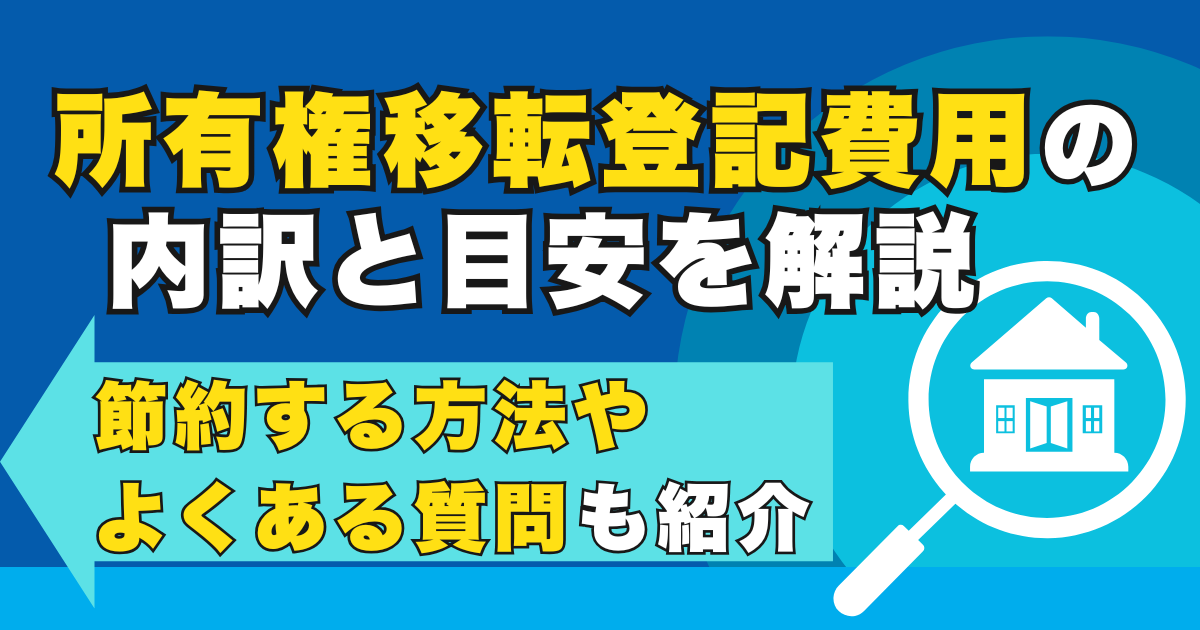
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...
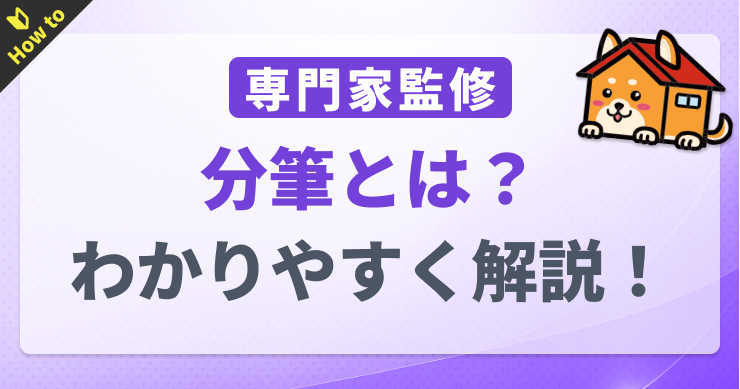
「子どもたちが相続で揉めないよう、今のうちに土地を分けておきたい…」
「でも、手続きは複雑そうだし、費用もどれくらいかかるのか心配…」
ご家族を大切に想うからこそ、そのように悩まれて、このページに辿り着かれたのではないでしょうか。
ご安心ください。「分筆(ぶんぴつ)」は、そうしたお悩みを解決するための、とても有効な手続きです。費用や注意点はありますが、一つひとつ順を追って理解すれば、決して難しいものではありません。
この記事では、相続案件を専門とする土地家屋調査士の私が、分筆の基本知識から、円満相続を実現するための注意点まで、わかりやすくご説明します。
この記事でわかること
まず、「分筆」という言葉ですが、難しく考える必要はありません。
分筆は、例えるなら「一つの大きなホールケーキを、人数分に切り分ける」ようなものです。
法務局にある公的な帳簿(登記簿)には、土地は「筆(ふで)」という単位で登録されています。一筆、二筆…と数えられ、これが土地の戸籍のようなものです。
分筆とは、この登記簿に記録されている一筆の土地を、二筆や三筆に分割し、それぞれが独立した土地として扱えるように法務局に申請する手続きのことを指します。単に地面に線を引くのではなく、この法的な手続きこそが分筆の本質です。
では、なぜ相続の準備で分筆が考えられるのでしょうか。
それは、一つの土地を複数の相続人で相続した場合、「共有名義」という状態になるからです。
共有名義の土地は、将来その土地を売却したり、家を建て替えたりする際に、共有者全員の同意が必要になります。今は仲の良いご家族でも、将来、それぞれの配偶者やお子さんの代になった時、意見がまとまらずに身動きが取れなくなる…というケースは、残念ながら少なくありません。
あらかじめ土地を分筆して、それぞれのお子さん名義の独立した土地にしておくことで、このような将来のトラブルの芽を摘み取ることができるのです。
ちなみに、分筆と似た言葉に「合筆(ごうひつ/がっぴつ)」や「分割」があります。
この記事では、「分筆」について詳しく解説していきます。
相続のために分筆を検討する上で、良い点と注意すべき点の両方をしっかりと理解しておくことが大切です。
最大のメリットは、やはりこれでしょう。土地を物理的に分けることで、ご長男にはAの土地、ご次男にはBの土地、というように、それぞれに独立した不動産として相続させることができます(これを現物分割と言います)。「共有」という将来の火種を残さず、公平に資産を分けられるため、円満相続の大きな助けとなります。
広い土地を一つだけ持っていても、その一部だけを売ることはできません。もし売却するなら、土地全体を売る必要があります。
しかし、分筆しておけば、「自宅の敷地は残し、隣の庭だった部分だけを売却して老後の資金にする」といった柔軟な資産活用が可能になります。また、土地が大きすぎる場合、そのエリアに合った適正な大きさに分筆することで、買い手が付きやすくなります。
万が一、相続税が現金で支払えない場合、土地そのものを税金として国に納める「物納」という制度があります。この物納の際に、必要な納税額に見合うように土地を分筆して納める、ということが可能になります。
ただし、残念ながら、分筆は無料では行えません。後ほど詳しく解説しますが、専門家である土地家屋調査士に支払う測量費や登記の報酬などで、数十万円単位の費用がかかります。これは、分筆を検討する上で最も大きなハードルと言えるかもしれません。
これは非常に重要な注意点です。たとえば、土地を単純に半分に分けた結果、片方の土地が道路に面さない「旗竿地(はたざおち)」になってしまったり、使いにくい形の「不整形地」が生まれたりすることがあります。
このような土地は、一般的に評価額が下がり、いざ売却しようとしても買い手が見つかりにくくなるなど、かえって資産価値を損なう結果になりかねません。
また、自治体が「最低敷地面積」を定めているエリアでは、その面積を下回る分筆をすることはできません。
「分筆は手続きが複雑で大変そう…」多くの方がそう思われるようです。
しかし、ご安心ください。手続きの大部分は、専門家である土地家屋調査士があなたに代わって行います。そのため、あなたは全体の流れを把握しておけば十分です。期間は3ヶ月~半年ほどが目安となります。
まずは、分筆手続きの専門家である「土地家屋調査士」に相談することから始まります。あなたの想いやご家族構成を伝え、どのような分け方が最適か、プロの視点からアドバイスをもらいましょう。
ここが、分筆手続きで最も時間がかかり、そして最も重要なプロセスです。
土地を分ける大前提として、「そもそも、あなたの土地の範囲はどこからどこまでか」を、全ての隣地の所有者と立会いのもとで確認し、お互いに合意する必要があります。これを境界確定測量と呼びます。
ただし、立会いの際に隣地の方が境界地点に納得せず、署名・捺印を得られないケースもあります。特に隣接する敷地が多い土地については、事前に過去の履歴を遡って、合意を取りやすいよう書類を用意しておくことも重要です。
土地の境界が確定したら、土地家屋調査士が測量結果に基づいて登記申請書を作成し、法務局へ「土地分筆登記」を申請します。この申請が受理されれば、登記簿上、一つの土地が複数の土地に分かれます。
分筆登記が完了した後、例えば「Aの土地は長男へ、Bの土地は次男へ」といったように名義を変更(贈与など)する場合は、別途、司法書士に依頼して権利に関する登記を行う必要があります。権利に関する登記には、「権利証(登記識別情報)」「本人確認書」「印鑑証明書」など権利関係の分かる書類が必要になります。事前に問い合わせのうえ、用意しましょう。
さて、気になる費用のお話です。
分筆にかかる費用は、土地の状況によって大きく変動するため、一概に「いくらです」とは言えませんが、一般的な住宅地であれば、総額で40万円~80万円程度が一つの目安になるでしょう。
費用の大部分は、土地家屋調査士への報酬です。
これには、過去の資料調査、現地での測量作業、隣地所有者との調整、各種書類の作成、登記申請の代行など、専門的な作業のすべてが含まれます。
分筆登記を法務局に申請する際には、「登録免許税」を納める必要があります。
登録免許税は、分筆後の土地1筆につき1,000円と定められています。たとえば、1つの土地を3つに分ける場合は、3,000円です。費用全体から見れば、ごくわずかですね。
費用の目安に幅があるのは、以下のようなケースでは作業がより複雑になり、費用が高くなる傾向があるためです。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
「土地を分ける」といっても、いつでも自由に好きなように線を引けるわけではありません。法律上の制約によって、「分筆はできても、分けた後に価値のない土地が生まれてしまう」という、最も避けたい事態が起こり得ます。
これは、分筆で最も注意すべき法律上のルールです。
建築基準法では、建物を建てるための土地は、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務が定められています。
このルールを知らずに土地を分けた結果、道路に面さない土地が生まれてしまうと、その土地には将来、家を建て替えることができなくなります。いわゆる「再建築不可物件」となるため、資産価値は著しく下がってしまうのです。
土地を細かく分けすぎた結果、一つひとつの土地が小さくなりすぎて、家を建てるには不十分な広さになってしまうケースです。これでは、せっかく分けても誰も活用できず、意味がありません。
また成形地でなく多角形のような土地は建物の建築に不向きで、比較的割安となってしまいます。
市町村が独自に「開発指導要綱」などの条例を定め、一定規模以上の土地開発や、最低敷地面積に制限を設けている場合があります。これも、分筆計画の際に必ず確認が必要です。
また、市街化調整区域にある土地も開発行為として制限されている場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
専門家からの一言アドバイス
相続のための分筆で最も大切なのは、登記上の線引きだけでなく、「家族の未来の線引き」を想像することです。機械的に分けるのではなく、愛情をもって分けることが、本当の円満相続につながります。
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
最後に、もう一度大切なポイントを振り返っておきましょう。
この記事で、分筆の全体像はご理解いただけたかと思います。
しかし、あなたの土地が持つ固有の状況や、ご家族への想いを反映した最適な分け方は、やはり専門家と顔を合わせてじっくりと相談するのが一番です。
多くの土地家屋調査士事務所では、初回は無料で相談に応じています。
まずは「我が家の場合はどうだろう?」と、お近くの専門家に話を聞いてもらうことから始めてみませんか。それが、ご家族の笑顔を守る、何よりの相続対策になります。
[免責事項]
本記事は2025年7月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的としています。個別の案件に関する法的な判断や費用の確定には、専門家へのご相談が必要です。
