
-
確定測量とは?費用や流れ、必要性についてわかりやすく解説


賃貸経営において頻繁に耳にする言葉の一つが「マスターリース」です。
不動産投資や土地活用を検討している方にとって、空室リスクの軽減は非常に重要なテーマです。マスターリースは、この空室リスクを抑え、安定した賃貸経営を実現するための手法として注目されています。
本記事では、マスターリースの基本的な仕組みから、サブリースとの違い、賃料支払いの仕組み、メリット・デメリットまでを専門家監修記事の形式でわかりやすく解説します。
マスターリースとは、オーナー(物件所有者)が不動産会社(サブリース会社)に賃貸物件を一括で貸し出す契約形態のことです。
オーナーはサブリース会社と賃貸借契約を締結し、その後サブリース会社が入居者と転貸借契約を結びます。オーナーにとっては、入居者ごとに契約を結ぶ手間が省けるうえ、賃料の受け取り先が一社に集約される点が特徴です。
マスターリースは「一括借り上げ」とも呼ばれ、特にマンションやアパートの複数戸を所有するオーナーに利用されています。入居者の募集・契約・管理業務などを不動産会社に任せられるため、初めての賃貸経営でも比較的安心して始められる仕組みといえます。

マスターリースと混同されがちな言葉に「サブリース」があります。両者は似ていますが、契約当事者が異なります。
つまり、オーナーと不動産会社の契約が「マスターリース契約」、不動産会社と入居者の契約が「サブリース契約」です。
実務上はこの二つを厳密に区別せず、まとめて「サブリース」と呼ぶことが多いですが、法的には別の契約関係として整理されています。
また、賃貸住宅管理業法上では、マスターリース契約を「特定賃貸借契約」、サブリース会社を「特定転貸事業者」と定義し、誇大広告や不当勧誘の禁止、契約前の重要事項説明などを義務づけています。これにより、オーナー保護の仕組みが強化されています。
| マスターリース | 物件を所有しているオーナーと不動産会社(サブリース会社)との賃貸借契約 |
|---|---|
| サブリース | オーナーから一括借り上げした不動産会社(サブリース会社)と入居者との賃貸借契約 |

マスターリース契約における賃料の支払い方式は、大きく分けて次の2種類があります。
空室保証型とは、物件の空き状況にかかわらず、一定の家賃収入が得られる方式です。基本的には家賃の80%から90%ほどが相場となっており、立地条件や築年数により料率は異なりますが、安定した収入を確保できる点が特徴です。空室保証型のメリットとデメリットについて、以下でさらに詳しく紹介します。
空室保証型は、空室があっても家賃収入は固定額で得られるため、稼働率が低い場合でも一定以上の収入が確保できます。そのため、賃貸経営でとくに大きなネックとなる空室リスクを軽減することが可能です。
また、不動産会社が入居者の募集や家賃の未払いが発生した際の対応などすべて任せられるため、面倒な手続きがなく、手間がかかりません。建物の管理や修繕計画などを立ててくれるのも大きなメリットといえます。
満室稼働でも賃料は一定で、収益の上限が決まってしまいます。立地が悪く空室が目立つような物件であれば空室保証型のメリットを享受できますが、人気がある物件では十分な利益を享受できない可能性があります。
さらに、定期的に賃料の見直し(減額請求)が行われることがあります。周辺相場よりも今の家賃が割高となった場合、借地借家法に基づき、サブリース会社は賃料減額請求を行う権利を有しています。
入居状況に応じてオーナーへの支払い額が変動する方式です。空室が多ければ収入が減少しますが、満室時には高い収益を得ることが可能です。メリットやデメリットについて、さらに詳しくみていきましょう。
稼働率が高い賃貸不動産であれば、高収益が得られます。空室保証型の場合、収益は安定しますが一定金額のため、物件の潜在価値に見合った利益を得ることは難しくなるのが特徴です。
しかし、パススルー型であれば入居者の数に合わせて家賃が支払われるため、 稼働率が高い物件では高収益を狙えます。また、入居者の情報や現在の賃貸条件などが開示されるため、自分が所有している物件の状況を正確に把握することが可能です。
パススルー型のデメリットとしては、入居者が少ない場合や賃料の滞納が生じた場合、家賃収入が得られない点です。空室保証型の場合は入居者が少なくても一定の家賃収入が得られますが、パススルー型は実際に入居している人数により収益が変動するため、多く入居者がいれば収入が多くなる一方、少なければその分利益は下がるのが特徴です。
空室保証型は「安定志向」、パススルー型は「収益最大化志向」と整理できます。どちらを選ぶかは、物件の立地・入居需要・オーナーの経営方針によって判断することが重要です。

マスターリースとは、物件所有者と不動産会社が一括借り上げをする契約です。マスターリースすることにより、所有者にはどのようなメリットがあるのかを詳しくみていきましょう。
マスターリース契約の最大のメリットは、空室リスクを大幅に抑えられる点です。
不動産会社が物件全体を借り上げるため、入居者がいない場合でもオーナーには一定の賃料が支払われます。特に、長期的な安定収益を求めるオーナーにとって有効な仕組みです。
賃貸経営は、さまざまな複雑かつ難しい管理業務があります。初めての経営の場合、何の経験もない状態のため、わからないことだらけで戸惑う場面や、スムーズに手続きが進められないといったトラブルが生じます。
マスターリース契約では、入居者募集、賃料回収、クレーム対応、修繕対応などの煩雑な業務を不動産会社に一任できるため、オーナーは労力をかけずに賃貸経営を継続できます。マスターリースは、このような面倒な管理業務もすべて任せられるため、豊富なノウハウがなくても安心して賃貸経営をスタートさせられます。
近年では、以前より賃貸経営が身近なものとなってきました。
そのため、マスターリースを提供する不動産会社が多様な付加サービスを展開しています。
経営アドバイス、リフォーム提案、税務・相続相談、投資セミナーの開催など、長期的な資産形成をサポートする体制が整っているケースも増えています。
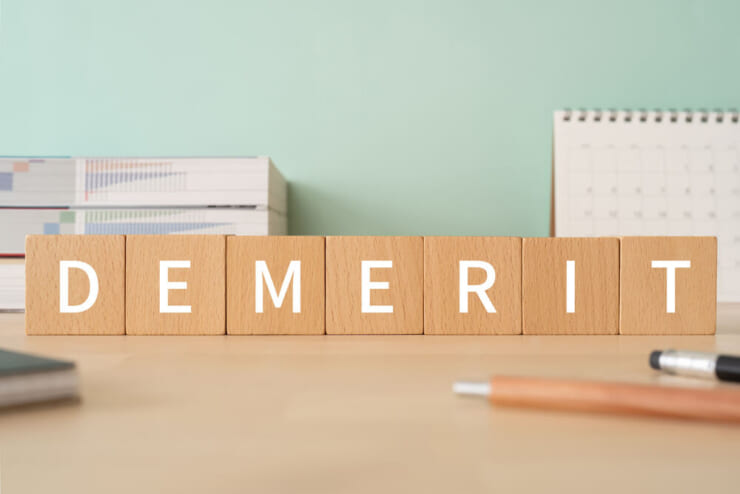
空室リスクを減らし安定した収入が得られるのがマスターリースですが、メリットばかりに目を向けていると思わぬ落とし穴に落ちてしまうこともあります。うまく賃貸経営を進めていくためにも、デメリットに対する深い理解は必須といえます。
メリットよりもデメリットの方が大きくなってしまっては、せっかくのマスターリースも活かすことはできません。失敗しない賃貸経営のために、ここでしっかりとデメリットについてみていきましょう。
マスターリースの場合は物件所有者が貸主になり、不動産会社が借主となります。借地借家法には、借主を保護するための条文があります。この結果、マスターリース契約によって借主である不動産会社側が保護される立場となります。法律上はプロが保護され、経験が浅くわからないことが多い賃貸物件所有者が弱い立場となる、すなわち、不動産会社に主導権を握られてしまうリスクが高いのが最大のデメリットです。
マスターリース契約は賃貸借契約であり、借地借家法により借主(サブリース会社)には賃料減額請求権が認められています。
そのため、「家賃保証」と記載されていても、景気変動や空室増加を理由に賃料を引き下げられる可能性があります。
過去にはこの点をめぐってトラブルが発生し、裁判に発展した事例もあります。
マスターリース契約付きの物件は、契約条件が制限されるため、一般の投資家にとっては敬遠される傾向があります。
賃料見直しリスクや運営の自由度の低さから、物件価値が下がる可能性もある点には注意が必要です。
マスターリース契約は、借主である不動産会社に有利な契約構造となっているため、オーナーからの一方的な解除は困難です。
建物の老朽化や賃料の下落などを理由に、サブリース会社側から契約を解除されるケースはありますが、オーナー側からの解約には「正当事由」が必要です。
このため、契約締結時には解除条件や期間、更新時の取り扱いを十分に確認しておく必要があります。
マスターリース契約は、空室リスクの軽減と安定した賃貸経営を実現する有効な手段です。
一方で、賃料減額や契約解除の制約といったデメリットも存在するため、契約内容を十分に理解し、慎重に判断することが求められます。
安定した賃貸経営を目指すには、「家賃保証」などの表面的な言葉に惑わされず、法的リスク・契約構造・収益性のバランスを見極めることが重要です。
マスターリースの仕組みを正しく理解し、自身の経営方針に合った活用を行うことで、長期的に安定した資産形成を実現できるでしょう。
