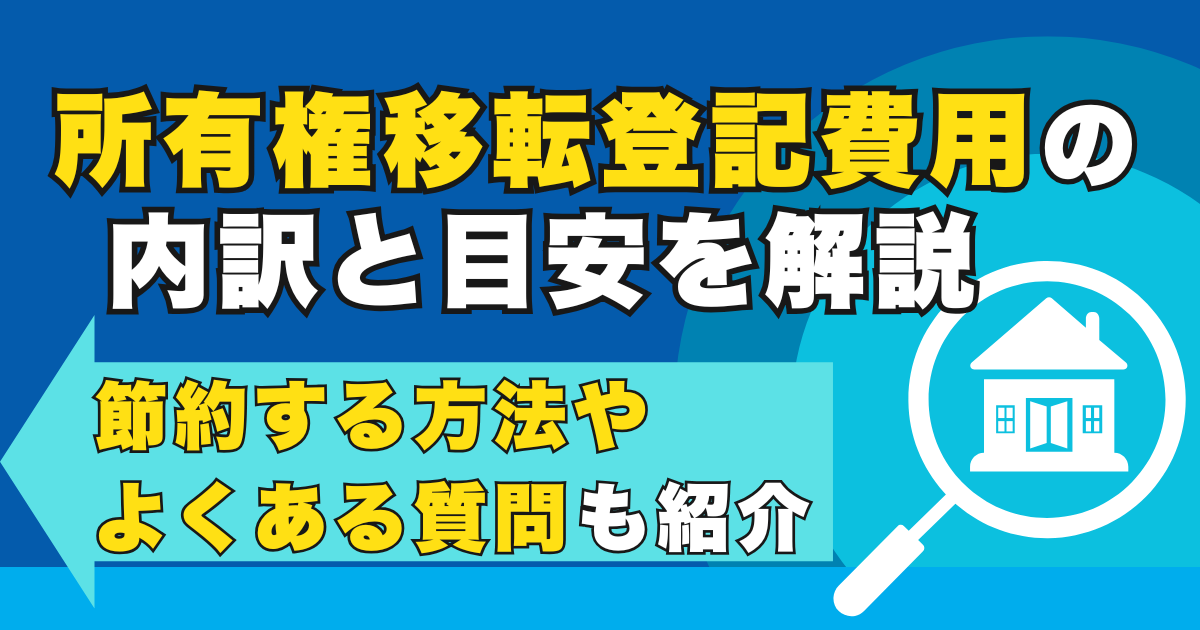
-
所有権移転登記費用の内訳と目安を解説|節約する方法やよくある...
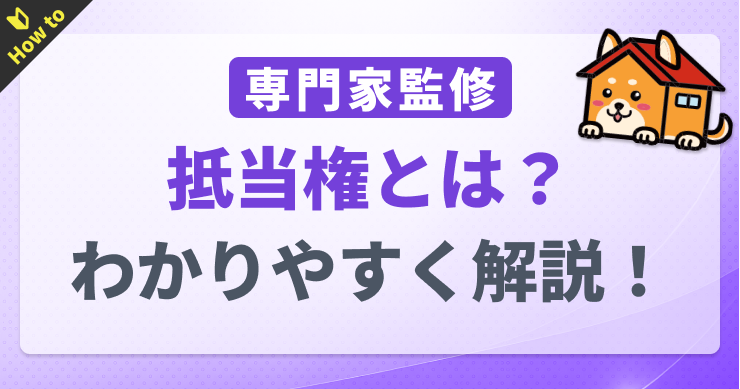
抵当権(ていとうけん)とは、金融機関が債務者の土地や建物を担保に貸付を行い、返済できない場合にその不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。
抵当権を設定することにより、お金を貸す側は、ローンの返済が滞った・できなくなった際、抵当権が設定された不動産を売却して返済に充てる権利を得られます。
(参照:g-gov 法令検索:民法 第三百六十七条及び第三百六十八条 第十章抵当権)
この記事では、抵当権の基本的な仕組みから、登記の手続きや費用、根抵当権・担保権との違いまで、初心者でもわかりやすいように解説します。
抵当権は、債務者の返済が滞る、もしくは困難に陥ったときに、担保とした不動産を売却することで債権者が優先的に弁済を受けられる権利です。抵当権の登記を行うことで第三者に「自分が優先的に弁済を受ける権利がある」と主張することができます。
たとえば、住宅ローンを組むとき、債権者である金融機関は債務者の不動産に抵当権を設定し、融資を行います。
次章では、この抵当権の仕組みを「わかりやすく」説明します。
抵当権は、土地や建物といった不動産に設定されます。設定するのは「お金を貸す人(債権者)」であり、設定される側の「借りる人(債務者)」は抵当権設定者と呼ばれます。
債務者がローンを滞納すると抵当権が実行されます。債権者は裁判所を通じてその不動産を差し押さえ、競売にかけます。 この一連の手続きを「抵当権の行使」と呼び、最終的にその売却代金から債権者は債権を回収することができます。
【監修者コメント】
住宅ローンの滞納が始まってから、実際に抵当権が実行され、不動産が競売にかけられるまでには、一般的に8ヶ月~1年程度かかります。
抵当権が法的に設定されるのは、住宅ローンの融資が実行され、あなたが物件の代金を支払う「決済日」の当日です。この日は不動産取引において最も重要な一日と言えます。
あなた、売主、不動産会社の担当者、そして司法書士が金融機関に集まり、お金の流れと権利の移転を同日中にすべて完了させます。なぜなら、所有権があなたに移った瞬間に、間髪入れず抵当権を設定しなければ、金融機関は無担保でお金を貸した状態になってしまうからです。
イメージがつきづらいと思うので、抵当権が設定される流れを、時系列で見てみましょう。
抵当権と根抵当権は、いずれも不動産に設定する担保の権利ですが、仕組みに大きな違いがあります。
抵当権は1回限りの借入に対応するのに対し、根抵当権は一定の上限まで何度でも借入ができる柔軟な形式です。
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 概要 | 特定のローンを担保するために設定 | 継続的な取引を担保するために設定 |
| 借入額 | 最初から金額が確定している | 極度額(根抵当権で保証される借入の最大額)の範囲内で自由に借入・返済が可能 |
| 利用ケース | 住宅ローンなどの単発借入 | 企業融資や運転資金の信用供与など |
| 追加借入 | 不可(別途設定が必要) | 可能(極度額内であれば自由) |
| 消滅条件 | 借金を完済したときに消滅 | 継続的な取引が終了し、清算後に消滅 |
また、抵当権と他の担保制度との違いも整理しておきましょう。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 担保権 | 借金が返せないときに、財産を処分して回収する権利の総称 |
| 質権 | 不動産以外のモノ(動産や権利)を預けて借金の担保にする制度 |
抵当権は担保権の一種であり、動産ではなく不動産に対して設定する点が特徴です。これにより、不動産購入に必要な多額の資金を低金利で借りられます。
抵当権を設定する最大のメリットは、低金利で高額な資金を借りられることです。金融機関は担保が取れれば債権回収不能となるリスクが低いので、債務者にとって有利な条件で融資を受けることができます。
| 項目 | 抵当権設定(有担保ローン) | 無担保ローン(抵当権なし) |
|---|---|---|
| 担保 | 不動産あり | なし |
| 金利 | 低め | 高め |
| 借入限度額 | 高額まで可能 | 比較的少額 |
| 審査 | 通りやすい傾向 | 厳しくなる傾向 |
特に住宅ローンでは、抵当権の設定が前提となるため、選択肢の幅が広がります。無担保で同等の金額を借りようとすると、返済条件が厳しいケースが多いでしょう。
参考:抵当権を設定した場合の借入可能額と年収の目安
| 年収 | 借入可能額の目安 (年収倍率 5~7倍) |
借入可能額の目安 (返済負担率 25%) |
毎月の返済額の目安 (返済負担率 25%) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 1,500万円 ~ 2,100万円 | 約2,120万円 | 約6.3万円 |
| 400万円 | 2,000万円 ~ 2,800万円 | 約2,820万円 | 約8.3万円 |
| 500万円 | 2,500万円 ~ 3,500万円 | 約3,530万円 | 約10.4万円 |
| 600万円 | 3,000万円 ~ 4,200万円 | 約4,240万円 | 約12.5万円 |
| 700万円 | 3,500万円 ~ 4,900万円 | 約4,940万円 | 約14.6万円 |
| 800万円 | 4,000万円 ~ 5,600万円 | 約5,650万円 | 約16.7万円 |
| 1,000万円 | 5,000万円 ~ 7,000万円 | 約7,060万円 | 約20.8万円 |
抵当権を設定しても、きちんと返済していれば問題ありません。 一方で、返済が滞った場合には大切な不動産を失う可能性があります。本章では、抵当権設定で生じる債務者側のリスクについて紹介します。
住宅ローンの融資を受けるうえで必要不可欠な抵当権について、しっかりと理解しておきましょう。
抵当権の設定には、登記費用や司法書士への報酬などの初期コストがかかります。
特に住宅ローンでは銀行指定の司法書士に依頼することが多く、自分で行うことは現実的には難しいのが実情です。
実務上は、ほぼすべてのケースで司法書士に依頼して行います。自分でやってはいけないという法律はありませんが、専門知識がないとミスをするリスクが高く融資実行に影響するため、金融機関に断られることがほとんどです。
| 費用項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 登録免許税 (国に納める税金) |
債権額(借入額)× 0.4% ※ただし、一定の要件を満たすマイホームの場合は、軽減措置により税率が0.1%に軽減されます。 |
| 司法書士報酬 (司法書士への手数料) |
3万円 ~ 10万円程度 ※報酬は司法書士事務所や地域、手続きの複雑さによって変動します。住宅ローンの場合は、所有権移転登記など他の手続きとセットで依頼することがほとんどです。 |
| その他実費 | 数千円 ~ 1万円程度 登記情報の事前調査に必要な「登記事項証明書」の取得費用(1通600円程度)、登記完了後の謄本取得費用、郵送費、交通費などが含まれます。 |
返済が滞ると設定された抵当権が行使され、裁判所が物件を差し押さえて競売にかけられる可能性があります。
つまり、所有権を失ってしまうリスクが現実化するのです。
ローンを組むということはこのようなリスクを背負うことでもあるため、無理のない返済計画を立てることが重要です。
【監修者コメント】
マイホームは多くの人の夢であり、家族の憩いの場となります。でも、その後の生活が苦しくなっては本末転倒です。差し押さえという最悪の事態を避けるため、ローンを組む前に知っておきたい計画のコツをお伝えします。
まずはこれを守ろう!安心な計画の立て方
これは危険!避けるべきNGケース
一番やってはいけないのが、銀行に言われた「借入上限額」でローンを組むこと。自分たちの家計に合った額で計画することが何より大切です。
抵当権がついたままの物件は、売却が難しくなることがあります。なぜなら、買主が抵当権が付いたままの物件の引き渡しを受けた場合、前所有者のローン滞納などで抵当権が実行され、不動産からの立ち退きを求められる可能性があるからです。
そのため、買主の購入判断に大きく影響します。
住宅ローンが残ったまま抵当権が付いた状態で物件が売り出されることは実際によくあります。居住中で売りに出されるケースが多く、このような場合には売却資金などで住宅ローンを完済し、抵当権を抹消して物件の引き渡しをする資金計画が組まれています。
「抵当権が残っている」というだけで売却を妨げるケースは少なく、多くの場合は立地や築年数、周辺環境や建物の状態などの要素が購入価格に影響を与えます。
競売では市場価格より2〜3割安く売却されるのが一般的です。通常の取引と比べて事前に得られる情報が少ないことで、買主のリスクが高いことが主な要因となります。
これらの要因から、競売物件はどうしても買い手側のリスクが大きくなり、それに見合った安値でしか売れなくなります。
その結果、本来の価値に比べて大きく損をする恐れがあるのです。
住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が消えるわけではなく、抵当権抹消登記が必要です。不要な権利は早めになくし、売却や相続時のトラブルを防ぎましょう。
完済証明書を受け取ったら、すみやかに抹消登記を行うことが望ましいです。放置すると数年後に思わぬ不利益を被る場合があります。
抵当権の登記手続きは、住宅ローンの融資が実行される「決済日」に、ミスなく完了させることが絶対条件です。そのため、金融機関が指定する司法書士に依頼するのが一般的であり、あなたが直接法務局へ行くことはほとんどありません。
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、あなたがやるべきことは意外とシンプルです。全体の流れと、それぞれのタイミングで誰が何をするのかを見ていきましょう。
手続きの役割分担
登記手続きは、主に以下の3者で連携して進められます。
【タイミング別】具体的な手続きの流れ
【監修者コメント】
「自分で登記すれば費用を節約できるのでは?」と考える方もいらっしゃいます。しかし、金融機関は「融資と同時に100%確実に抵当権を設定すること」を融資の絶対条件としています。万が一の書類不備も許されないため、実務上は専門家である司法書士への依頼が必須となっているのです。あなたは安心して司法書士に任せ、指示された書類を準備することに集中してください。
抵当権の登記費用は、司法書士への依頼費用を含めて10万円前後が目安となりますが、物件価格や借入額によって変動します。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 借入額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 約5万円〜6万円 |
| 登記事項証明書などの実費 | 数千円程度 |
抵当権の登記費用は8〜12万円程度を準備しておきましょう。司法書士事務所により登記費用は異なるので、事前に見積もりを取ると安心です。
最後に、抵当権についてお客様からよくいただく質問にお答えします。
A1. はい、全く問題ありません。
抵当権の大きな特徴は、所有者が占有(住み続けること)を続けながら担保にできる点です。住宅ローンをきちんと返済している限り、あなたの居住権が脅かされることは一切ありません。
A2. はい、可能です。ただし、条件があります。
売却は可能ですが、買主に所有権を引き渡すタイミングで、売却代金を使って住宅ローンを全額返済し、抵当権を抹消する必要があります。これを「抵当権抹消」と呼び、通常は不動産会社と司法書士がサポートしながら、売却と同時に手続きを行います。
A3. ローンの返済義務も一緒に相続することになります。
不動産というプラスの財産だけでなく、住宅ローンというマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。相続人は、引き続きローンを返済していくか、家を売却してローンを完済するか、あるいは相続自体を放棄するかを選択する必要があります。
抵当権は、住宅ローンを組む際に欠かせない重要な知識です。
返済が滞ると不動産を失う可能性がある一方、金利や借入条件が有利になるというメリットもあります。
デメリットとしては手続き費用や抹消登記の手間がありますが、きちんと返済を続けていれば問題はなく、物件は最終的に自分のものになります。
この記事を通して、抵当権の基本的な仕組みを正しく理解し、安心して住宅ローンを利用できる一助となれば幸いです。
