
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
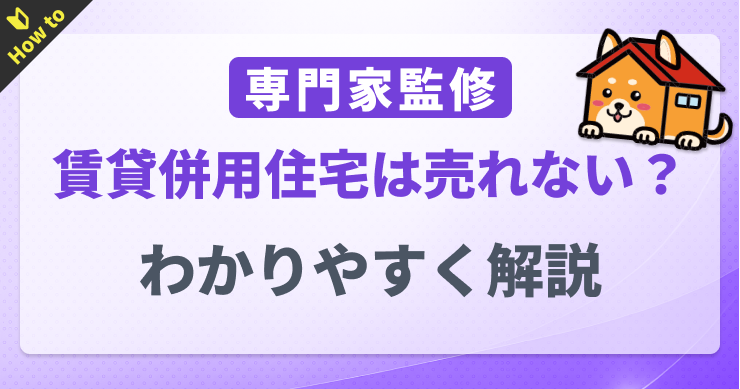
「賃貸併用住宅は」、マイホームとしての居住性と家賃収入による収益性を兼ね備えていて、家賃収入を住宅ローンの返済に充てられる点が大きな魅力です。
しかし、いざ売却しようとすると「思ったより売れない」「希望の価格で売却できない」と悩む人も少なくありません。
その背景には、購入希望者が限られていることや、一棟アパートに比べて収益性が低いことなど、複数の要因が関係しています。
とはいえ、こうした「売れにくい」と言われる理由を正しく理解し、適切な戦略を立てて売却活動を行うことで、高値でスムーズに売却することも十分に可能です。
この記事では、賃貸併用住宅の売却を検討している方に向けて、売却方法や注意点、税金のポイントをわかりやすく解説します。
「賃貸併用住宅」とは、一つの建物の中に、所有者が居住する「自宅部分」と、第三者に賃貸する「賃貸部分」が共存している住宅のことです。
オーナーが自ら居住しつつ、別の部屋やフロアを賃貸して家賃収入を得ることができるため、住宅ローンの返済を家賃収入で一部まかなえる点が魅力です。
総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、日本の一戸建・長屋建約3,027万戸のうち、「店舗等の住宅以外の部分を含む物件」は、約146万戸(※)です。
「純粋な居住専用ではない住宅」は一戸建・長屋建全体の約4.8%であるため、賃貸併用住宅は市場においても希少性の高い物件であることがわかります。
賃貸併用住宅は、一般的な住宅とは異なり市場流通量が少ないため、「住宅ローンの負担を軽減しつつ、資産性のあるマイホームを持ちたい」人にとって価値の高い物件だといえるでしょう。
※「平成30年住宅・土地統計調査」より筆者算出。本データの「店舗等の住宅以外の部分を含む物件」は、賃貸併用住宅を直接集計したものではなく、自宅兼自営業の店舗・自宅兼自営業の事務所・自宅の一部を事業用の店舗や事務所として第三者に貸している住宅なども含まれます。
賃貸併用住宅の大きな魅力は、住宅ローンを利用しながら賃貸経営ができる点です。
建物の一部にオーナー自身が居住していれば「居住用住宅」として認められ、事業用のアパートローンではなく、住宅ローンを利用できる可能性があります。アパートローンと比べると、住宅ローンは一般的に、低金利・長期返済・税制優遇があるといった点でメリットがあります。
また、賃貸部分からの家賃収入をローン返済に充てることで、実質的な住居費の負担を軽減できます。
さらに、建物の一部を事業用として活用しているため、固定資産税や減価償却費などの面で節税効果が期待できる点もメリットです。
将来的に家族構成やライフスタイルが変化した場合には、賃貸部分を自宅に転用したり、逆に自宅部分を賃貸に出したりと、柔軟な運用も可能です。
賃貸併用住宅には収益性の魅力がある一方で、家賃収入に依存した住宅ローンの返済にはリスクもあります。
特に空室が長期間続くと、住宅ローンの返済をすべて自己資金でまかなう必要があるため、資金繰りが厳しくなる可能性があります。
また、入居者との生活トラブルにも注意が必要です。騒音やマナー違反、契約違反など、さまざまな問題が起こるリスクがあるため、入居者の選定や賃貸管理体制を整えることが重要です。
さらに、同じ建物内に他人が住むことで、プライバシーの確保が難しく感じることもあります。特に、玄関や廊下などの共用スペースがある場合、生活音や人の出入りにストレスを感じるケースもあります。プライバシー性を高める間取りの工夫や防音対策は、快適な暮らしを実現するためのポイントです。
賃貸併用住宅は、家賃収入を前提に資金計画を立てるケースも多いですが、立地条件や建物設備、周辺環境によっては入居率が予想を下回り、家賃収入が安定しない可能性があります。その結果、ローン返済が家計を圧迫し、経済的に苦しくなるリスクが「やめとけ」「危険」と言われる理由の一つです。
また、賃貸併用住宅は自宅と賃貸部分が一体となった特殊な物件であるため、将来の売却においても注意が必要です。購入希望者が「投資目的」か「自宅用」かによってニーズが分かれるため、一般の戸建て住宅や投資物件に比べて売却しづらく、価格が想定より低くなるケースがあります。
購入後に後悔しないためには、購入時点で将来的な出口戦略まで見据えた計画を立てておくことが重要です。
この章では、賃貸併用住宅が他の不動産に比べて売却が難しいと言われる理由について解説します。
賃貸併用住宅が売れないと言われる理由の一つに、購入希望者が限定されることが挙げられます。賃貸併用住宅は、自宅と賃貸部分が一体化しているため、自宅と投資の両方を求める購入層にしかマッチしません。
たとえば、自宅用としての購入を検討している人は、「賃貸部分は不要」「他人と同じ建物に住むことに抵抗がある」と感じたり、投資用物件を探している人は、「自宅部分が収益を生まないため非効率」と判断したりと、どちらの購入層からも敬遠されがちです。
このように、どちらのニーズにも完全には合致しないため、購入層が限定的になってしまうのです。
賃貸併用住宅が投資目的の人から敬遠される理由の一つに、利回りの低さが挙げられます。
自宅スペースがある賃貸併用住宅は、建物の一部しか賃貸として貸し出せないため、全体に占める賃貸部分の割合が少なくなります。そのため、表面利回り(物件価格に対する年間家賃収入の割合)を比較すると、一般的な一棟アパートに比べて見劣りする傾向があるのです。
たとえば、2階建ての住宅で1階部分のみを賃貸として運用する場合、同価格・同規模の一棟アパートと比べて、利回りはおおよそ半分程度に下がることがあります。
例:価格・面積が同じ1億円/200㎡の物件における表面利回りの比較
| 物件種別 | 物件価格 | 年間家賃収入 | 表面利回り |
| 一棟アパート
(全200㎡が賃貸) |
1億円 | 600万円 | 6.0% |
| 賃貸併用住宅
(100㎡が自宅、100㎡が賃貸) |
1億円 | 300万円 | 3.0% |
表面利回りは投資判断の指標であり、低い物件は市場評価も下がりやすくなります。利回りを重視する投資家にとっては、投資効率が悪いと判断されやすいのです。
賃貸併用住宅の売却時に賃貸部分に入居者がいる場合は「オーナーチェンジ物件」として扱われ、以下のような制約が発生します。
まず、買主が室内を内見できないことが多く、物件の状態を確認できないまま検討を進めることになります。そのため、購入判断が慎重になり、売却活動が長期化する可能性があります。
次に、賃貸借契約の継承と敷金の引き継ぎが必要です。買主は、既存の契約条件を引き継ぐことになるため、賃料の見直しや退去交渉などが自由にできず、運用の自由度が制限されます。
さらに、入居者に退去を求める場合は、借地借家法に基づく「正当事由」が必要です。正当な理由がない場合は、立ち退き料の支払いによって合意を得るケースが多く、一般的には月額家賃の6か月〜12か月分が目安とされています。
このように、オーナーチェンジ物件としての売却には法的・実務的なハードルが多いことも、賃貸併用住宅が売れないと言われる理由の一つです。
賃貸併用住宅の売却を成功させるには、物件の特性を理解し、収益性や住環境の魅力をアピールすることが重要です。この章では、賃貸併用住宅の売却を成功させる4つのポイントを解説します。
賃貸併用住宅の売却を成功させるには、売却時期の見極めが重要です。不動産市場が活発になる1月〜3月の新生活シーズンや、9月〜11月の転勤シーズンに合わせて売却活動を開始することで、より多くの購入希望者に物件を見てもらえる可能性が高まります。
また、賃貸部分が満室の状態で売却に出すことも効果的です。満室であれば、その物件が安定した家賃収入を生んでいる証拠となり、投資家にとって安心材料となります。そのため、価格交渉の場面でも売主が有利に進めやすくなるでしょう。
一般住宅と収益物件の両方の性質を持つ賃貸併用住宅は、価格設定に注意が必要です。
賃貸併用住宅の価格査定では、周辺の類似物件との比較による「取引事例比較法」と、家賃収入をもとに価値を算出する「収益還元法」の両方を使って評価されます。
| 評価方法 | 算出方法 | ポイント |
| 取引事例比較法 | 類似物件の過去取引から相場を推定 | 近隣で実際に売買された類似物件の価格を参考にして、立地や条件を補正しながら算出する方法。 |
| 収益還元法 | 年間家賃収入 ÷ 利回り | 将来得られると見込まれる賃料収入から価格を逆算する方法で、収益物件では最もよく使われる評価方法。利回りを基準に、投資家が期待する収益水準から妥当な価格を割り出す。 |
※参照元:不動産鑑定評価基準
査定は、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。それぞれの査定額の根拠や見解を比較検討し、適正な価格を設定しましょう。
物件の魅力を正確に伝えるための資料や写真を整えることも重要です。特に賃貸併用住宅の場合は、自宅部分と賃貸部分のそれぞれの特徴に応じて情報を整理するのが効果的です。
まず、自宅部分は、明るく清潔感のある状態で撮影した写真を用意しましょう。購入希望者が実際の暮らしをイメージしやすくなり、内覧や問い合わせのきっかけになります。
一方で、賃貸部分は、投資用不動産としての魅力を伝えることがポイントです。修繕履歴、建物の管理状況、家賃収入の実績といったデータを資料としてまとめることで、物件の収益性や管理状況の良さを客観的に示すことができます。
資料や写真が揃っていることで、買主に安心感を与え、成約率の向上にもつながります。
賃貸併用住宅の売却では、居住用・投資用の両方に精通した実績豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。
自宅としての側面と投資物件としての側面を併せ持つため、一般的な住宅仲介の知識だけでは不十分です。収益性を訴求した販売戦略や、ターゲット層に刺さる広告展開ができる会社であれば、より高く・早く売れる可能性が高まります。
不動産会社との面談時には、過去の取り扱い実績や販売方法を具体的に確認することをおすすめします。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
賃貸併用住宅の売却は、住宅としての側面と収益物件としての側面をあわせ持つため、一般的な不動産売却とは異なる特有の注意点も存在します。この章では、4つの注意点を解説します。
住宅ローンの残債と抵当権の状況を確認することは、賃貸併用住宅に限らず、不動産売却でのトラブルを未然に防ぐために不可欠なプロセスです。
民法第369条では、抵当権は、債務者(ローンの借主)がその担保として提供した不動産について、他の債権者に優先して自己の債権(ローン)の弁済を受ける権利であることが定められています。つまり、金融機関にとって、貸したお金を確実に回収するための切り札になるのが抵当権です。
抵当権は、ローンを完済しなければ抹消できないため、売却によって得られる金額でローンを完済できるか(アンダーローンか)を事前に確認しておく必要があります。逆に、売却価格よりローン残債が多い「オーバーローン」の状態であれば、不足分を自己資金で補わなければ抵当権を抹消できず、売却が進められない場合もあります。
こうした事態を避けるためにも、売却を検討し始めたら、金融機関に「残高証明書」や「返済予定表」の発行を依頼し、資金状況を正確に把握しておきましょう。
賃貸併用住宅の売却では、特に契約不適合責任への対応に注意が必要です。
2020年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更され、売主の責任がより厳格に明確化されました。そのため、後の深刻なトラブルを回避するためにも、売主は知っている不具合をすべて正確に告知する義務を果たす必要があります。
賃貸併用住宅の場合、「自宅」「賃貸部分」「共用部」の3つの異なる性質を持つ空間で構成されていることから、告知すべき内容は多岐にわたります。
売却後に、契約書に明記されていなかった不具合が発覚すると、買主から修繕・代金の減額・契約解除などを請求される可能性があります。特に賃貸部分の不具合は、買主の家賃収入計画(事業計画)に直接的な損害を与えかねません。シビアな紛争に発展するリスクもあるため、注意が必要です。
賃貸併用住宅の売却では、自宅部分と賃貸部分が混在することから、按分計算や各種特例の適用関係、減価償却の考慮など、税務計算が複雑になります。思わぬ過少申告や、活用できたはずの特例を逃すといったことのないよう、正確な判断が必要です。
たとえば、自宅部分は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例が適用される可能性があります。ただし、自宅部分が9割未満の場合は、複雑な按分計算が求められます。賃貸部分は、事業用資産として扱われるため、この特例が適用されません。(租税特別措置法第35条)
また、特例を使うと新たな住宅ローン控除が数年間使えなくなる制約もあるため、住み替えの場合にも注意が必要です。
賃貸併用住宅の売却に伴う税務計算は専門性が高いため、税理士や管轄の税務署に相談することをおすすめします。
賃貸併用住宅を入居者がいる状態で売却(オーナーチェンジ)する時は、敷金や賃貸契約の内容を正確に引き継ぐ必要があります。
入居者から預かっている敷金は、売主から買主へ全額引き継がれるべき金銭のため、売主は敷金相当額を買主に引き渡す(または売買代金から相殺する)必要があります。
また、家賃・共益費・契約期間・更新料・禁止事項などの賃貸借契約の内容は、正確に開示しなければならず、不備があるとトラブルの原因になりかねません。
買主が賃貸条件を正確に把握できるよう、事前に契約内容を整理し、適切に情報開示を行うことが売却後のトラブル防止につながります。
賃貸併用住宅には、売却以外にもさまざまな出口戦略があります。
たとえば、空室が多く収益性が低い場合には、リフォームの実施、家賃や管理方法の見直しなどを行うことで、入居率の改善と収益向上を図り、そのまま保有・運用を続ける選択肢があります。
また、自宅部分も賃貸に出し、建物全体を収益物件として運用することも可能です。これにより家賃収入が増え、投資物件としての魅力も高まります。
さらに、マイホームを探すファミリー層への売却や将来的な相続を見据えて、二世帯住宅や一戸建て住宅への改装を行う方法もあります。二世帯住宅への改装は、「小規模宅地等の特例」が適用されれば、相続税の軽減効果が期待できるため、事前に適用条件を確認しておくことが重要です。
「売却が難しい」と言われる賃貸併用住宅だからこそ、状況に応じた出口戦略を検討し、資産価値の最大化を目指しましょう。
あなたが保有する賃貸併用住宅の売却難易度をチェックしてみましょう。
【診断結果】
「はい」が5個以上:売却しやすい可能性大。複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を確認しましょう。
「はい」が2〜4個:やや売却に工夫が必要。リフォームや空室対策、資料の整備、アピール方法次第で条件が改善できる可能性があります。
「はい」が0〜1個:売却困難な可能性大。リフォームや賃料の見直しなど、別の出口戦略も含めて、専門業者へ早めの相談を検討しましょう。
賃貸併用住宅の売却は、通常の住宅や投資物件とは異なる特性があるため、売れにくいと感じる方も少なくありません。
しかし、購入希望者の傾向や収益性の評価、入居者の有無といったポイントを押さえ、タイミングや価格設定、資料の準備を工夫することで、スムーズに売却できる可能性は十分にあります。
資産価値を最大化できるよう、状況に応じた出口戦略を検討しましょう。
