
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
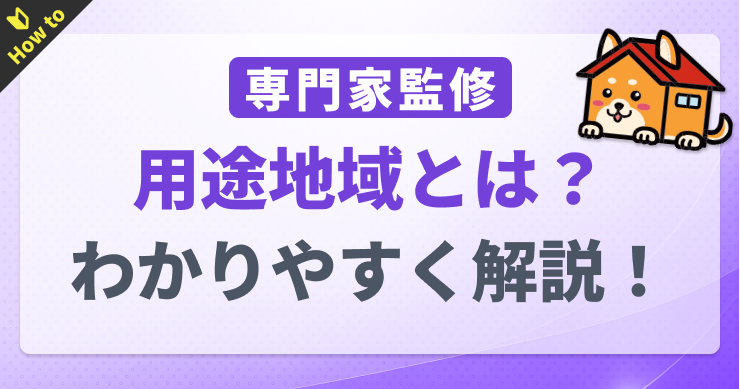
「用途地域って何?」「この土地に家を建てても大丈夫?」
土地選びや建築計画を進めるうえで、こんな疑問を抱いたことはありませんか?
用途地域では、地域ごとに建てられる建物の種類や規模に制限が設けられています。しかし、13種類もある用途地域の違いはわかりにくく、専門用語も多いため、初めての方は戸惑いやすい分野です。
この記事では、用途地域の意味や13種類それぞれの特徴・建築制限の内容を解説します。用途地域を確認する方法や注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
用途地域とは、都市の秩序ある発展と住環境・景観の保全を目的として、建築できる建物の用途や規模を制限する制度です。土地計画法に基づき、都道府県知事が指定する市街化区域内で定められます。
住宅系・商業系・工業系に大きくわけられ、13種類の用途地域が指定されています。
用途地域を定めることで、住環境の保護と商業・工業の円滑な運営が図られるとともに、不動産取引においても重要な判断基準となります。用途地域は、その地域の特徴や将来の環境を把握するうえでも重要な指標です。
【用途地域に関する基本情報】
用途地域は、地域ごとに、どんな建物が建てられるかを制限することで、都市の健全な発展を支える土台となるものです。
例えば、住宅街の中に突然大きな工場が建つと、騒音や大型の車の出入りなどで、良好な住環境が損なわれ、安全性の問題が生じる恐れがあります。
用途地域で工場が建てられる地域を制限することで、商業活動や工業活動するうえで発生するトラブルを未然に防ぐことができます。
「用途地域とは何か」を正しく理解することで、自身の暮らしや不動産取引におけるリスク回避にもつながるでしょう。
用途地域は、都市計画法に基づいて、住宅系(8種類)・商業系(2種類)・工業系(3種類)の13種類に分類されたエリアです。それぞれのエリアごとに建てられる建物の用途や規模、高さなどが制限されています。
用途地域で区分することにより、地域ごとの特性に合った土地利用が実現できます。用途地域ごとの違いを把握することは、不動産の取引や新たに建物を建築するうえで不可欠です。
| 用途地域の分類 | 種類 | 主な特徴 |
| 住居系 | 8種類(例:第一種低層住居専用地域) | 良好な住環境の整備・保全が目的。騒音や環境悪化の原因となる、商業施設や工場などの建築が制限されている。商業系・工業系と比べて建てられる建物の制限が厳しい。 |
| 商業系 | 2種類(近隣商業地域・商業地域) | 駅周辺や都市の中心部など、人が集まりやすい地域が指定され、主に商業や業務活動の利便性を高めることが目的。 土地を有効活用するために、建ぺい率や容積率などの制限は緩やかになっている。 |
| 工業系 | 3種類(準工業地域・工業地域・工業専用地域) | 工業の利便性を促進することを目的として定められ、主に工場やその関連施設の建築を促進する地域。工業専用地域では、住宅の建築も制限されている。 |
それぞれの用途地域の特徴を理解することで、事前に希望する建物が建てられるかどうかを把握できます。
特に、住居系は良好な住環境の保護を目的としているため、商業施設や工場などが制限される点に注意が必要です。
一方で、商業系や工業系の地域は、商業活動や工業活動を促進するための地域として指定されるため、住宅を建てる際は、住環境と生活利便性とのバランスを考慮する必要があります。
13種類の用途地域の特徴を知ることで、土地活用や不動産選びの判断材料になるでしょう。
住居系の用途地域は、静かで快適な生活環境を守るために定められたエリアで、13種類の用途地域のうち8種類が該当します。
8種類の用途地域のなかでも、建築可能な建物や建てられる建物の規模、建ぺい率の上限などは異なります。
低層住宅を中心とする地域から中高層の集合住宅が建てられる地域まで、段階的に建てられる建物の用途が広がっていくのが特徴です。ただし、キャバレーなど一部の風俗施設や、環境を悪化させる恐れの高い工場などは、住居系の用途地域では建てられません。
住環境を重視するエリア選びでは、まずこの住居系の用途地域の違いを理解することが第一歩となります。
| 名称 | 主な特徴と建築制限 |
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、戸建て住宅が中心。建物の高さ制限(10mもしくは12m)があり、集合住宅も3階建て程度まで。幼稚園や学校は建てられるが、店舗や事務所は原則不可。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 第1種低層と同様、低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、建物の絶対高さ制限がある。日用品の販売店や喫茶店などで床面積が150㎡以下の小規模店舗は建てられるため、日常のちょっとした買い物には便利な地域。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。床面積500㎡以下の店舗のほか、病院や大学などが建築可能。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域に建てられる建物に加え、床面積が1,500㎡以下の店舗・飲食店などが建築可能。 |
| 第一種住居地域 | 住宅環境を保護するための地域。床面積3,000㎡以下の店舗や事務所、ホテル、自動車教習所などが建築可能。 |
| 第二種住居地域 | 主に住環境を守るための地域で、床面積10,000㎡を超える店舗のほか、パチンコ店やカラオケボックスなども建築可能。 |
| 田園住居地域 | 農業の利便性を図りつつ低層の住環境を保護するための地域。制限内容は、第1種低層住居専用地域と近くなっている。 |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いにおいて、自動車関連施設などと住居が調和する住環境を保護するための地域。
住居系のなかで最も制限が緩く、3階以上または300㎡を超える自動車倉庫や床面積150㎡以下の自動車修理工場なども建築可能。 |
住居系用途地域の分類は、不動産購入に直接関わる非常に重要な情報です。たとえば、「静かで落ち着いた住宅地に住みたい」と考えている人には、多少不便でも第一種低層住居専用地域が適しています。一方で、買い物など生活利便性を優先したい場合は、第二種住居地域のような選択肢も考えられます。
住環境としての良好さと生活利便性のバランスを見極めるために、それぞれの制限内容と特徴を押さえておくことが大切です。
参照:東京都都市整備局|用途地域による建築物の用途制限の概要
※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
こんな悩み、抱えていませんか?
こうした悩みがある場合は、手軽に試せる不動産一括査定がおすすめです。
今の家がいくらで売れるか不安で、新しい住まい探しに踏み切れない
税金や名義変更の手続きも含め、何から始めればいいのか分からない
会社によって売却額が数百万円変わると聞き、選び方で損をしないか心配
簡単な質問に答えるだけで最大6社があなたの物件価値をしっかり査定します。その中から「信頼できる一社」を見つけて理想的な不動産売却を実現させましょう。

商業系用途地域は、商業その他の業務の利便性を促進するための地域です。主に、駅前や都市の中心部など、人やサービスが集まるエリアに設定されます。
住宅やオフィスに加えて、スーパーや飲食店、娯楽施設など多様な建築が可能で、買い物や飲食などの生活利便性の高さが特徴です。2種類に分類され、日常的な買い物エリアと大規模商業ゾーンとで役割が分かれています。人の流れや交通量が多い地域に設定されることが多く、住居もある程度は建てることができます。
| 名称 | 主な特徴と建築可能施設 |
| 近隣商業地域 | 主に、近隣の住宅地に住む住民に日用品の供給を行うことを目的とする地域。床面積10,000㎡までの店舗や商業施設、遊技場のほか、床面積150㎡までの小規模な工場も建築可能。 |
| 商業地域 | 店舗・事務所・商業施設の利便性を促進するための地域。都市の中心部に設定され、高層ビル・百貨店・映画館のほか、風俗営業施設も建築可能。一部の工場や危険物貯蔵庫を除いて、工場や倉庫も建てることができる。建ぺい率・容積率も高いため、高層ビルやマンションが密集するエリアが形成される。 |
商業系地域は、生活の利便性を重視したい人や、商売を考えている事業者にとって有効な選択肢となります。
特に商業地域は、建築制限が緩やかであるため、多くの施設が集まりやすいのが特徴です。一方で、住環境として選ぶ場合は、騒音や交通量、防犯性などの周辺環境について慎重な確認が必要です。住環境と商業活動がどのように共存しているかを把握したうえで、購入の判断をしましょう。
工業系用途地域は、主に工場における業務の利便性促進を目的とし、製造業や物流事業などが円滑に活動できるように設けられた区域です。
住宅地と異なり、騒音や振動などの発生が想定される施設も建設が可能です。ただし、3つの工業系地域のなかでも、危険性や環境悪化の恐れの程度に応じて建築できる施設に違いがあります。住居の建築が可能な地域もありますが、住環境の快適性は限定的であるため、慎重な判断が必要です。
| 名称 | 主な特徴と建築制限 |
| 準工業地域 | 主に、環境の悪化をもたらす恐れが少ない工業の利便を増進するための地域。工場や倉庫のほか住宅や学校、店舗などが混在して立地することが多い。商業地域と並んで建てられる用途の範囲が広く、ほとんどの建物は建築可能。 |
| 工業地域 | 主に、工業の利便性促進を図るための地域。住宅や店舗も建てられる一方、危険性や環境を悪化させる恐れが多い工場も建築可能。学校や病院、ホテルなどは建築不可。 |
| 工業専用地域 | 工業の利便性を促進するための地域。工業の増進を妨げる用途の建築が原則として禁止され、住宅や学校、病院、店舗などの建築は不可。 |
工業系用途地域は、3つの地域のなかでも、建築可能な建物に違いがあります。たとえば、準工業地域や工業地域では、工場と住居、店舗が混在している一方、工業専用地域では住宅が建てられません。そのため、不動産活用や土地購入を検討する際は、利用目的に応じてそれぞれの違いを把握しておくことが重要です。
参照:東京都都市整備局|用途地域による建築物の用途制限の概要
※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
こんな悩み、抱えていませんか?
こうした悩みがある場合は、手軽に試せる不動産一括査定がおすすめです。
今の家がいくらで売れるか不安で、新しい住まい探しに踏み切れない
税金や名義変更の手続きも含め、何から始めればいいのか分からない
会社によって売却額が数百万円変わると聞き、選び方で損をしないか心配
簡単な質問に答えるだけで最大6社があなたの物件価値をしっかり査定します。その中から「信頼できる一社」を見つけて理想的な不動産売却を実現させましょう。

田園住居地域は、都市計画法の改正によって、2018年に新たに追加された用途地域で、農業と住居の共存を目的としています。
これまで明確な位置づけがなかった「市街化区域内の農家住宅」などを制度的に支え、都市部において宅地化されず残っている貴重な農地を保全するための地域です。農地を活用しながら住むことができるという特徴があり、都市と農の調和を目指した新しい用途地域といえます。
| 主な特徴 | 内容 |
| 施行年 | 2018年(平成30年) |
| 建築可能な施設 | 住宅 農産物直売所・農家レストラン(2階以下) 農産物・農業の生産資材を貯蔵する倉庫 農産物を生産、集荷。処理。貯蔵するための工場など |
| 建築が制限される施設 | 一定規模の店舗や事務所のほか、大学、ホテル、遊戯・風俗施設など |
| 主な目的 | 都市部における農地の保全 |
田園住居地域は、特に都市近郊の農地保全を意識した政策的背景を持っています。第1種低層住居専用地域に準じた扱いですが、農業との両立を前提にした土地利用が想定されているため、一般の住宅用地とは異なる運用ルールが存在します。農業関連施設を計画している人や農地転用を検討している人にとって、理解しておくべき重要な用途地域です。
用途地域によって、建てられる建物の種類や建築に関する制限は大きく異なります。たとえば、住宅専用地域では工場や商業施設の建築が制限される一方、商業地域では住宅から映画館まで幅広く建てられるのが特徴です。
これにより、地域の特性に基づいて効率的な土地活用ができるだけでなく、住民同士のトラブル防止にもつながっています。建てたい建物の種類が用途地域に適合しているかの確認は、土地活用の第一歩です。
| 制限項目 | 内容の例 |
| 建築可能用途 | 住宅/店舗/事務所/学校/病院/ホテル/遊戯・娯楽施設/工場などの可否 |
| 建ぺい率 | 敷地面積に対する建築面積の割合 |
| 容積率 | 敷地面積に対する延床面積の割合 |
| 高さ制限 | 建物の最高高さに関する制限(絶対高さ制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制など) |
このような制限は、都市ごとに細かく定められており、同じ用途地域でも自治体によって内容が異なることがあります。
たとえば、建ぺい率・容積率は、原則的に定められている建ぺい率と容積率から、地域の事情を考慮して、特定行政庁※が指定します。そのため、土地を購入する場合は、自治体の都市計画図の確認が不可欠です。思い描く建物を実現するには、用途地域に加えて制限内容にも注意しましょう。
※特定行政庁は、建築主事を置く地方公共団体およびその長。建築主事がいない市町村は、都道県知事が特定行政庁になる。
用途地域は、土地購入や建物を建てる前に必ず確認すべき項目です。自治体が公表している都市計画情報を参照することで、自分の土地がどの用途地域に該当するかを調べることができます。現在は、インターネット上でも閲覧できる自治体が増えており、誰でも簡単にアクセスできるようになっています。
【用途地域の確認方法】
用途地域を調べる際は、インターネット上の都市計画図が最も手軽です。ただし、用途地域以外の詳細な制限を確認したいときには、役所の窓口で問い合わせましょう。
また、一つの土地に複数の用途地域がまたがっている場合は、制限の種類によって適用の仕方が変わります。たとえば、建物に適用される用途制限は、敷地面積が大きい用途地域が適用されますが、高さ制限は、それぞれの用途地域の制限を受けます。
実際にどういう建物が建築可能で、どういった制限を受けるのかを確認することが重要です。
用途地域の確認作業において、情報の取得そのものより「制限の内容をどのように解釈するか」が重要になるケースがあります。
特に注意すべきは、一つの敷地が複数の用途地域にまたがっているケースや、自治体によって制限内容が異なるケースです。また、地図上で確認できる内容と、条例で定められた制限が違う場合もあるため、都市計画図の確認だけでは不十分なこともあります。
【注意すべきポイント】
用途地域の確認は単なる「場所の確認」だけでなく、規制内容に対して、実際に建てたい建物の適合性を読み取る作業でもあります。
特に、初めて土地を購入する方や、建物の用途変更・建替えを予定している場合には、正確な把握が欠かせません。不動産業者でも見落とすケースがあるため、複数の手段で確認すると安心です。
用途地域は、都市の秩序ある発展と住環境の保全を目的として、建てられる用途や規模を制限する制度です。
用途地域ごとの制限内容を把握しておくことで、不動産購入や建築計画において失敗するリスクを回避できます。用途地域の基礎知識を持つことは、土地活用の第一歩といえるでしょう。
【用途地域を理解するための要点】
土地選びや建物を新築する際に、「ここはどういう地域でどういった建物が建築可能なのか」を把握することが意思決定の質を大きく左右します。
特に、住宅地としての落ち着いた環境や、買い物や交通の利便性など、自分が重視するポイントと照らし合わせて判断することが重要です。
用途地域の意味を正しく理解し、正確に解釈することで、失敗のない土地選びが可能になります。
