
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
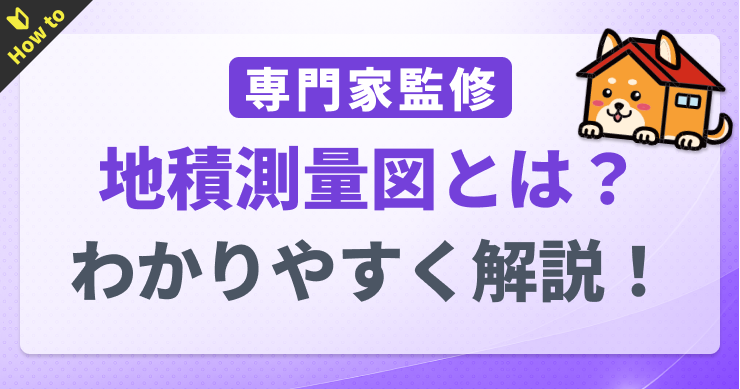
土地を売却したり相続したりする際、「地積測量図が必要」と言われて戸惑ったことはありませんか?公図との違いや取得方法がわかりにくく、どうすればよいか悩む方は少なくありません。
この記事では、地積測量図の意味や見方、公図との違い、取得方法までをわかりやすく解説します。
「地積測量図」とは、土地の正確な「面積」や「形状」、「境界線」を明示するために作成される図面です。法務局に備え付けられるもので、主に不動産登記の際に使用されます。地積測量図は、測量士が実地測量を行ったうえで作成するため、公図などと比べてはるかに精度が高いのが特徴です。不動産売買や相続、建築許可など、さまざまな場面で用いられる重要な資料です。
地積測量図は、登記申請や土地取引の裏付け資料として法的効力を持ち、境界に関するトラブルを防ぐうえでも重要な図面です。ただし、土地ごとに作成されているとは限らないため、必要に応じて新たに作成が求められる場合もあります。公図のように、全ての土地に存在するわけではない点にも注意が必要です。
地積測量図の法的根拠は、不動産登記法施行規則第17条に定められています。特に、土地の分筆登記を行う際にはこの図面が必須とされ、正確な面積や境界の確認が求められます。
現場では、地積測量図が整備されていないことが原因で取引が遅延したり、建築確認申請が通らなかったりするケースもあります。不動産業者や測量士がよく直面するのは、買主が金融機関から融資を受ける際に、地積測量図の提出を求められる場面です。
そのため、不動産の売却を検討している方は、早い段階で地積測量図の有無を確認しておきましょう。
地積測量図と似た測量図に、「確定測量図(確定実測図)」や「現況測量図」があります。これらはいずれも土地の形状や面積を表す点では共通していますが、境界の取り扱いや法的効力に違いがあります。特に、不動産の売買や登記など、実務に関わる場面では、この違いを正しく理解することが重要です。
【地積測量図・確定測量図・現況測量図の比較】
| 項目 | 地積測量図 | 確定測量図(確定実測図) | 現況測量図 |
|---|---|---|---|
| 境界の確定 | 隣接地所有者との立会いあり | 隣接地所有者との立会いあり | 立会いなし |
| 作成者 | 測量士または土地家屋調査士 | 土地家屋調査士(依頼者による) | 土地家屋調査士 |
| 利用目的 | 登記・売買などの公的手続きに使用可 | 登記・売買などに使用可(個人所有) | 現況把握の参考用、売買には不向き |
| 図面の保管先・取得方法 | 法務局に備え付け、誰でも取得可能 | 土地所有者が保管(再取得には再測量要) | 所有者が保管(公的取得不可) |
確定測量図は、記載内容や境界の確定方法において地積測量図と同等の信頼性を持ちますが、法務局で取得できない点が大きな違いです。一方で、現況測量図は境界の合意がなく、あくまで現地の状況を測量した参考資料の位置づけとなるため、法的な効力は限定的です。
現場では、確定測量図を「地積測量図と同じもの」と誤解されるケースがありますが、法務局に登記されていない以上、第三者が取得することはできません。
そのため、不動産取引の場面では「登記情報として提出可能かどうか」が判断基準となります。
また、現況測量図のみを根拠に売買契約を進めた結果、後に境界をめぐるトラブルに発展した事例もあります。土地家屋調査士の実務では、「確定測量図を法務局に備え付けの地積測量図として登記したい」という依頼もありますが、その際は再度の登記申請の手続きが必要になります。境界確定の有無は、法的・実務的に大きな差を生むため、測量図の種類を正しく把握しておくことが重要です。
地積測量図と公図は、どちらも土地の位置や形状を示す図面ですが、目的や精度が異なります。公図は主に土地の大まかな位置や地番を把握するための「参考図」として機能する一方、地積測量図は登記や売買に必要な正確な図面として利用されます。
この違いを知っておくと、どちらの図面を使用すべきかの判断がしやすくなるでしょう。
【地積測量図と公図の主な違い】
| 項目 | 地積測量図 | 公図 |
|---|---|---|
| 作成目的 | 登記のための正確な測量図 | 土地の位置・形状の参考図 |
| 作成主体 | 測量士などの専門家 | 明治期の土地調査をもとに作成 |
| 精度 | 高い(境界標・縮尺あり) | 低い(目安程度) |
| 取得場所 | 法務局または登記情報提供サービス | 法務局 |
| 使用場面 | 登記・売買・境界確定など | 所在確認・地番の参照 |
公図はその起源が明治時代の地租改正事業にあるため、現況とのズレが生じることがあります。一方で、地積測量図は現代の測量技術と法律に基づいて作成されるため、高い正確性があります。不動産取引や境界確認では、地積測量図の利用が推奨され、公図はあくまで参考情報と考えるのが一般的です。
実務では、公図をもとに境界を判断してしまい、実際の筆界と大きく異なっていたというトラブルが少なくありません。公図上は隣地との間に明確な空地があったにもかかわらず、現地では塀が敷地を越えて設置されていたという事例もあります。こうしたズレは、公図の精度が十分でないために起こる典型例です。
法務省も公図を「登記簿の内容を補足する参考図」として位置づけており、法的な境界を示すものではないと明示しています。
境界の確定が必要な場面では、公図だけを根拠とせず、地積測量図や確定測量図の有無を必ず確認することが重要です。必要に応じて、土地家屋調査士への相談も検討することをおすすめします。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
地積測量図を正しく読み解くことで、土地の境界や面積、形状などを正確に把握できます。図面には多くの情報が含まれているため、どこを見ればよいかを知っておくことが大切です。特に土地の売買や建築に関わる際には、境界線・面積・方位などの確認が求められるケースが多くなります。
地積測量図には、現地の状況や測量精度に基づいて記された具体的な情報が記載されています。たとえば、面積だけでなく、隣地との筆界における合意の有無や、立ち会い測量の記録などが備考に書かれていることもあります。
こうした内容を読み解けるかどうかが、実務における判断やトラブルの回避に大きな差を生みます。
測量士や土地家屋調査士の実務では、「図面の面積と実測の面積が大きく異なる」ケースがよくあります。これは、古い測量技術による誤差や、境界標の紛失によって再測量が必要になるためです。買主が図面を確認せずに契約を進めた結果、後に越境や境界紛争が発覚し、再測量や隣接者とのトラブルが発生してしまうことも珍しくありません。
また、不動産登記法施行規則第17条では、面積を伴う登記変更時には、原則として地積測量図が必要とされています。
動産を売却する際のトラブルを防ぐためにも、図面の見方を事前に確認し、不明点は土地家屋調査士など専門家に相談すると安心です。
地積測量図は、土地の登記内容を確認したい場合や、売買・相続手続きに必要な場面で取得できます。一般的には法務局の窓口か、オンラインサービスを利用して取得することができます。ただし、すべての土地に地積測量図が存在するとは限らないため、事前の確認が重要です。
それぞれの取得方法について詳しく解説します。どの取得方法が目的に合っているのかを考えながら読み進めてみましょう。
地積測量図は、土地の所在する地域を管轄する法務局の窓口で直接取得できます。図面があるかどうかは法務局によって異なるため、あらかじめ確認をしてから訪問するとスムーズです。取得には土地の「地番」が必要となるため、登記簿や固定資産税通知書などで事前に確認しておきましょう。
窓口での手続きは比較的簡単ですが、混雑状況や図面の所在によっては即日発行できない場合があります。また、同一地番内に複数の地積測量図が存在するケースもあるため、係員の案内を受けながら申請を進めると確実です。
実務では、建築確認申請や農地転用の手続きの際に、申請者が「法務局で地積測量図を取得しようとしたが、図面が存在しなかった」というケースも少なくありません。そのような場合、法務局では「地積測量図不存在証明」の発行が可能です。
これは、図面が存在しないことを公式に証明する文書であり、新たな測量や図面作成の出発点として重要な意味を持ちます。
地積測量図は、インターネット上の「登記情報提供サービス」からも取得できます。外出せずに手続きできるため、忙しい方や遠方の土地を扱う方にとって便利な手段です。利用にはユーザー登録が必要ですが、図面の有無を検索し、必要な書類だけを取得できる利便性があります。
手続きは全国どこからでも申請できます。PDFデータでダウンロードできるため、すぐに関係者と共有したい場合にも適しています。登記情報提供サービスは、法務省の外郭団体である公益財団法人 不動産登記情報センターが運営する公式サービスです。信頼性が高く、情報も最新に保たれています。
ただし、オンラインでは提供されていない古い図面や、地積測量図自体が作成されていない土地も一部存在します。このような場合は、法務局の窓口での確認が必要になります。
また、手数料の支払いにはクレジットカードが必要なため、法人名義で取得する場合などはあらかじめ支払方法を整えておくことも大切です。
地積測量図の取得に手間取る場合や、図面がそもそも存在しない可能性がある場合には、土地家屋調査士に依頼するのが安心です。専門家が法務局での調査から現地測量まで対応してくれるため、取得にかかる不安や負担を大幅に軽減できます。特に売却や分筆、境界確認が関わる場面では、最も確実な手段といえます。
依頼費用は案件の内容によって異なりますが、調査・測量・作図までを含めて、数万円〜数十万円程度が目安です。登記まで含めたフルサポートを希望する場合は、事前に見積もりを取っておくと安心です。
実務では「地積測量図が見つからない」「図面が古すぎて使えない」といったケースも多く、土地家屋調査士の出番となることがよくあります。調査士は、法務局の図面閲覧や現地での境界標の確認を通じて、土地の実態を把握します。
また、地積測量図がない場合でも「確定測量図」や「現況測量図」を作成して対応することが可能です。こうした対応により、売却や登記の遅延を防ぐことができます。
公益社団法人・日本土地家屋調査士会連合会の公式サイトでは、地域ごとの調査士検索も可能です。
地積測量図は、不動産の正確な情報を把握するために欠かせない重要な資料です。特に、境界や面積に関するトラブルの防止や、登記や売買の際の信頼性確保のために大きな役割を果たします。公図と異なり、精密な測量に基づいて作成されるため、より信頼性が高い図面として扱われます。
地積測量図を適切に活用すれば、不動産取引の安全性や信頼性が大きく高まります。取得や活用には一定の知識が必要なため、不安なときには専門家のサポートを受けながら進めると安心です。特に相続や売却など、利害関係が発生するタイミングでは、早めの確認が後のトラブル防止につながります。
不動産の現場では、測量図の不備や誤解によって買主・売主の間でトラブルに発展するケースが少なくありません。たとえば「登記簿上の面積と現況が一致しない」ことから、買主が融資を受けられなくなる場合もあります。こうしたリスクを回避するには、測量図の確認と整備が前提条件となります。
また、不動産登記法第14条第4項では、図面の登記に関する規定があり、信頼できる測量図の備え付けが制度的にも重視されています。
今後土地の活用や売却を考えている方は、まずは「自分の土地に地積測量図があるか」を確認することから始めてみてください。
