
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
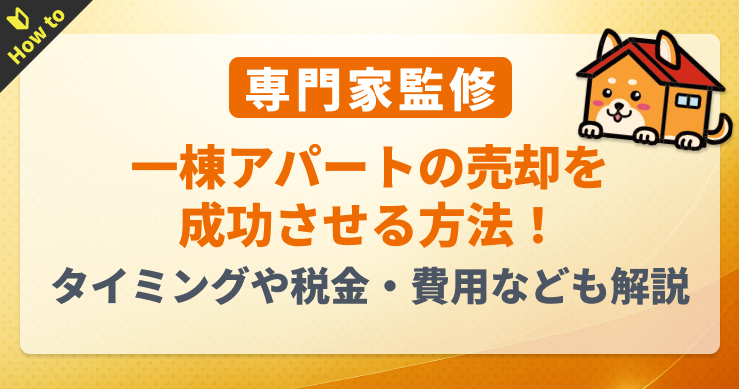
一棟アパートの売却は、「いつ・いくらで・どう売るか」によって、最終的な手取り額や将来的な資産形成に大きな差が生まれます。築年数や減価償却の進行、空室率の増加など、収益性の変化を見極めたうえで、適切なタイミングで売却判断を行うことが重要です。
また、売却には譲渡所得税や登録免許税などの税金や、ローン残債の精算など、見落としがちな費用もあります。
スムーズかつ有利に売却を進めるためには、信頼できる不動産会社の選定と、購入希望者に「買いたい」と思わせる魅力的なアピールポイントの準備が不可欠です。
この記事では、一棟アパートの売却を検討している人に向けて、売却すべきタイミングや相場の考え方、必要な手続き・費用、売却成功のポイントをわかりやすく解説します。
一棟アパートの売却を検討する際は、所有年数や減価償却の状況、築年数などの節目が重要です。また、大規模修繕前や空室率・収支の悪化など、将来的な収益性が下がる兆しが見えたタイミングも判断材料となります。
ここでは、一棟アパートの売却を考える目安となる6つのタイミングを解説します。
一棟アパートの売却で最も重要なのが「所有期間5年超」のタイミングです。譲渡所得にかかる税率が、5年を境に大幅に変わるためです。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となり、税率が合計20.315%に軽減されます。一方で、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として合計39.63%の課税となり、ほぼ2倍の税率がかかってしまいます。
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
たとえば、売却益が1,000万円の場合、所有期間によって税負担は約200万円以上変わる可能性があり、手取り額に大きな差が生じます。
節税効果を最大化するためにも、所有期間5年超での売却は賢明な判断といえます。
一棟アパートの売却を検討する目安の一つに、ローンの元本返済額が減価償却費を上回ったタイミングがあります。
「減価償却費」とは、建物の価値減少分を毎年経費として計上できる制度のことです。税負担を抑える上で重要な役割を果たします。
しかし、国税庁が示す不動産所得の計算ルールでは、ローンの利息は必要経費として認められますが、元本返済額は経費になりません。そのため、ローン返済が進むと、経費になる「利息」が減り、経費にならない「元本」が増えます。
元本返済額が減価償却費を上回ると、手元の現金は減っているのに税金が増える状況になってしまいます。
実際のキャッシュフローと税負担の間にズレが生じる状態が続けば、節税効果が薄れ、税負担だけが重くなってしまいます。そのため、減価償却という税制上のメリットが有効なうちに売却を検討することが、合理的な選択肢の一つとなるのです。
一棟アパートの減価償却が終了する前の売却は、税金面・価格面の両方でメリットがあります。
売主にとって「減価償却費」は、不動産所得を計算するうえで税負担を軽減する重要な経費です。
しかし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められた法定耐用年数が経過し、減価償却が終了すると、この費用を経費として計上できなくなります。その結果、帳簿上の利益が増加し、所得税や住民税の負担が重くなる可能性があります。
購入希望者も同様に、所得税法上の節税効果を考慮して投資判断を行います。
減価償却が残っていない物件は、購入後の節税効果がほとんど見込めないため、投資対象としての魅力が大きく低下します。
減価償却の終了は、売主・買主双方の税務メリットを失わせるため、市場での需要低下や価格交渉での不利につながる可能性があります。資産価値を最大限に活かすためにも、減価償却が終了する直前が売却の好機といえるでしょう。
築年数が20年以内であるうちも、売却の好機です。築20年を超えると、以下のような問題が発生する可能性があります。
これは、木造アパートの法定耐用年数が22年と定められており、金融機関が築年数を差し引いた「残存耐用年数」を融資期間の上限とすることが一般的であるためです。
たとえば、築20年の木造アパートの場合、残存耐用年数は2年しかありません。そのため、長期融資が難しくなり、買主は現金で購入できる投資家に限定されてしまいます。
築浅物件は融資を受けやすく需要も高いため、早期売却が有利です。
一棟アパートを長く所有していると、屋根や外壁、給排水設備などの大規模修繕が必要になります。大規模修繕には数百万円単位の費用がかかる場合もあるため、オーナーにとって大きな負担です。
そのため、修繕の必要性が出てくる前に売却を検討すれば、大規模修繕に伴う高額な出費を回避できます。
また、買主側が修繕を前提に価格交渉を行うケースもあり、現状のままでの売却のほうが結果的に得になる場合もあります。
国土交通省の「長期修繕計画標準様式 長期修繕計画作成ガイドライン」では、大規模修繕は以下のタイミングで実施するのが目安とされています。
今後の維持費が増えるタイミングこそ、売却を検討すべき時期といえます。
一棟アパートの空室率が高くなり、家賃収入が減って収支が悪化してきた場合は、早期に売却を検討することが重要です。
エリアの需要が低下していたり、築年数の経過によって競争力が落ちていたりすると、空室が埋まらず収益が回復しない可能性があります。
そのまま保有し続ければ、管理費や修繕費、固定資産税などの支出がかさみ、損失が膨らむリスクもあります。
空室率が高く家賃収入が減って収支が悪化した状態での長期保有は、投資効率を悪化させるため、再生が難しいと判断した段階での「見切り売却」が、損失を最小限に抑える賢明な判断です。
一棟アパートを売却する時の相場は、一般的に数千万円から数億円程度が目安です。ただし、立地や規模、築年数などによって大きく異なるため、「この金額が相場」といった明確な基準はありません。
同じ広さの物件でも、東京都内の駅近物件と地方都市の物件とでは、価格差が数倍以上になることも珍しくありません。
実際に、国土交通省が公表する「地価公示」を見ると、東京23区と地方都市では土地価格に数倍から数十倍の差があります。
建物価格を加味しても、大きな価格差が生じています。
売却相場を把握するには、以下の方法があります。
ただし、これらのデータは過去の事例や指標に基づくものです。物件ごとの個別要素(管理状態、入居率、修繕履歴など)を反映した「現在の」査定価格を知るには、不動産会社による査定を受けるのが良いでしょう。
一棟アパートの売却価格は、「物件自体の条件」と「周辺の市場環境」という2つの大きな要素によって決まります。特に以下の5つのポイントは、価格に大きな影響を与えます。
| 売却価格に影響する要素 | ポイント |
|---|---|
| 立地 (駅距離・都市か地方か) |
駅に近く、人口が多い都市部ほど賃貸需要が高く、売却価格も上がりやすい |
| 築年数・構造 | 築浅であるほど資産価値が高く、RC(鉄筋コンクリート)構造は耐久性が高いため評価されやすい |
| 入居率・家賃収入 | 満室に近い状態や安定した家賃収入がある物件は、投資先として魅力があるため、高値で売れやすい |
| 管理状態・修繕履歴 | 適切な管理がされておらず、修繕履歴がないと、買主は将来的な修繕リスクを懸念して価格が下がる可能性がある |
| 法規制
(建ぺい率・容積率など) |
将来的な増築や再建築が可能な物件は価値が高まりやすい |
※参考:不動産鑑定評価基準
売却価格に影響する要素を把握し、自身の物件がどの位置にあるのかを理解しておくことが、適正価格での売却につながります。
一棟アパートの売却価格は、次の3つの評価方法で算出されます。
| 評価方法 | 算出方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 収益還元法 | 年間家賃収入 ÷ 利回り | 年間の家賃収入を基準に価格を出す方法。アパートなどの収益物件でよく使われる。 |
| 原価法 | 建物の再調達価格-減価償却+土地価格 | 建物を新築する場合の費用から、築年数による価値下落分を引いて価格を出す方法。築浅物件に適している。 |
| 取引事例比較法 | 類似物件の過去取引から相場を推定 | 近隣で実際に売買された類似物件の価格を参考にして、立地や条件を補正しながら算出する方法。 |
参照元:不動産鑑定評価基準
これらの評価方法は、不動産鑑定士が行う鑑定評価や、不動産会社が行う価格査定の基準となる「不動産鑑定評価基準」に基づいて使用するもので、精度の高い価格査定を行う際の基礎になります。
| 税金の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 売却益にかかる税金(譲渡所得税) | アパートを売って利益が出たときにかかる税金。持っていた年数によって税率が変わる。 |
| 建物の売却にかかる消費税 | 建物部分だけにかかる税金。
個人の売主や免税事業者は課税されない。 |
| 印紙税 | 売買契約書を作るときにかかる税金。
金額に応じて、決まった額の印紙を貼って払う。 |
| 登録免許税 | 所有者を変更するときの登記でかかる税金。
一棟アパートの売却では、所有権移転と抵当権抹消の登記が必要になり、それぞれに税金がかかる。 |
一棟アパートの売却時には、以上の4つの税金が発生する可能性があります。この章では、手取り額に直結するこれらの税金について説明します。
一棟アパートを売却して利益が出た場合、その利益には「譲渡所得税」が課されます。
売却益は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出されます。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として以下の税率が適用されます。
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
一棟アパートを売却する時、建物部分には消費税がかかる場合があります。ただし、個人の売主や免税事業者であれば、消費税は課税されません。
一方、売主が課税事業者である場合は、建物の価格に対して消費税(原則10%)が課税されます。なお、土地部分の売却は非課税です。
一棟アパートを売却する際に作成する売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が課されます。印紙税は国税の一種で、契約書に収入印紙を貼って納付します。
たとえば、契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下なら印紙税は2万円、5,000万円超〜1億円以下なら6万円が必要です。
| 記載された契約金額 | 印紙税額 (1通または1冊につき) |
|---|---|
| 1万円未満(※) | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
登録免許税は、不動産の所有権などを法務局の登記簿に記録する「登記」手続きの際に課される国税です。一棟アパートを売却する際には、主に「所有権移転登記」と、売主がローンを利用していた場合の「抵当権抹消登記」が必要になります。
| 所有権移転登記 | 土地 | 固定資産税評価額×1.5%(2.0%※) |
|---|---|---|
| 建物 | 固定資産税評価額×2.0% | |
| 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1,000円 | |
※本来の税率は2.0%ですが租税特別措置法により2027年3月31日まで軽減税率が適用されます
法律で決まっているわけではありませんが、買主名義にするための所有権移転登記の費用は「買主」、売却の前提となる抵当権抹消登記の費用は「売主」が負担するのが一般的な取引慣行です。
ただし、最終的には売買契約書の内容が優先されるため、事前にしっかりと確認することが重要です。
| 費用項目 | 特徴 |
|---|---|
| 不動産会社に支払う仲介手数料 | アパートの買い手を見つけてくれたお礼として、不動産会社に払う成功報酬。法律で上限が決まっている。 |
| 仲介手数料以外の諸費用 | 所有者の変更に必要な登記や、土地の境界線を調べるための費用など。物件によって内容や金額が変わる。 |
この章では、一棟アパートを売却する時にかかるこれらの費用についてわかりやすく解説します。
不動産会社を通して一棟アパートを売却した場合、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条などで上限が定められています。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 取引価格(税抜)×5% |
| 200万円超~400万円以下 | 取引価格(税抜)×4%+2万円 |
| 400万円超 | 取引価格(税抜)×3%+6万円 |
法律で定められているのはあくまで「上限」であるため、不動産会社との合意によっては、この金額より低くなる可能性もあります。実際に支払う手数料は、不動産会社との媒介契約締結前に確認しておきましょう。
一棟アパートの売却では、仲介手数料以外にもさまざまな費用が発生します。
主な費用には、以下のようなものがあります。
これらの金額は物件の状況や必要書類の有無によって変動します。追加費用が発生するケースもあるため、事前に把握しておくと安心です。
一棟アパートを売却する際にローンの残債がある場合は、売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権が残ったままでは買主が登記できず、取引が成立しません。
売却金額がローン残高を上回るケースでは、売却代金から完済できるため問題はありません。しかし、売却金額がローンを下回ると「オーバーローン」となり、対応が必要です。
オーバーローン時には、以下のいずれかで対処します。
任意売却では、金融機関の同意を得たうえで、残債を抱えたまま売却が可能になります。ただし、信用情報に影響が出る可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。
この章では、一棟アパートを売却する際の基本的な流れについて説明します。
まずは、収支やローン残高、過去の修繕履歴など、物件の状況を正確に把握することが大切です。
次に、複数の不動産会社へ査定を依頼し、相場を比較しましょう。媒介契約は種類により営業スタイルが異なるため、自身の売却方針に合った契約を選ぶことが重要です。
販売活動が始まれば、写真撮影や内見対応にも協力する必要があります。買主が見つかれば契約を締結し、ローンが残っていればその清算と抵当権抹消の手続きを行います。
最終的に残代金を受け取り、物件を引き渡せば売却は完了です。
一棟アパートの売却は、事前の準備次第で結果に大きな差が出ます。この章では、売却を成功させるための3つのポイントを紹介します。
一棟アパートの売却を成功させるには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
まずは複数社に査定を依頼し、査定額だけでなく、その算出根拠や具体的な販売戦略を比較検討しましょう。単に高値を提示する会社よりも、周辺の取引事例や収益性(利回り)に基づいた根拠ある提案をしてくれる会社が信頼できるでしょう。特に、一棟アパートのような投資用不動産の売買実績が豊富かどうかも、会社選びの重要な判断基準となります。
また、不動産会社と締結する媒介契約の種類にも注意が必要です。媒介契約の種類は以下の3つがあり、それぞれ特徴が異なります。
| 契約の種類 | 複数社との契約 | レインズへの登録義務 | 売主への業務報告義務 | 自己発見取引の可否 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 可能 | なし(任意) | なし(任意) | 可能 |
| 専任媒介契約 | 不可(1社のみ) | 7日以内 | 2週間に1回以上 | 可能 |
| 専属専任媒介契約 | 不可(1社のみ) | 5日以内 | 1週間に1回以上 | 不可 |
参考:宅地建物取引業法
「専任」や「専属専任」は1社に任せる分、不動産会社側の情報公開(レインズ登録)や売主への報告義務が重く、積極的な販売活動が期待できます。売却方針に合った契約を選ぶことが、スムーズで有利な売却につながるでしょう。
買主に物件の魅力を感じてもらうには、収益性や管理状況などを丁寧に伝えることが重要です。物件の価値が明確に伝わると、検討段階での信頼感にもつながります。
たとえば以下のような情報は、購入判断に大きく影響します。
共用部分の清掃や定期点検の実施状況も、好印象を与えるポイントです。これらの情報を資料にまとめておくと、売却活動をスムーズに進めやすくなります。
投資用不動産である一棟アパートの売却で税負担を軽減できる特例は、非常に限定的ですが、主に2つあります。
一つ目は、所有期間に応じた特例で、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているか、いないかで、税率に大きな差が出ます。
| 区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
二つ目は、他の事業用資産に買い換えることで適用できる可能性がある「事業用資産の買換え特例」で、一定要件のもとで売却益への課税を将来に繰り延べる制度です。
たとえば、売却額以上の資産に買い換えた場合、売却益の原則80%について課税繰延べが認められます。
この特例を活用すれば、売却時の税負担を抑え、手元資金を効率的に次の投資へ回すことが可能です。ただし、適用要件が複雑なため、詳細は国税庁のウェブサイトで確認し、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
現在のアパートの状況を自己診断し、売却・保有どちらがおすすめかをチェックしてみましょう。
一棟アパートの売却を成功させるには、タイミング・価格設定・準備の3つが重要です。所有期間が5年を超えたタイミングや、減価償却が終了する前、大規模修繕の前などは売り時の目安となります。また、築年数や空室率、収支の状況を総合的に判断し、保有継続か売却かを判断しましょう。
相場はエリア・構造・収益性によって大きく異なります。利回りや類似物件との比較、土地の公示価格などを参考にしながら価格設定を行いましょう。
売却を成功させるには、信頼できる不動産会社の選定や、正確な情報開示(収支・修繕履歴など)、控除や特例を活用することが大切です。売るべきか悩む場合は、まず一括査定サービスで相場を把握し、専門家に相談してみることをおすすめします。
