
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
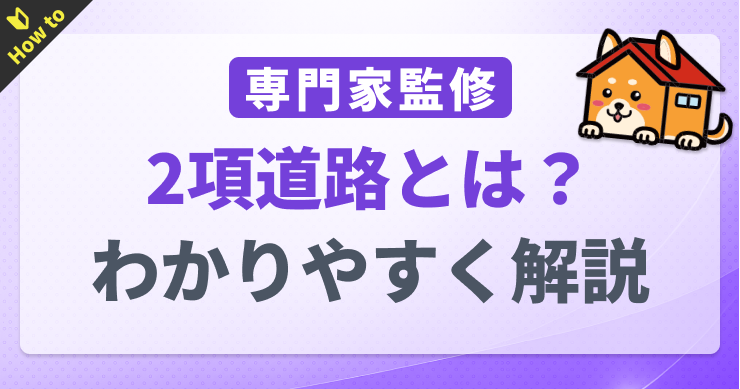
不動産会社から「2項道路に面しています」と言われて、どういう意味かわからず戸惑っていませんか?。
不動産に関する用語は難解なものが多く、建て替えや資産価値にどう影響するのかご不安ですよね。でもご安心ください。「2項道路」は、基本的なポイントを押さえることで、リスクを正しく理解し、適切に対処することが可能です。
この記事を読めば、不動産会社の説明にも自信を持って対応できるようになるでしょう。
【この記事でわかること】
「2項道路(みなし道路)」とは、法律上の道路と見なされる道のことです。
大前提として、建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路」に「2m以上」接していなければならない、というルールがあります。これを「接道義務」と呼びます。
しかし、昔からある住宅街の道には、幅が4mに満たないものもたくさんありますよね。もしこのルールを厳格に適用すると、そうした道に面した土地には家が建てられないことになってしまいます。
そこで、一定の条件を満たした幅4m未満の道も「法律上の道路とみなしましょう」という、いわば救済措置が設けられました。これが「2項道路」、通称「みなし道路」です。
では、なぜ道路には「幅4m」という基準が設けられているのでしょうか。
これは、万が一の火災や急病の際に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行できるようにするためです。道が狭いと、消火活動や救命活動が遅れてしまう可能性があります。
つまり、接道義務や2項道路の規定は、安全な暮らしを守るために非常に重要な役割を果たしているのです。
| 目的 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 緊急車両の通行確保 | 消防車や救急車が迅速に現場に到着するため |
| 安全な避難経路の確保 | 地震や火災の際に、住民が安全に避難するため |
| 日照・通風の確保 | 建物が密集しすぎるのを防ぎ、良好な住環境を維持するため |
この2項道路の根拠となっているのが、「建築基準法 第42条2項」です。
建築基準法第42条2項によれば、特定行政庁(市役所など)が指定した道は、幅が4m未満であっても建築基準法上の道路とみなすと定められています。
この記事では、この法律があなたの土地にどう関係するのか、一つひとつ丁寧に解説していきます。
2項道路に面した土地で最も重要なポイントが「セットバック」です。
セットバックとは、日本語で「後退」を意味します。具体的には、道路の中心線から2mのラインまで、自分の敷地を後退させることを指します。
まず安心していただきたいのは、セットバックは「今すぐ」行わなければならないものではないということです。義務が発生するのは、その土地に建っている家を「将来、建て替える時」です。
つまり、中古住宅を購入してそのまま住み続ける分には、すぐに敷地が狭くなるわけではありません。
セットバックには、主に2つのパターンがあります。ご自身の状況がどちらに当てはまるか、確認してみましょう。
最も一般的なケースです。この場合、道路の中心線から水平に2m後退した線が、道路と敷地の境界線とみなされます。
たとえば、現在の道路の幅が3mだったとすると、中心線から自分の敷地側へ1.5mの位置が中心です。そこから2m後退する必要があるため、セットバックする距離は 2m – 1.5m = 0.5m となります。
この場合は、向かい側の境界線を動かすことができません。
そのため、川や崖などの境界線から、水平に4m後退した線が、道路と敷地の境界線とみなされます。
たとえば、現在の道路の幅が3mだとすると、セットバックする距離は 4m – 3m = 1mとなり、①のケースより後退する幅が大きくなるので注意が必要です。
「セットバックした土地は誰のものになるの?」というご質問もよくいただきます。
結論から言うと、セットバックした部分の土地の所有権は、あなたのままです。しかし、その部分は建築基準法上の「道路」として扱われるため、以下のような利用の制限を受けます。
つまり、所有権はあっても、実質的には「公衆用道路」として提供する土地、と理解しておくのが良いでしょう。
2項道路の主なデメリットは、以下の通りです。
この章では、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
2項道路に面する土地の最大のデメリットは、将来建て替える際に、家を建てられる有効な土地の面積が減ってしまうことです。
建ぺい率や容積率(敷地面積に対する建築面積・延床面積の割合)は、セットバック後の敷地面積を基準に計算されます。
そのため、「今建っている家と同じ大きさの家を建てようとしたら、面積が足りなくて建てられなかった…」という事態も起こり得ます。これは購入前に必ず理解しておくべき最も重要なポイントです。
検討している土地が2項道路に面した「角地」である場合は、セットバックに加えて「隅切り(すみきり)」が必要になるケースがほとんどです。
隅切りとは、角の部分を三角形に切り取り、道路として使えるようにすることです。これは、自動車がスムーズに曲がれるようにし、見通しを良くして交通事故を防ぐ目的があります。
この隅切り部分も、セットバック部分と同様に敷地面積から除外されるため、さらに有効宅地面積が小さくなる点に注意が必要です。
セットバックが必要な土地は、不動産としての評価において、いくつかの点で不利に働く可能性があります。
| 影響を受ける側面 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 資産価値 | セットバックで有効宅地面積が減る分、近隣の同じ面積の土地と比べて、資産価値は低く評価される傾向にあります。 |
| 担保評価 | 住宅ローンを組む際、銀行などの金融機関は土地を担保に融資を行いますが、その際の担保評価額が低くなる可能性があります。 |
| 売却のしやすさ | 将来、土地を売却しようとする際に、2項道路のデメリットを敬遠する買主もいるため、売却に時間がかかるケースも考えられます。 |
もちろん、立地や周辺環境など他の要素も大きく影響しますが、こうしたデメリットがあることは認識しておきましょう。
セットバック部分については、自治体に届け出をしない限り、宅地の一部として通常どおり課税されてしまう点にも注意が必要です。
自治体に申告することで、固定資産税の非課税や減額の対象となる可能性があります。ただし、この制度は所有者からの申告が前提であり、届け出をしないままでいると、私有地として課税され続けます。
また、塀・門・フェンスなどがあると「私的に使用している」と見なされ、非課税対象から外れるリスクもあります。
これにより、将来的に課税されることはなくなりますが、一度寄付した土地は原則として再取得できないため、慎重に判断する必要があります。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
この章では、ご自身の土地が2項道路に面しているかどうかを、市役所や区役所で確認する具体的な手順について解説していきます。この確認を怠ると、将来大きな損につながってしまう可能性があるので注意しましょう。
ご自身の土地が2項道路に面しているかどうかを調べるには、不動産会社の資料を見るだけでなく、必ずご自身で「特定行政庁」の窓口で確認することが重要です。
「特定行政庁」というと難しく聞こえますが、基本的には市役所や区役所のことです。
まずは、市役所(区役所)の「建築指導課」「建築審査課」「道路管理課」といった名称の部署を探してみましょう。建築に関する相談窓口であれば、担当部署を案内してもらえます。
窓口に着いたら、職員の方に「前面道路が建築基準法上の道路かどうか調べたい」と伝えてください。
そうすると、「道路査定図(どうろさていず)」や「指定道路図(していどうろず)」といった地図を見せてくれます。(※自治体によって書類の名称は異なります)
これらの図面には、どの道が建築基準法上の道路で、どの種別に該当するかが色分けなどで示されています。ここで、該当する道路が「42条2項道路」と記載されているかどうかを確認します。
図面を見てもよくわからない場合や、より正確な情報を得るためには、窓口の担当者に直接質問するのが一番です。その際に、以下の3つの質問をすると、必要な情報を漏れなく確認できます。
この3点を質問すれば、担当者の方も的確に答えてくれるはずです。メモと、該当地点の地図を持参していきましょう。また、窓口であらかじめ詳しい担当者がいるか確認しておくとスムーズです。
監修者からの一言アドバイス
不動産売買において、道路に関する情報は必ず「今、この瞬間」の一次情報を自分自身の目で確認してください。不動産会社の資料や過去の書類を鵜呑みにすると、後で建て替えができないなどの致命的な問題が発覚することがあります。
A. 自治体によりますが、セットバックによって「公衆用道路」として利用されている部分は、固定資産税が非課税の対象となる場合があります。
これは自動的に減額されるわけではなく、ご自身で「固定資産税(非課税)申告書」といった書類を、お住まいの市町村の資産税課に提出する必要があります。セットバックが完了したら、必ず手続きについて問い合わせてみましょう。
A. セットバック部分は建築基準法上の「道路」とみなされるため、たとえ所有権が自分にあっても、通行の妨げになるような利用は認められません。
具体的には、以下のような行為は禁止されています。
A. セットバックの義務は「新たに建築(建て替え含む)する際」に発生します。
そのため、昔から建っているお隣の家などが後退していなくても、それは違反建築というわけではありません。ご自身の土地を建て替える際に、ご自身の敷地だけをルールに従って後退させることになります。
今回は、専門用語が多くて分かりにくい「2項道路」について、その基本から具体的な調査手順まで解説しました。
この記事のキーポイント
2項道路は、有効宅地面積が減るなどのデメリットは確かにありますが、その本質は、そこに住む人々の安全を守るための大切なルールです。
不動産会社の言葉だけに頼らず、ぜひこの記事を参考に、ご自身で役所での確認という「行動」を起こしてみてください。リスクとメリットを正確に天秤にかけ、納得のいく不動産購入ができることを心から応援しています。
