
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
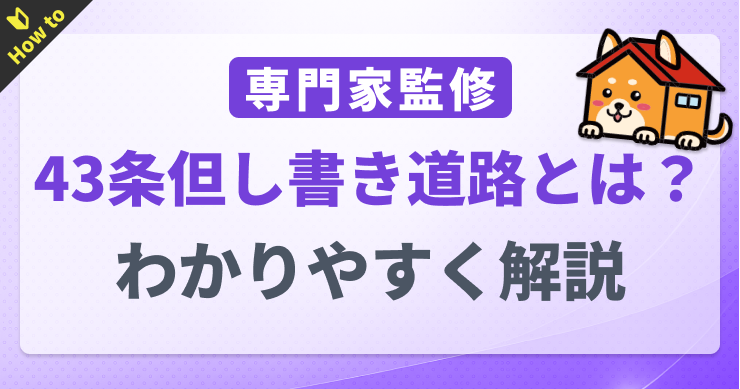
相場よりも安い土地を見つけたものの、不動産会社から「この土地は43条但し書き道路に接しています」と説明され、困惑していませんか?
一体どのようなリスクがあるのか、本当に家を建てて大丈夫なのか、不安に感じている方も多いでしょう。
結論から言うと、建築基準法上の「道路」に2m以上接していないと、原則として建物の再建築ができません。しかし、特定行政庁から特例の許可(いわゆる43条但し書き許可)を得ることで、再建築が可能になる道が残されています。
この記事では、「43条但し書き道路」の基本的な意味から、再建築の可否までわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
「43条但し書き道路」を理解するには、まず、なぜ建物は道路に接していなければならないのか、という大原則を知る必要があります。それが建築基準法に定められた「接道義務」です。
「接道義務」とは、「建物を建てる敷地は、建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない」というルールのことです。なぜこのような義務があるかというと、火災や地震などの災害時に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに進入し、人々が安全に避難できる経路を確保するためです。
| 項目 | 規定内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 接道義務 | 建物を建てる敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接すること | 消防活動・救急活動・避難経路の確保 |
| 対象道路 | 建築基準法第42条で定義された道路(国道、県道、位置指定道路など) | 公的な安全性が担保された道路 |
この「建築基準法上の道路」に接していない、または接している間口が2m未満の土地は、接道義務違反となり、原則として新しい建物を建てたり、再建築することができません。
では、「43条但し書き道路」とは何でしょうか。これは、接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件をクリアすれば、建築審査会の同意を得た上で特定行政庁(市長や都道府県知事)が「例外的に建築を許可する」という道を開くための規定です。
つまり、43条但し書き道路は、法が定める正式な「道路」ではありません。あくまで、建築を許可するための特例措置が適用される「通路」や「空地」といった位置づけになります。このため、許可を得るためには、その通路が安全上問題ないことを証明する、厳格な審査が必要となるのです。
43条但し書き道路に面した土地で再建築の許可を得る鍵は「特定行政庁」と「建築審査会」にあります。自治体ごとに定められた「包括同意基準」を満たすか、個別に安全性を証明し「個別審査」を通過する必要があります。
許可のプロセスには、2つの重要な組織が関わっています。
申請者が特定行政庁に許可を申請し、特定行政庁がその案件を建築審査会に諮り、審査会が同意すれば、特定行政庁が正式に許可を出す、という流れになります。
許可の基準には、大きく分けて2つの種類があります。
| 基準の種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 包括同意基準 | 頻繁に申請されるケースについて、あらかじめ建築審査会が定めておいた画一的な基準。 | この基準に適合すれば、比較的スムーズに許可が得られる可能性が高い。 |
| 個別審査基準 | 包括同意基準に当てはまらない、特殊なケースを個別に審査するための基準。 | 敷地の状況や安全性を詳細に説明し、審査会の同意を得る必要があるため、難易度が高くなる。 |
まずは、その土地が所在する自治体の「包括同意基準」を確認することが第一歩です。たとえば、「幅員4m以上の通路状の接道義務を満たした空地に2m以上接している」といった基準が定められています。
実際に再建築の許可を得られるかどうかを調べるには、以下のステップで進めるのが確実です。
【筆者からの一言アドバイス
不動産会社の説明を鵜呑みにせず、必ずご自身で役所の窓口に足を運んでください。役所の担当者は、公平な立場で法的な見解や過去の実績を教えてくれます。この「一次情報」にあたることが、リスクを回避する上で何よりも重要なのです。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
43条但し書き道路の物件は、価格が安いというメリットがある一方、それを上回る可能性のある重大なリスクを抱えています。ここでは、特に注意すべき3つのリスクを解説します。
最大のデメリットは、再建築が100%保証されているわけではないことです。
金融機関は、融資の担保となる不動産の資産価値を厳しく評価します。43条但し書き道路の物件は、この点で大きなハンデを負います。
| 銀行が融資に慎重になる理由 |
|---|
| 担保価値が低い:再建築ができない可能性がある不動産は、担保としての評価が著しく低くなります。 |
| 換金性が低い:債務者がローンを返済できなくなった場合、銀行が物件を差し押さえて売却しようとしても、買い手がつきにくいため、現金化が困難です。 |
このため、住宅ローンの利用を断られたり、利用できても融資額が少なくなったり、金利が高くなったりするケースが一般的です。購入を検討する場合は、現金での購入か、融資に強い金融機関を探す必要があります。
将来その物件を売却しようとする際にも、大きな困難が伴います。
このセクションのポイント
この章では、43条但し書き道路に関してよくある疑問についてお答えします。
これは非常に重要な違いです。簡単に言うと、42条道路は建築基準法が認めた正式な「道路」ですが、43条但し書き道路は正式な道路ではなく、あくまで特例許可の対象となる「通路」です。
| 項目 | 42条道路 | 43条但し書き道路(通路) |
|---|---|---|
| 法的性質 | 建築基準法上の道路 | 建築基準法上の道路ではない |
| 再建築 | 原則として可能 | 原則として不可(特例許可が必要) |
| 資産価値 | 正常な評価 | 低く評価される傾向 |
不動産の重要事項説明書には、接している道がどの条文に該当するかが明記されているので、必ず確認しましょう。
前述の通り、許可はその時の建築行為に対して一度だけ有効です。将来、増改築や再建築を行う場合は、最新の法令や状況に基づいて再度申請し、改めて許可を得る必要があります。
役所に申請する手数料自体は数万円程度ですが、それ以外に、測量費用や、建築士に代理申請を依頼するための設計・コンサルティング費用などが別途数十万円以上かかることが一般的です。
この記事では、43条但し書き道路という複雑な不動産の特性について、その基本からリスク、調査方法までを解説しました。
この記事の重要なポイント
43条但し書き道路に面した物件は、安い価格が魅力的である一方、その裏には大きなリスクが潜んでいます。安易に「再建築可能」という言葉を信じるのではなく、その根拠は何か、どのような手続きが必要で、将来にわたってどのような制約があるのかを徹底的に調査・理解することが極めて重要です。
もしあなたがこのような物件の購入を検討しているなら、まずは信頼できる不動産の専門家に相談し、役所調査に同行してもらうなど、慎重に検討を進めることを強くおすすめします。
