
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
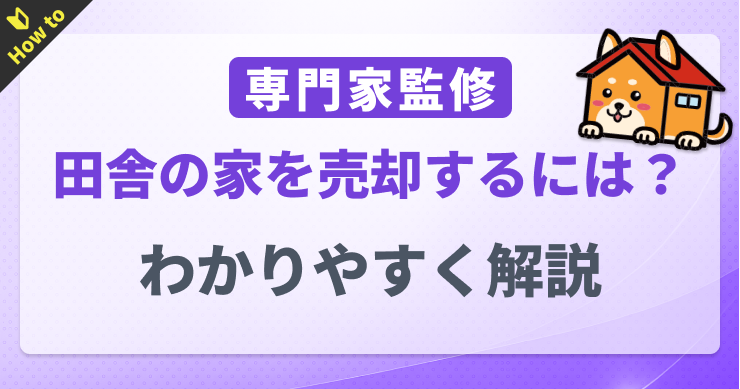
田舎にある家を売却しようと思っても、「なかなか売れない」「どこに相談すればいいのかわからない」と悩む方は少なくありません。
実際に、老朽化や過疎化、依頼できる不動産会社の少なさなど、都市部とは異なる事情により、売却が難しいケースは多くあります。
しかし、地域に強い不動産会社の選定や、適正な価格設定、最低限のリフォームといった工夫をすれば、田舎の家でも売れる可能性は十分にあります。それでも売れない場合には、更地化、不動産会社による買取、自治体や国への寄付といった選択肢もあります。
この記事では、田舎の家を売却したいと考えている方に向けて、売れにくい理由や、売却を成功させるための方法、売れない場合の対処法や注意点まで、わかりやすく解説します。
田舎の家は、以下のような理由から売却しにくいと言われています。
この章では、田舎の家が売却しにくい理由を、さらに詳しく解説します。
田舎の家が売却しにくい大きな理由のひとつが、その地域に買い手が少ないことです。
人口減少や過疎化が進むエリアでは、移住希望者や住み替えニーズが限られます。買い物や医療機関へのアクセスが悪いと、定住を敬遠されやすく、学校や職場が近くにない地域は、子育て世代や現役世代にも選ばれにくくなります。
国土交通省の住宅市場動向調査によると、既存(中古)戸建住宅取得世帯が住宅を選ぶ際の理由として、価格や建物の種類に次いで「住宅の立地環境が良かったから」と答えた割合が36.5%と高く、「交通の利便性が良かったから」と答えた割合も24.1%となっています。(P.203「(3) 住宅の選択理由」より)
地方では、交通の便が悪い、周辺施設が少ないなどの理由から、そもそも住みたいと考える人が少ないエリアも多く、賃貸需要が伸び悩む傾向にあります。そのため、賃貸物件を用意しても入居者がなかなか見つからないケースも珍しくありません。
さらに、地方の家賃相場は都市部よりも大幅に低く、投資額を回収するまでに長い年月を要することになります。総務省の住宅・土地統計調査を見ると、1ヶ月当たりの家賃が最も高い東京都が81,001円、最も安い鹿児島県が37,863円と、約2倍以上の差があります。(P.11「都道府県別の主な指標」より)
また、サブリースや民泊といった活用方法も、地域の条例や住民の反対によって制限を受ける場合があり、思うような運用ができない場合もあります。
田舎の家は築年数が古く、老朽化が進んでいることも売却を難しくする理由です。
特に1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅は、現在の安全基準を満たしておらず、資産価値が著しく低く評価されます。そのため、購入後に耐震補強や大規模な修繕が必要になるケースが多く、費用負担を懸念した買い手から敬遠されやすい傾向があります。
エリアによっては、対応可能な不動産会社が限られている場合もあります。
地方では、大手不動産会社の支店が少ないため、都市部と比べて選択肢が大幅に限られます。また、地元の中小規模の不動産会社はインターネットを活用した集客や広域的な販売活動が不得手なケースがあり、物件が買い手の目に触れる機会が少なくなりがちです。
国土交通省の統計を見ると、都市部と地方では宅建業者数に明確な差があることがわかります。(P.2「宅地建物取引業者数①(本店所在地別集計)」より)
田舎の家は物件価格が安いため、一見するとお得に感じられますが、購入後には想定以上の維持費がかかる場合があります。
固定資産税や火災保険料に加えて、草刈りや雪かき、老朽化に伴う修繕費など、定期的な管理コストが必要です。特に空き家の状態が続くと建物の劣化が進み、シロアリ被害や雨漏りなどのトラブルが発生しやすくなります。
居住予定がなくても、年に数回の現地確認や管理委託が求められることもあり、実際の所有負担は決して軽くありません。空き家対策特別措置法では、管理が不十分な空き家に対して固定資産税の軽減措置を解除するなどの課税強化もされています。
この章では、こうした課題を解消しながら売却を成功させるための4つのポイントについて解説します。
田舎で家を売却するなら、地元での売却実績が豊富な不動産会社を選びましょう。
地域に精通した業者であれば、その土地ならではの買い手のニーズや適正な価格帯を把握しており、現実的な売却戦略を立ててくれます。地価の相場感や交通アクセスの評価、地域の特徴など、田舎特有の事情に対応できることがポイントです。
また、地元に根ざしたネットワークを持つ業者なら購入希望者との接点も多く、成約までのスピードも期待できます。
不動産会社の選択肢が限られている中でも、経験と実績を見極めて信頼できる業者に依頼することが売却成功への第一歩となります。
相場とかけ離れた価格設定を避けることも成功のポイントです。
不動産会社の査定額に加えて、「地価公示」や「固定資産税評価額」、近隣の成約実績といった公的データを確認しましょう。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、不動産の取引価格や地価公示などを確認できます。
また、建物の老朽化や維持管理にかかるコストも価格に反映する必要があります。価格が高すぎれば買い手がつかず、売れ残るリスクが生じます。一方で、価格が安すぎると本来得られる利益を逃してしまいます。重要なのは、なぜその価格なのかという根拠を明確にすることです。
現実的かつ戦略的な価格設定を行うことで、売却成功の可能性が高まります。
必ずしも大規模なリノベーションが必要というわけではありませんが、最低限のリフォームで第一印象を改善することは、売却成功の鍵になります。
特に効果的なのが、水回り(キッチン・浴室・トイレ)や外観の整備です。これらは購入希望者のチェックが厳しく、「そのまま住めそう」と感じてもらえるポイントとなります。
また、最近では古民家を自分好みに改装したいという若年層や移住希望者からの「古民家リノベーション需要」も増えており、一定の手入れをすることで関心を引きやすくなるでしょう。
手頃なコストでの部分的なリフォームが、売却の後押しとなります。
物件そのものの情報だけでなく、地域全体の魅力をあわせてアピールすることも重要です。
たとえば、豊かな自然環境や静かで落ち着いた暮らしなど、都会では得られない価値を言葉で伝えることで、移住希望者やスローライフを求める人の心を引きつけやすくなります。
また、自治体によっては移住支援金や住宅取得補助制度もあり、これらの情報を買い手に紹介するのも効果的です。
加えて、生活費や家賃、水道光熱費などのコストが都市部に比べて安いことも強みになります。
購入希望者が「ここに住むメリット」を具体的にイメージできるように工夫しましょう。
| 対処法 | 特徴 |
| 不動産会社に買取を依頼する | ・不動産会社による直接買取
・とにかく早く処分したい人におすすめ |
| 更地にして売却する | ・家を解体して土地だけで売る ・土地だけで売った方が価値がある場合におすすめ |
| 自治体への寄付や国への返還 | ・家や土地を無料で手放すことが可能
・誰にも売れず、放置もできない場合におすすめ |
田舎の家が売れない時には、状況に合わせた対処法を選ぶことが重要です。ここでは、3つの対策を紹介します。
通常の仲介売却ではなく、不動産会社による「直接買取」も一つの方法です。直接買取は、不動産会社が買い手を探すのではなく、物件をそのまま買い取ってくれる仕組みです。
最大のメリットは、売却活動を行う必要がなく、短期間で現金化できる点です。また、面倒な残置物の処分や清掃も不動産会社に任せられるケースが多く、手間がかかりません。
ただし、、買取価格は市場相場の2割〜3割ほど安くなることが一般的です。加えて、建物の状態が悪ければ、さらに安く買取されることも想定されます。高値で売ることを重視したい場合には、注意が必要です。
築年数が古く老朽化が進んだ家は、建物を解体し更地で売却するという選択肢もあります。
更地にすれば、住宅用地に限らず駐車場や資材置き場など用途が広がり、買い手が見つかりやすくなるでしょう。特に「家付き土地」よりも「土地のみ」を求める人には、建物解体の手間や費用が省けるため魅力的に映る可能性があります。
ただし、建物を解体すると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるので、税額が約6倍程度に増加することがあります。(地方税法第349条の3の2)
また、木造家屋の解体費用は、構造や立地などにもよりますが、一般的に100万円~300万円程度が必要です。
解体費用も含め、売却後の収支を十分にシミュレーションしてから判断してください。
田舎の家や土地をどうしても売却できない場合、「寄付」や「国への返還」も可能です。
自治体への寄付は、地域活性化や公共利用などの目的がある場合に限り、受け入れられることがありますが、使い道のない空き家は基本的に受け取りを断られます。
一方、2023年に施行された「相続土地国庫帰属法」では、一定の条件を満たせば相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。
管理負担の重い土地を相続したくない人への救済措置ですが、建物付きの土地や管理が難しい土地などは対象外となります。さらに、申請には10年分の土地管理費相当額の負担金(最低でも20万円)を納付する必要があります。
田舎の土地は、相続土地国庫帰属法の要件を満たせないケースが多いため、利用条件を確認しておきましょう。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
相続後空き家になっている田舎の家は、税制優遇を考慮すると3年以内に売却するのがおすすめです。また、放置すると「特定空き家」に認定される恐れがあるので注意しましょう。
この章では、田舎の家を売る時の2つの注意点をわかりやすく解説します。
相続した田舎の空き家を売却する際は、空き家になってから3年以内に売却すると、譲渡所得から最大3,000万円が非課税となる制度を受けられる可能性があります。適用には一定の条件を満たす必要がありますが、適用されれば大きな節税効果が期待できます。
適用期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」です。
たとえば、2025年5月1日に相続が発生した場合、3年を経過する日(2028年5月1日)が属する年、つまり2028年12月31日までが売却の期限となります。
税負担を抑えて売却したい場合は、早めの行動をおすすめします。
空き家を長期間放置していると、「特定空き家」に指定される可能性があるため注意が必要です。
倒壊の危険や著しい景観の悪化など、周囲に悪影響を及ぼす状態にある空き家に該当すると自治体が判断すれば、「特定空き家」と認定され、住宅用地特例が解除され固定資産税が約6倍に上がるリスクがあります。
さらに、特定空き家認定後の行政指導や命令に従わない場合には、行政代執行となるケースもあります。
こうした法的リスクを避けるためにも、空き家は放置せず、早めに売却・処分・管理の対策を講じることが重要です。
田舎の家を売る時の手順は次の3STEPです。各ステップごとにポイントを簡単に説明します。
田舎の家を売却する最初のステップは、買い手を探すことです。
不動産会社に依頼して広告を出したり、不動産ポータルサイトを活用する方法がありますが、その前に物件の現状把握も重要です。特に以下の点を確認しておきましょう。
Point
2024年から相続登記が義務化されています。
他人名義のままだと売却手続きが進まないので注意してください。
買い手が見つかったら、価格や引き渡し時期などの条件を交渉し、双方が合意すれば売買契約を結びます。
売買契約では、宅地建物取引業法に基づいて、宅地建物取引士(宅建士)が物件の権利関係や法的制限などをまとめた「重要事項説明」を行います。その後、契約内容を確認し、売主・買主ともに署名・捺印をして契約が成立します。
Point
後のトラブルを防ぐためにも、条件の確認は慎重に行いましょう。
売買契約後は、残代金の受け取りと同時に鍵を買主へ引き渡し、所有権移転登記を行うことで売却手続きが完了します。
登記が完了すると法的に新しい所有者が確定します。登記手続きは専門的な知識が必要なため、通常は司法書士に依頼して進めるのが一般的です。
Point
登記費用に加えて、司法書士に依頼する場合は報酬などの費用も発生します。
事前に費用感を確認しておきましょう。
チェックリストに「はい」「いいえ」で答えることで、あなたの田舎の家がどの程度売却しやすいかを自己診断できます。売却に向けた改善点の把握にも役立つので、ぜひ活用してみてください。
【診断結果】
「はい」が8個以上売却は比較的スムーズに進む可能性大。地域需要や価格設定を意識すれば、短期間での売却も期待できます。
「はい」が4〜7個条件次第では売却可能。改善できる点を整理し、対策を立てましょう。
「はい」が3個以下 売却は難航するかもしれません。更地化、買取依頼、寄付制度の活用なども視野に入れ、早めに方針を決めましょう。
田舎の家は、都市部と比べて「買い手が見つかりにくい」「賃貸需要が低い」「築年数が古い」などの理由から、「売れない」「売却が難しい」と言われています。
しかし、地域に強い不動産会社の選定や適正価格の設定、最低限のリフォーム、地域の魅力を丁寧に伝える工夫などによって売却成功の可能性は高まります。万が一売れない場合も、不動産会社による買取や更地化、自治体・国への寄付など、対処法は複数あります。
売却を検討する際は、現状をしっかりと把握し、早めに動くことが重要です。この記事を参考に、家の状況を見直して最適な手段を検討していきましょう。
