
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
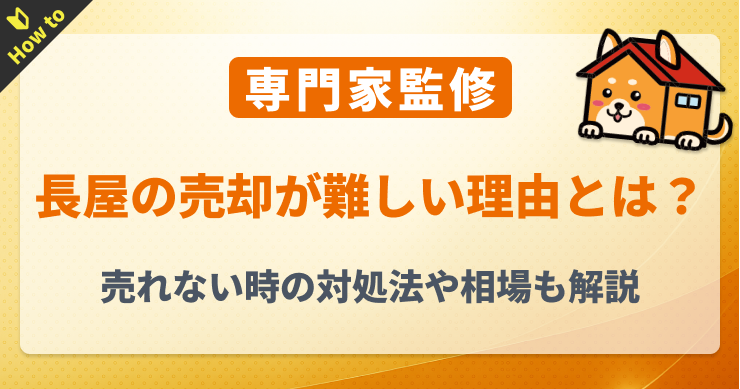
長屋を売りたいと考えている方の中には、「売却が難しく、どう対処すればよいかわからない」と悩む方も少なくありません。
長屋は、構造上、隣家と壁を共有しているため、共同住宅とは異なる法的・物理的な特徴を持つ特殊な物件です。そのため、接道義務を満たしていないケースや、建築基準法上の再建築不可物件に該当することも多く、住宅ローンの審査が通りにくい、共有名義の調整が必要になるなど、売却には複数のハードルがあります。
とはいえ、長屋の売却実績がある不動産会社への相談や、一棟売却への切り替え、隣人への売却、不動産買取業者の活用といった具体的な対処法をとることで、売却を成功に導くことは十分可能です。
本記事では、長屋特有の構造や法的な背景、売却が難しいと言われる理由、対処法、売却相場について詳しく解説します。
長屋とは、日本の伝統的な住宅形式の一つで、隣家と壁を共有しながら横に連なって建てられた戸建て住宅です。
上下階で別世帯が暮らす共同住宅とは異なり、1戸につき1世帯が専有する構造となっています。各戸にはそれぞれ独立した玄関があり、住戸が上下ではなく横方向に連続して配置されているのが特徴です。
また、各住戸が玄関から直接道路や通路に出ることができる構造となっている点も、共同住宅との大きな違いです。こうした理由から、建築基準法上も、建築基準法第2条第2号に規定される「特殊建築物」には該当せず、一戸建て住宅に分類され、「戸建ての集合形態」とされています。
長屋と共同住宅は、見た目が似ていても構造や法的な分類に違いがあります。
長屋は、各住戸が横に連結されて建てられており、住戸ごとに専用の玄関が設けられ、外部から直接出入りできる構造です。
一方、共同住宅はアパートやマンションのように、共用の廊下や階段を通じて各住戸へアクセスする構造で、建物内に複数の世帯が上下に分かれて住む形態が一般的です。
建築基準法上では、長屋は一戸建て住宅(長屋建て)として扱われるのに対し、共同住宅は、一棟の建物を複数の住戸が区分所有する共同住宅(集合住宅)として分類されます。こうした建築基準法上の違いは、建築制限や売却時の取り扱いにも大きく関係してきます。
| 長屋 | 共同住宅
(アパート・マンションなど) |
|
| 構造 | 住戸が横に連なり、壁を共有している | 上下または左右に住戸が配置されている |
| 出入口 | 各住戸に専用玄関があり直接出入りできる | 共用の廊下・階段を通じて各戸に出入りできる |
| 所有形態 | 基本的に戸建てと同様の所有形態 | 一棟建物内の区分所有となることが多い |
| 建築基準法上の分類 | 戸建て住宅
(「長屋建て」として定義) |
共同住宅 (集合住宅) |
テラスハウスと長屋は、見た目やイメージには違いがあるものの、建築基準法上はいずれも「長屋」に分類される構造です。
どちらも、複数の一戸建て住宅が横に連なって建てられた集合住宅で、各戸が専用玄関を持ち、外から直接出入りできる点で共通しています。つまり、構造上は同じ建物形式です。
違いがあるとすれば、その呼ばれ方やデザインの印象です。昔ながらの木造住宅を想起させる長屋に対し、テラスハウスは現代的でスタイリッシュな外観や内装を持つ物件に使われることが多くなっています。
構造的には同じ建物になるため、呼び名や印象で区別されているにすぎません。
この章では、長屋の売却が難しいと言われる主な理由について、わかりやすく解説します。
長屋は、住宅ローンの審査に通りにくいという特徴があります。
住宅ローンでは、購入予定物件が金融機関にとって十分な担保価値を持つかどうかが重視されます。
しかし、長屋は、接道義務を満たしていないケースや、建築基準法上の再建築不可物件に該当することがあり、その結果、評価額が低く見積もられ、融資審査が通りにくくなるのです。
買主が住宅ローンを利用できない場合には現金購入者に限定されてしまうため、売却の難易度が高くなってしまいます。
長屋は、住戸同士が壁を共有する形で一体化して建てられているため、一戸だけを切り離して売却・解体することが非常に困難です。たとえ土地が分筆されていたり、建物が個別に登記されていたとしても、建物構造が隣接住戸と連続している場合は、単独での解体や改修に重大な制約が伴います。
たとえば解体の際には、隣戸の壁や屋根に影響が及ぶ可能性があり、隣人の同意や追加の補修工事が必要になるケースも少なくありません。
こうした構造的な独立性の低さも、流通市場での評価を下げる要因となり、買主から敬遠されやすい理由の一つとなっています。
長屋では、敷地や建物が共有名義となっているケースが少なくありません。
民法第251条では、「共有物の変更は、共有者全員の同意によって行う」ということを定められており、共有部分に関わるリフォームや解体、賃貸などの重要な変更を行うには、すべての共有者の同意が必要です。
つまり、共有名義の場合、自分の所有部分を取り壊すような場合でも、隣接する住戸の所有者が同意しなければ手続きを進めることができません。
こうした制約が売却活動の足かせとなり、売却に時間がかかる、あるいは交渉が難航する原因となることもあります。
長屋の中には、建築基準法第43条で定められた接道義務を満たしておらず、再建築が法律上認められない「再建築不可物件」となっているケースがあります。
接道義務とは、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、新たに建築できないという規定です。特に古い長屋では、路地状の敷地や私道に面していることが多く、この要件を満たせないケースが見られます。
再建築不可物件は、住宅ローンの審査で不利になりやすく、将来的な新築や建て替えもできないため、資産価値が低く評価され、買主から敬遠される傾向にあります。そのため、売却活動が長期化したり、買取価格が大幅に下がったりするリスクにも注意が必要です。
長屋は築年数の古い物件が多く、経年劣化による老朽化が問題となることがあります。
特に古い長屋では、現行の耐震基準を満たしていないケースが多く、水回り、屋根、外壁、基礎部分、耐震補強など、広範囲にわたる修繕が必要になる可能性があります。これらの改修には数百万円規模のコストがかかることもあり、買主にとっては大きな負担です。
そのため、買主はリフォームや補修が前提となる物件を敬遠する傾向があり、結果として売却価格が下がる要因にもなります。
国土交通省の令和5年度住宅市場動向調査によると、既存(中古)住宅にした理由として、「リフォームされてきれいだったから」が29.1%、「リフォームで快適に住めると思ったから」が24.4%と、多くの買主がきれいな状態での入居を希望していることがわかります。(P.209「(6) 既存(中古)住宅にした理由」より)
老朽化が進んだ長屋を売却する際には、修繕を実施するか、現況のまま価格を下げて売り出すといった判断が求められます。
長屋を売却するには、物件の特性に合った方法を選ぶことが重要です。売れにくい場合でも、適切な対処法を取ることで、売却の可能性を高めることができます。この章では、4つの売却方法を紹介します。
長屋の売却を成功させるためには、長屋の取扱い実績が豊富な不動産会社に依頼することが重要です。
長屋は構造や権利関係が複雑で、再建築不可や共有名義といった特殊事情を抱えるケースも多いため、一般的な不動産会社では対応が難しく、売却が長引くことがあります。
そのため、過去に長屋の売却実績がある会社や、再建築不可物件の取扱いに強い専門業者、地域に精通した地元密着型の会社を選ぶことがポイントです。こうした業者は、物件の特性を理解し、適切な価格設定や販売戦略を提案してくれます。
ただし、広告範囲が限定的な場合や、仲介手数料が割高な場合もあります。
Point:売却の確実性を重視するなら、専門性の高い業者の活用が効果的です。
長屋は1戸単位での売却が難しいケースが多いため、他の住戸を買い取って「一棟まるごと売却」する方法も有効です。構造上の分離問題や再建築不可物件に伴う制限も解消しやすくなり、物件としての市場価値が高まります。
特に、収益物件として運用を検討している投資家にとっては、一棟で所有できる点が魅力的に映るため、購入意欲を引き出しやすくなります。
デメリットは、他の所有者との交渉が必要で、買い取り費用や時間がかかることです。また、全住戸を取得できる保証はないため、計画が頓挫するリスクもあります。
Point:長期的な資産整理や売却価格を高くしたい人には、有力な選択肢といえます。
隣の住人に買い取ってもらう方法も有効です。
隣人が複数戸を所有することで、リフォームや建替えの自由度が高まり、将来的な活用の幅が広がるため、隣人にとってもメリットの大きい取引となります。
お互いに顔見知りである場合も多いため、話がまとまりやすければ、不動産会社を通さずに早期売却が実現できる可能性もあります。
一方で、隣人に購入意思がない場合は成立しない、適正価格での取引がしづらいなどのデメリットもあります。
Point:長屋特有の構造を活かした現実的な売却手段の一つとして、まず隣人に声をかけてみる価値は十分にあるでしょう。
長屋がなかなか売れない場合や早急に現金化したい場合に、不動産買取業者に売却する方法は有効な選択肢です。
買取業者は現況のままで物件を買い取ってくれるため、リフォームや修繕の手間が不要で、契約から現金化までのスピードも早いのが特徴です。再建築不可物件や老朽化が進んだ長屋など、一般の買主が敬遠しがちな物件でも引き取ってもらえる可能性があります。
デメリットは、相場よりも安い価格での買取となるケースが多いため、価格面での妥協が必要になる点です。
Point:早期売却・手間削減・確実性を重視する人には、現実的で効果的な手段と言えます。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
長屋に特化した統計はありませんが、国土交通省の不動産情報ライブラリにある「地価公示」を参照すると、都市部と地方では土地価格に大きな差があることがわかります。この地価を基礎とし、実際の不動産取引価格情報や中古住宅市場の動向を踏まえると、長屋の売却相場は都市部で数千万円、地方では数百万円程度が実態に近い水準と言えるでしょう。
ただし、再建築不可物件の場合、土地価格より2〜5割程度安く評価されることが多く、実際の売却価格も大きく下がる傾向にあります。
売却価格に影響を与える要素としては、接道条件、建物の老朽度、法的制限(再建築の可否)、共有部分の有無、周辺環境(駅距離・治安・インフラ整備など)などがあります。長屋は構造上の制約が多いため、一般的な戸建て住宅と比べて評価が厳しくなりやすい点に注意してください。
なお、不動産ポータルサイトでは「長屋」と明記された売却事例が少ないため、近隣の「再建築不可物件」や「古家付き土地」の売出価格を参考にすることで、より実態に近い相場を把握しやすいでしょう。正確な価格を知るためには、複数の不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。
再建築ができない物件は、住宅ローンが利用しにくく、買主が限られるため、売却価格も相場より大きく下がる傾向にあります。再建築不可物件に該当する長屋を所有している場合、次のような対処法を検討しましょう。
物件の状況に応じて、柔軟な対応と専門的なサポートを活用することが重要です。
長屋は構造や法的制限が特殊なため、売却の難易度に大きな差が出ます。以下のチェックリストに「はい」または「いいえ」で答えて、あなたの長屋が売却しやすい物件かどうかをセルフ診断してみましょう。
【診断結果】
「はい」が 8個以上:売却は比較的スムーズに進む可能性大。相場を確認し、早めの売却活動をおすすめします。
「はい」が 4〜7個:条件によっては売却可能。修繕や専門業者への相談など、改善できる点を整理して対策を検討しましょう。
「はい」が 3個以下:売却は難航する可能性があります。買取業者への相談や隣接住戸との協議など、現実的な対処法を検討しましょう。
長屋の売却には、特有の課題が伴います。特に、接道義務を満たしていない再建築不可物件や、共有名義、老朽化による修繕負担、構造上一部だけを切り離せない点などが、売却が難しいとされる主な理由です。
しかし、長屋の取扱いに強い不動産会社への依頼、隣人や他住戸を買い取っての一棟売却、買取業者への売却など、状況に応じた対処法を選ぶことで売却の可能性を高めることができます。
相場の目安としては、都市部で数千万円、地方では数百万円程度ですが、再建築不可や接道条件などの要因により、相場より2〜5割程度安くなるケースも少なくありません。
正確な価格を把握するためには、複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。
