
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
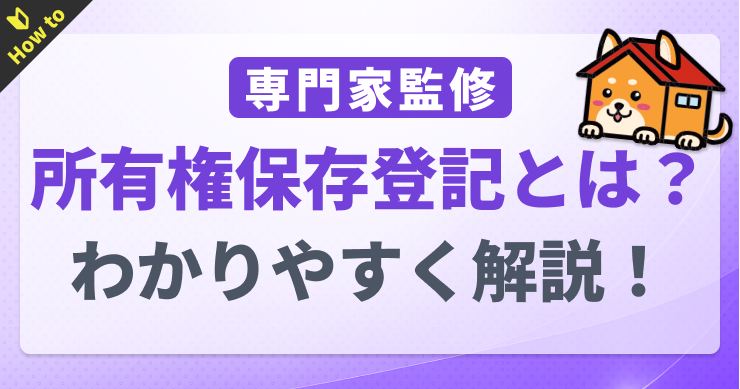
「保存登記って何?」「手続きが複雑そうで不安」と感じたことはありませんか?
建物を新築したとき、最初に行う登記手続きが「所有権保存登記」です。
この記事では、所有権保存登記の基礎知識から費用目安、自分で手続きできるかどうか、登記を行わなかった場合の影響まで、わかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
建物や土地を新しく取得したとき、最初に行う登記が「所有権保存登記」です。所有権保存登記は、不動産の所有者としての権利を公的に証明するための手続きであり、登記簿に「誰が最初の所有者であるか」を記載する役割を担います。所有権移転登記と異なり、前所有者が存在しない新築建物や分譲マンションの登記で利用されるのが特徴です。
所有権保存登記を行わないと、住宅ローンの抵当権を設定できなかったり、売却時に手続きが煩雑になったりする可能性があります。そのため、不動産を取得した直後には、できるだけ早めに所有権保存登記を行うことが重要です。この登記は不動産登記法に基づいて管理されており、正確な権利関係の把握に欠かせない制度です。
【専門家(監修者)が解説!保存登記の重要ポイント】
保存登記は「不動産登記法第74条に基づく法的手続きであり、登記名義人(所有者)本人によって申請される必要があります。
実務上では、住宅ローンを組む際に銀行が「保存登記の完了」を融資の条件とするケースも多いです。そのため、「登記が済んでいないので融資が実行できない」という例も少なくありません。また、建売住宅などの場合は、ハウスメーカーや不動産会社が代行して保存登記を行っていることもあります。
司法書士としての実務経験上、「保存登記を怠ったまま相続が発生し、通常の相続登記に加えて煩雑な手続きや追加書類が必要となり、時間や費用が余計にかかってしまった」という事例も複数見られます。
将来の相続や売却手続きに支障をきたさないよう、建物完成後はできるだけ早く保存登記を行うことが重要です。
保存登記を行う際には、主に「登録免許税」と「専門家(司法書士)への報酬」が発生します。
新築住宅の登記などでは、費用を抑えるために自分で登記する人もいれば、手間を省くために司法書士へ依頼する人も少なくありません。登記にかかる費用は、建物の評価額や依頼先によって変動します。
費用を正確に把握するためには、建物の固定資産評価証明書や見積書を確認し、管轄の法務局または専門家に事前相談することが重要です。
登録免許税とは、不動産登記にかかる国税であり、法務局に納める必要があります。所有権保存登記の場合、基本的な税率は「固定資産評価額×0.4%」です。ただし、特例措置による軽減が適用されるケースもあります。
なお、「固定資産評価額」と「購入価格」は異なる点に注意が必要です。登記費用を計算する際には、必ず固定資産評価額を基準としてください。また、新築住宅に対する軽減税率の有無も事前に確認しておきましょう。
司法書士に保存登記を依頼する場合は、手数料として報酬が発生します。報酬額は依頼する地域や司法書士事務所によって異なりますが、一般的な相場は2万〜6万円程度です。この費用には、必要書類の取得代行や申請代行などのサービスが含まれます。
依頼前に見積書を取り、費用明細を確認しておくと安心です。依頼先によってはセット料金を提示している場合もあり、コストを抑えることも可能です。
【専門家(監修者)が解説!保存登記の重要ポイント】
登録免許税に関しては、「租税特別措置法第73条」に基づき、住宅用家屋に該当する場合は軽減税率が適用されます。
ただし、「評価額が記載されていない」などの理由で、申請時に戸惑うケースも少なくありません。そのため、申請前に市役所などで固定資産評価証明を取得し、評価額と課税標準を確認しておくことが重要です。
また、司法書士への報酬については、事前に「見積書の内訳を出してもらう」ことがトラブル防止に役立ちます。実務では、依頼者が「報酬以外の費用が別途かかるとは知らなかった」と不満を持つケースも見られます。
保存登記にかかる費用は、金額の大小だけでなく、「何に対して支払っているのか」という内訳の透明性がポイントになります。
保存登記を行うには、法務局へ必要書類を提出し、所定の手続きを行います。基本的な流れとしては、事前に書類を揃え、登記申請書を作成し、申請書類一式を窓口に提出する、という段取りになります。登記手続きの正確性と、提出書類の整合性が重要です。
手続きをスムーズに進めるためには、提出先となる法務局の管轄確認や、登記簿に記載する情報の正確な記入が求められます。書類に不備があった場合は差し戻されることもあるため、慎重に準備しましょう。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
保存登記は自分で申請することも可能です。特に費用を抑えたい場合や登記内容がシンプルな場合には、自力で登記する人も少なくありません。ただし、必要書類や記載内容にミスがあると、手続きに時間がかかる可能性もある点には注意が必要です。
登記手続きに不慣れな方にとっては、内容が難しく感じることもあります。そのため、登記経験者のブログを参考にしたり、法務局の窓口でサポートを受けたりするのも有効です。初めての登記の場合は、事前に申請書のひな形や記入例を確認してから申請に臨むのが安心です。
【手続きをスムーズに進めるポイント】
保存登記を行わなくても、法律上ただちに罰則が科されることはありません。しかし、登記をしていない状態では第三者に対して所有権を主張できず、不動産取引上のリスクが大きくなります。特に、住宅ローンの利用や売却・贈与を予定している場合、保存登記の未実施は大きな障害になります。
保存登記は「自己の権利を守るための盾」としての役割を果たします。取得した不動産に対しては、速やかに登記を済ませておくことが、トラブルの予防やスムーズな資産活用につながります。特にローンや売却などの取引予定がある場合は、登記が事実上の「必須条件」になることを認識しておきましょう。
【専門家(監修者)が解説!保存登記の重要ポイント】
保存登記を怠ってトラブルとなった代表的な例が、「第三者への対抗問題」です。たとえば、不動産を購入したAさんが保存登記をせずにいたところ、売主が同じ建物を第三者のBさんに再度売却・登記してしまい、登記簿上はBさんが正当な所有者と見なされたというケースがあります。このような場合、未登記のAさんは所有権を主張できず、大きな損害を被ります。
また、住宅ローンの審査時にも、保存登記がされていない建物は、登記簿が存在しないため抵当権を設定できず、金融機関は担保価値を認められません。そのため、住宅ローンの審査に通らない、または融資を受けられないという事態につながる可能性があります。
保存登記は、所有権の法的安定と不動産の実務運用において、不可欠な手続きであるといえます。
建物の保存登記を行う際には、その建物が建っている土地に関する情報の提出が必要です。これは、建物は土地と不可分な関係にあり、建物の所在を正確に記録するためには、土地の情報による補完が不可欠であるためです。特に法務局では、登記の対象となる建物が実在し、かつその土地に正当に存在しているかを確認する必要があります。そのため、以下のような理由から土地の情報が必要です。
このように、土地情報は登記の正確性と信頼性を確保するために重要です。法務局で保存登記の申請を受理してもらうためには、土地の登記事項証明書や地積測量図などの添付書類が求められるケースがあります。建物単体ではなく、「建物と土地の一体性」を前提とした情報提出が求められる点に注意しましょう。
所有権保存登記は、新築や未登記の不動産に対して最初に行う、基本的かつ重要な登記です。正しく行うことで、所有権を法的に証明でき、住宅ローンや将来の売却・相続にも対応しやすくなります。費用面では、登録免許税と司法書士への報酬が中心となり、登記の正確性には、土地情報も不可欠です。
不動産を資産として有効活用するには、まず所有権を登記簿に確実に記録することが出発点となります。少しでも不明点があれば、司法書士や法務局などの専門機関に相談し、適切なタイミングで手続きを行うようにしましょう。
