
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
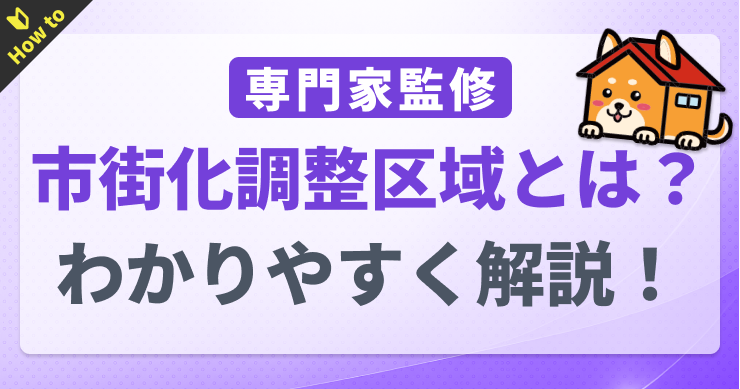
この記事では、市街化調整区域の概要と、該当区域の売買をする前に知っておきたい注意点・ポイントをわかりやすく解説します。
「市街化調整区域」とは、農地や森林などを守るために、開発を制限した地域です。
建築や開発が原則として禁止されており、住宅や施設を建てる場合には厳しい条件をクリアしなければいけません。
市街化調整区域とよく対比されるのが「市街化区域」です。市街化調整区域と市街化区域には、以下の違いがあります。
| 比較項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
| 定義 | すでに市街地となっている、または今後10年以内に市街地として発展させる区域 | 市街地化を抑制し、無秩序な開発を防ぐ区域 |
| 目的 | 計画的に都市を発展させ、住宅や商業施設を整備する | 農地や自然を守り、都市の無秩序な拡大を防ぐ |
| 建築・開発のしやすさ | 原則として自由に建築・開発が可能 | 原則として開発・建築は制限される(特例あり) |
| 許可が必要な開発 | 一定規模以上の開発には許可が必要だが、基本的に建築可能 | 住宅や店舗の建設には原則として開発許可が必要 |
| 用途地域の指定 | 用途地域が設定され、住居・商業・工業などの区分がある | 基本的に用途地域の指定なし(開発が制限されるため) |
| 主な土地利用 | 住宅地、商業地、工業地、公園など多様な用途 | 農地、森林、工場、公益施設(学校・病院など) |
| インフラ整備 | 道路・水道・下水道などの都市インフラが整備されている | インフラ整備が不十分なことが多い |
| 土地の価値 | 市街地のため、一般的に土地の価値は高い | 開発制限があるため、土地の価値は比較的低い |
| 具体例 | 駅周辺の住宅地や商業エリア | 郊外の田園地帯や山林、工場が点在する地域 |
簡単にいえば、市街化調整区域は「農地や自然を守るため」の区域、市街化区域は「都市を発展させるため」に定められた区域という違いがあります。
市街化調整区域かどうかをすぐに知りたい場合は、該当する市区町村の「都市計画課」などの担当窓口に電話で問い合わせるのが、確実でスピーディーな方法です。
ただ、「電話で問い合わせるのはちょっと面倒」「平日には連絡しづらい」という方もいると思います。そのような場合は、市区町村が公式サイトで公開している「都市計画図」からでも調べられます。
具体的な手順は以下の通り。
購入検討している土地があり、調整区域かどうかを調べる必要がある場合は、このような方法で確認しましょう。
市街化調整区域は、5年ごとに実施される都市計画基礎調査の結果によって見直しが行われます。
町の人口増減や防災強化・自然保護の観点から、以下の判断が下されます。
審議にさらに1年ほどかかるため、市街化調整区域は5~6年間隔で見直されると覚えておくとよいでしょう。
市街化調整区域には、大きく分けて以下の3つの特徴があります。
「安価でありながら、建築や居住のハードルは高い」という点が、市街化調整区域の最大の特徴といえるでしょう。それぞれのポイントについて、以下でもう少し詳しく解説していきます。
市街化調整区域の特徴として、土地価格が安いことが挙げられます。
市街化調整区域は、住居・商業施設の建築や建て替えが制限されるなど、用途が限られているため、市街化区域の土地と同じ値段では買い手がつかないからです。
価格は、市街化区域の同じ広さの土地に比べて、7~8割程度となるのが通常です。
水道や電気・道路などのインフラが整っていない土地では、価格が5割前後となる場合もあります。
土地価格が安いため相続税や固定資産税も比較的安いですが、資産としての価値も低くなってしまう点には注意が必要です。そのため、ローンの担保などには不向きです。
また、購入後は、都市計画税が課税されないため、ランニングコストが抑えられることがメリットといえます。ただし、条例で定める区域には課税されることがあります。
原則として、新築・建て替えを問わずマイホームを建てられない点も、市街化調整区域の特徴です。
都市計画法第三十四条で、市街化調整区域の開発は条件を満たしていなければ、都道府県知事は開発許可をしてはならないとされています。
制限されている理由は、主に以下の2つです。
ただし、市街化調整区域でのマイホーム建築は、完全に禁止されているわけではありません。
以下の条件のうちいずれかを満たしていれば、マイホームの建築は可能になります。
市街化調整区域の特徴として、インフラ整備や便利な施設が整っていないことも挙げられます。
これは、多くの市街化調整区域の土地は、農地・山林にあり、市街地から離れているためです。
学校や駅・スーパーなどが近くにないだけでなく、そもそも電気・水道・道路が通っていないこともあります。
そのため、市街化調整区域をマイホームなどに活用する場合は、実費でインフラを整えなければならないケースもあります。
市街化調整区域の土地の活用を検討する場合、土地の価格だけでなく、初期費用やその後の出費にも目を向けることが重要です。
本章では、市街化調整区域にマイホームを建てるための、4つの方法を詳しく紹介します。
土地活用をしたい方は、ぜひ参考にしてください。
市街化調整区域にマイホームを建てる方法として、自治体からの開発許可が挙げられます。
許可がない者は特定の条件を満たしている場合以外、新たにマイホームは建てられないと、都市計画法第三十四条で定められているためです。
しかし、自治体に申請を出しても、特別な事情がなければ許可は得られません。
実際に建築許可が得られた例としては、以下のようなケースが多く見られます。
一般的な市街化調整区域での開発許可申請は、以下のステップで行います。
開発許可を受けるには、各自治体に設定された取り扱い規準や、まちづくり条例などの規定を守らなければいけません。また、開発許可申請の準備から許可までは、早くても3ヵ月、長引くと1年以上かかる場合もあります。
※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
こんな悩み、抱えていませんか?
こうした悩みがある場合は、手軽に試せる不動産一括査定がおすすめです。
今の家がいくらで売れるか不安で、新しい住まい探しに踏み切れない
税金や名義変更の手続きも含め、何から始めればいいのか分からない
会社によって売却額が数百万円変わると聞き、選び方で損をしないか心配
簡単な質問に答えるだけで最大6社があなたの物件価値をしっかり査定します。その中から「信頼できる一社」を見つけて理想的な不動産売却を実現させましょう。

農業・林業・漁業を営む方は、市街化調整区域にマイホームを建てられる可能性があります。
これは、都市計画法第二十九条により、市街化調整区域でも、農業・林業・漁業を営む者の住居は、開発許可を得ずに建築できると認められているためです。
農業・林業・漁業に就労している証明は、市町村の役場や漁協で取得できます。自身が開発許可を得ずに建築できるのか、自治体に確認を行いましょう。
実際に、自己の事業を支えるための居住であり、経営規模もある程度大きいケースでは、建築できている事例があります。
ただし、自分の事業と関係ない家や、家庭菜園のみの場合は認められないため注意が必要です。
また、建てられるのは就労している方のマイホームであって、他人の家や寮・別荘は建てられないことも覚えておきましょう。
市街化調整区域にマイホームを建てる方法として、宅地利用が認められた土地の活用も挙げられます。
地目が宅地となっている土地は、建築許可のみでも自己の専用住宅や分家住宅、住宅兼用店舗を建築できるためです。
宅地利用が認められた土地は、市街化区域に隣接していたり、すでに50戸以上の家が建っていたりする地域によく見られます。
土地の地目は、登記簿謄本と固定資産税評価証明に記載されています。登記簿謄本と固定資産税評価証明に食い違いがあるケースもあるため、なるべく両方を確認しておきましょう。
不動産業者が開発許可を取得している土地に建てることも、市街化調整区域でマイホームを持つ方法です。
不動産業者がすでに水道・電気・道路などインフラを整備し、分譲住宅地として販売をしている土地の場合、購入すればすぐにでもマイホームを建てられます。
土地を所有しておらず、新たに購入しなければいけない場合におすすめです。ただし、市街化調整区域内での分譲住宅は珍しく、タイミングも場所も丁度よく見つかることは少ないのが現状です。
不動産業者が開発許可を取得している土地かどうかを調べるには、役所の開発指導課で聞いてみましょう。開発許可が下りている場合は、開発行為の内容が示された開発登録簿が取得できます。
本章では、市街化調整区域を購入する際に注意すべきポイントを4つ紹介します。
市街化調整区域の購入を検討している場合には、「目先の価格の安さ」だけでなく、「長期的な損益」を意識することをおすすめします。
参考:市街化調整区域の土地買取で失敗しない!高額で売却するための完全ガイド| GreenEnergy&Company
市街化調整区域の購入の際に注意すべきポイントとして、土地の地目が挙げられます。
地目が宅地か農地かによって、建築のしやすさが大きく異なるためです。
地目が農地になっていると、家や太陽光発電所などに活用するのに「農地転用」を行わなければいけません。
しかし、市街化調整区域内での農地転用は、原則不許可とされています。地目が農地の土地を購入しても、土地活用は不可能と思っておいた方がよいでしょう。
購入する際には、地目が「宅地」になっているかを確認してください。
市街化調整区域内にある建物が、線引き前のものか線引き後のものかを確認しておくことも重要です。線引きとは、区分けがなかった地域や市街化地域を、市街化調整区域に定めることをいいます。
| 線引き後の建物 | 線引き前の建物 | |
| 定義 | 市街化調整区域になった後に建てられた建物 | 市街化調整区域になる前に建てられた建物 |
| 建て替え | 建て替えがしづらい | 建て替えが比較的しやすい |
線引き後の建物は、建て替えの許可などに厳しい条件が設定されています。
一方で、線引き前の建物は、2001年に既存宅地制度が廃止され、許可こそ必要になったものの、比較的緩い条件で建て替えることができます。
市街化調整区域を購入する際には、いつ建てられたのかも確認しておきましょう。
市街化調整区域の土地を購入する際に注意すべきポイントとして、土地売却の際に不利になるリスクがあることが挙げられます。
住宅建築など開発の条件が市街化区域の土地に比べて厳しく、不動産会社によっては売買仲介を断られたり、安く買い叩かれたりしてしまうためです。
市街化調整区域の土地は、買い手がつかずに土地価格が下落する可能性も考えておかなければいけません。
そのため、購入する際は、開発の条件が緩和された調整区域を選ぶのがおすすめです。
たとえば、地目が宅地の土地や、線引き前の建物が建っている土地などは、開発条件が緩い傾向があります。
住宅ローンの審査が厳しくなることも、市街化調整区域の土地を購入する際に注意すべきポイントです。
住宅ローンの審査が厳しくなる理由は、以下の2つです。
住宅ローンを組めなければ、費用の関係上家を建てるのは困難です。
しかし、第三者でも家を建てられる土地は、住宅ローンの審査に通る可能性があります。担保としての価値が高まり、融資のリスクが低下するためです。
農林漁業従事者しか家を建てられない、分家しか建てられないなどの土地は、審査がほとんど通らないので覚えておきましょう。
市街化調整区域で住宅を建てられない土地でも、以下の3つへの活用で収益化が目指せます。
ただし、土地の地目が「農地」の場合は、農地転用の許可が必要です。転用の許可が下りない場合、このような活用をすることはできないため、注意してください。
市街化調整区域の活用例として、駐車場やコインパーキングが挙げられます。
都市計画法第29条では、屋根や壁を設けるなどして建築物にならない限り、原則許可を得ずに建設できるとされています。
特に、工場地帯や大型施設・駅に隣接する市街化調整区域の土地であれば、駐車場としてのニーズが期待できます。月極駐車場や時間貸しパーキングに活用すると、安定した収入を得られるようになるでしょう。
ただし、アスファルト舗装やライン引き、照明設備の導入などを行う場合は、初期費用や整備費用が必要です。
どのような設備が必要かは、収支とのバランスを見て決めてください。
墓地・霊園として、宗教法人や霊園業者に貸し出すことも、市街化調整区域の土地の活用例の1つです。
市街地よりも広い土地を安く確保できるため、市街化調整区域の地域を墓地・霊に選ぶケースは、全国でも多く見られます。
インフラ整備やクレーム対応が必要なく、安定した収入が得られるメリットがあります。
ただし、墓地にしてしまうと他の活用方法が難しいことや、資産価値が低下するデメリットは理解しておきましょう。
また、貸出先探しや近隣住民・市町村の許可も必要です。事前に行政手続きや規制を確認しておきましょう。
市街化調整区域の土地の活用例として、太陽光発電も挙げられます。
ソーラーパネルも建築物ではなく、開発許可はいらないためです。
人の往来が少なく交通が不便な地域でも、日照条件が確かであれば、売電収入によって安定した収益を得られるでしょう。
ただし、太陽光発電の初期投資は、150坪で1,200万円ほどかかるのが一般的です。利回りや維持コストは慎重に精査しなければいけません。
また、農地転用をしてソーラーパネルを設置するには、通常の資料に加えて以下の添付も求められます。
提出書類が多いことを理解しておき、詳しくは太陽光発電設置を依頼する業者や、自治体に確認してください。
本章では、市街化調整区域に関するよくある質問を2つ紹介します。
自分の望む土地活用のために、ぜひお読みください。
市街化調整区域では、建て替えや増築も制限されます。
建物の建築は自治体の開発許可がなければ不可能であり、市街地に比べて容積率や建ぺい率、建て替えの規模にも制限がかかっています。
ただし、条例で建て替えや増改築を認めている地域もあるため、事前に土地ごとに確認しておくのがおすすめです。
特に、「古民家を買ってリフォームしよう」と考えている方は、気をつけてください。売買により所有者が変わった場合の建て替えは、許可が下りないケースも考えられます。
市街化調整区域に家を建てるメリットは、以下の3つです。
市街化調整区域の土地は市街化区域の土地の7~8割の価格で販売されており、固定資産税も同様に安く設定されています。また、都市計画税の負担もありません(一部地域を除く)。
市街地から離れた場所では周辺の開発も行われないため、騒音がなく、建物に景色が遮られる心配もありません。
市街化調整区域とは、住居や商業施設の建築が制限されたエリアです。
都市の無秩序な拡大を防ぎ、農地や自然環境・都市機能を守るために設けられています。
市街化調整区域の土地に建築するには、いくつかの厳しい条件をクリアしなければいけません。
なにも知らずに購入・活用すると、無駄なお金を使っただけに終わる可能性もあります。
ただし、知識さえあれば費用を抑えて住居や商業施設を建てたり、駐車場などで安定収入を得ることもできます。
地目やインフラ・保留制度などに注目して、市街化調整区域の土地を見てみましょう。
また、地域密着の不動産会社は、活用方法を知っている業者も多いので、場所や予算を伝えたうえで相談してみるのもおすすめです。
