
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
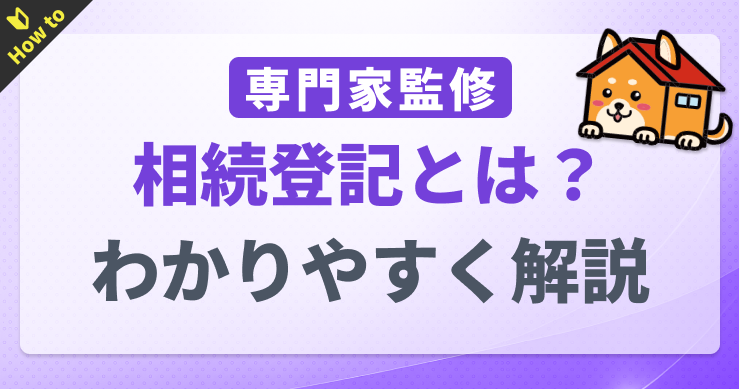
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続人は原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
この記事では、相続登記の全体像から具体的な手続きの流れ、費用までをわかりやすく解説します。相続登記であなたが「今すぐやるべきこと」が明確になり、安心して第一歩を踏み出せるはずです。
この記事でわかること
まず最も重要な「相続登記の義務化」のポイントから解説します。この法改正は、あなたに直接関係する非常に大切な内容です。
法務省の定めにより、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
原則として、「ご自身のために相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
多くの場合、「被相続人が亡くなったこと」と「ご自身が相続人であること」を知った日が起算点になるとお考えください。
もし、正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ご安心いただきたいのは、これは「罰金」という刑事罰ではなく、行政上の秩序を維持するための「過料」であるため、前科がつくことはありません。
しかし、無用な支出を避けるためにも、期限内に手続きすることが重要です。
また、法務省は「正当な理由」があれば、義務を免れるケースも示しています。たとえば、相続人が極めて多くて戸籍謄本の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性で争っている場合などがこれにあたります。
「義務化より前に発生した相続はどうなるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
この法律は、過去に発生した相続にも適用されます。
ただし、すぐに罰則の対象となるわけではなく、2024年4月1日から3年間、つまり2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。過去に発生した相続については、この期間内に相続登記を済ませれば問題ありません。
【監修者コメント】実家が祖父や曽祖父の名義のままになっている場合、ご自身が相続人だと気づいた時点から3年の期限がスタートします。まずは法務局で登記簿謄本を取得し、現在の名義人を確認することから始めましょう。
この章では、そもそも相続登記とは何なのか、なぜそれほど重要なのかについて、基本に立ち返ってご説明します。
相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を亡くなった方(被相続人)から、財産を受け継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。
不動産の所有者が誰であるかは、法務局が管理する「登記簿」に記録されています。この登記簿の情報を、現在の正しい所有者に書き換える作業が相続登記です。
2024年4月1日までは義務ではなかったため、相続登記をしないまま放置されるケースも少なくありませんでした。しかし、それには大きなリスクが伴います。
【監修者コメント】
手続きの先延ばしは、百害あって一利なし。「いつかやろう」は禁物です。私が担当した案件では、祖父の代の相続を放置した結果、孫の代で相続人が8人にまで増え、話し合いがつかずに裁判にまで発展してしまいました。
また、当該不動産が古ければ古いほど、所有者や関係者との接点が薄くなり、所在不明者も多くなります。相続登記が必要となることがわかった場合は、迅速に親族や関係者とコンタクトを取り、戸籍などの調査を進めておくことが重要です。
では、具体的に相続登記はどのように進めれば良いのでしょうか。
この章では、手続き全体の流れを5つのステップに分けて解説します。ご自身で進める場合は、2ヶ月〜半年程度の期間を目安にすると良いでしょう。
相続登記で最も時間がかかるとも言われるのが、この必要書類の収集です。本籍地の役所など、複数の場所に請求する必要があるため、計画的に進めましょう。
主な必要書類は以下の通りですが、遺言書の有無や遺産の分け方によって異なります。
【相続登記 必要書類チェックリスト】
| 書類名 | 取得場所 | 誰のものが必要か | 備考 |
| 登記申請書 | 法務局の窓口 / Webサイトでダウンロード | 申請人が作成 | ひな形は法務省のウェブサイトで公開されています。自分で作成または司法書士が作成します。 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 亡くなった方(被相続人) | 相続人を確定するために必須。複数の役所に請求することも多いです。 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続人全員 | 相続人が現在も生存していることを証明するために必要。 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場 | 亡くなった方(被相続人) | 登記簿上の住所と死亡時の住所をつなげるために必要。 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 新しく名義人となる相続人 | 遺産分割協議で不動産を取得しない相続人の分は不要。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(都税事務所) | 対象不動産 | 登録免許税を計算するために使用。最新年度のものが必要です。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 相続人全員 | 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要。原則として遺言書がない場合に作成します。 |
| 相続関係説明図 | 申請人が作成 | ― | 作成を推奨。提出すると、添付した戸籍謄本などの原本を返却してもらえます。 |
遺言書がない場合は、どの財産を誰が相続するのかを、相続人全員で話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
話し合いがまとまったら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名と実印の押印をします。
遺産分割協議がなかなかまとまらず、3年以内の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」をすることで、過料を回避することができます。相続人申告登記の費用は無料で、相続人が複数いても単独で申告することができます。
ただし、相続登記の義務が免除されるわけではないため、協議が成立したら正式に所有権移転登記を行いましょう。
【監修者コメント】
遺産分割協議では、財産の話の前に、まず故人の思い出話から始めてみてください。感情的な対立を避け、円満な話し合いを進めるためのコツです。お金の話から入ると、どうしても雰囲気が硬くなってしまいます。
必要書類がすべて揃い、遺産の分け方も決まったら、法務局に提出する「登記申請書」を作成します。
法務省のウェブサイトに、申請書のひな形や記載例が公開されているので、参照しながら作成を進めるのが良いでしょう。 不動産の情報を正確に記載する必要があるため、登記簿謄本や固定産評価証明書を手元に置いて作業してください。
次に、申請書と必要書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。申請方法は、窓口への持参、郵送、そしてオンライン(マイナンバーカードが必要)の3つがあります。
平日に時間が取れない方は郵送、パソコン操作に慣れている方はオンライン申請が便利です。
| 申請方法 | メリット(こんな人におすすめ) | デメリット(注意点) |
| 窓口申請 | ・その場で職員に質問できるため安心感がある
・書類の不備をその場で指摘してもらえる可能性がある → 初めての手続きで不安な方、法務局が近くにある方におすすめ |
・法務局の開庁時間(平日の日中)に行く必要がある
・混雑していると待ち時間が長い ・遠方の場合は交通費と時間がかかる |
| 郵送申請 | ・24時間いつでも自分の都合で発送できる
・法務局に行く必要がない → 平日は忙しい方、法務局が遠方にある方におすすめ |
・質問ができず、書類に不備があると郵送でのやり取りになり時間がかかる
・「書留郵便」で送り、返信用の書留郵便封筒も同封する必要がある |
| オンライン申請 | ・24時間いつでも自宅から申請できる
・登録免許税が安くなる場合がある(※条件あり) → パソコン操作に慣れている方、初期設定の手間を惜しまない方におすすめ |
・マイナンバーカードとICカードリーダライタ(または対応スマホ)が必須
・専用ソフトのインストールと操作が複雑で、初心者にはハードルが高い ・一部の書類(戸籍謄本など)は別途郵送する必要がある |
申請書に不備がなければ、申請から約1週間〜2週間で登記が完了します。
登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」という新しい権利証が発行されます。これは非常に重要な書類なので、絶対に紛失しないように大切に保管してください。
以上で、相続登記の手続きはすべて完了です。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。
手続きを進める上で、費用がどれくらいかかるのかは気になるところだと思います。費用は大きく分けて「必ずかかる実費」と、専門家に依頼した場合の「司法書士報酬」の2つがあります。
ご自身で手続きを行う場合でも、以下の費用は必ず発生します。
仮に、相続する不動産の固定資産税評価額が合計で3,000万円だった場合の、具体的な費用感を比較してみましょう。
| 費用項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼する場合 | 備考 |
| ① 登録免許税(実費) | 120,000円 | 120,000円 | 固定資産税評価額 3,000万円 × 税率0.4% |
| ② 必要書類 取得費用(実費) | 約 10,000円 | 約 10,000円 | 戸籍謄本や住民票などの取得費用。相続人の数により変動します。 |
| ③ 司法書士報酬(専門家費用) | 0円 | 約 100,000円 | 書類収集、遺産分割協議書作成、申請代理など一式を依頼した場合の一般的な報酬額。 |
| 合計費用 | 約 130,000円 | 約 230,000円 | 専門家に依頼すると、実費に加えて報酬が必要になります。 |
費用を抑えるためにご自身で手続きを行うことも可能ですが、以下のようなケースでは、司法書士への依頼をおすすめします。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。やるべきことが多くて、何から手をつければ良いか、まだ少し混乱しているかもしれません。
ご安心ください。あなたが今、最初にやるべきことは、たったの2つです。
まず、「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。
そのために、亡くなった被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」一式を取得してください。これにより、ご自身が知らなかった相続人がいないかなどを正確に確認できます。
次に、「何を相続するのか」という財産の全体像を把握します。
不動産については、市区町村の役場で「名寄帳(なよせちょう)」の写しを取得しましょう。これにより、被相続人がその市区町村内に所有していた不動産の一覧を確認できます。
相続手続きは、多くの方にとって初めての経験です。一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることも、賢い選択肢の一つです。
多くの司法書士事務所では、初回無料の相談窓口を設けています。まずはそうした場で、ご自身の状況を話し、専門家のアドバイスを聞いてみるだけでも、頭の中が整理され、次の一歩が明確になるはずです。
あなたの相続手続きが、トラブルなく円満に進むことを心から願っております。
参考文献
法務省: 相続登記の申請義務化に関するQ&A – 法務省, (参照日: 2025-07-02)
法務省: 不動産登記の申請書様式について – 法務省, (参照日: 2025-07-02)
国税庁: No.7191 登録免許税の税額表 – 国税庁, (参照日: 2025-07-02)
