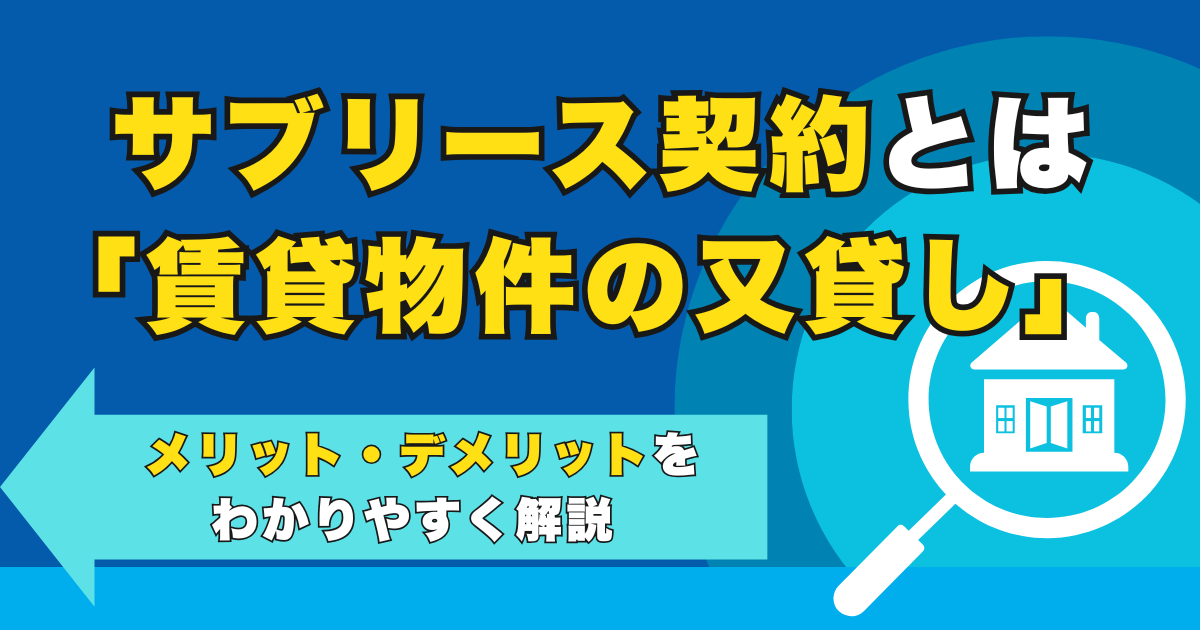
-
サブリース契約とは「賃貸物件の又貸し」 | メリット・デメリ...

「根抵当権って何だろう?」と、抵当権との違いや設定・抹消の手続きが分からず戸惑っていませんか?金融機関から根抵当権の契約を提案されても、メリットとリスクのバランスを判断しづらく、不安になる方も少なくありません。
この記事では、根抵当権の基礎知識から抵当権との違い、設定・抹消手続き、費用、注意点までをわかりやすく解説します。
根抵当権(ねていとうけん)は民法が定める担保物権の一つで、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた「極度額」の限度で担保するために設定できる抵当権です。
抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は、継続的取引などから生じる複数・将来の債権をひとまとめに担保できる点が特徴です。
たとえば、金融機関による事業資金の継続的な貸付など、継続・反復的な資金需要が想定される場面で活用されているよ!
根抵当権を設定する際には、契約で「担保すべき債権の範囲」と「極度額」を定める必要があります。
根抵当権で担保することができる債権の種類を指します。銀行における融資取引の場合には、「銀行取引契約に基づく一切の貸付債権」などとなり、契約内容により決まります(民法398条の2、不動産登記法83条)。
適切に担保の範囲と極度額を設定しておけば、同一内容の取引に基づく追加融資を受ける場合でも新たな抵当権設定登記をする必要がないため、抵当権の設定や抹消の手続きを何度も行う手間や登記費用の削減にもつながります。
ただし、担保範囲に含まれない債務には効力が及ばないため、契約内容を事前に確認することが重要です。
極度額は、担保となる不動産の評価額を上限に、その時点での金融機関の審査基準や、借入人の信用状況、返済能力、将来の借入計画などを踏まえて設定されますが、実際の貸出予定額は極度額の80%前後に抑えられるのが一般的です。
たとえば極度額が5,000万円でも、実際に借りられるのは4,000万円程度になります。これは、金融機関がリスクヘッジとして、極度額いっぱいの貸し出しを避けているためです。
根抵当権で実際に担保される債務群のことを、被担保債権といいます。担保されるのは契約で定めた一定の範囲に属する不特定の債権であり、包括的にすべての債務を担保することは認められていません。
取引中に追加融資が行われれば、その範囲に含まれる限り自動的に被担保債権に加わります。
被担保債権は「どの借入に根抵当権が及ぶのか」を示すもので、契約書に明確に記載されています。事業ローンなどを根抵当権で担保している場合、自分の借入がどこまで被担保債権に含まれるのかを確認しておくことが大切です。
抵当権は主に、住宅ローンのように反復、継続されない一度きりの借入などで活用されます。返済が終われば抹消できるため、個人の住宅購入では管理しやすいです。
一方で、根抵当権は、会社などが継続的な資金需要(仕入れや運転資金など)に対応する際に活用されます。一度設定すればその後の追加融資も同じ枠内で担保でき、新たに登記をせずに済むため、手間とコストを省けます。
| 比較項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保範囲 | 特定の債務 | 契約で定めた範囲内の継続的・将来の債務 |
| 登記変更 | 追加融資ごとに必要 | 原則不要。ただし、債務の範囲や極度額変更には登記が必要 |
| 元本確定 | 設定時に確定 | 債権者の請求などにより後日確定 |
| 実行手順 | 任意売却・競売 | 同左 |
抵当権は単発融資に向き、根抵当権は継続的な資金需要に対応できます。
根抵当権の最大の利点は、極度額の範囲内で繰り返し融資を受けられる点です。抵当権のように新たな契約や登記をその都度行う必要がないため、金融機関は事務負担を減らせ、債務者は迅速な資金調達が可能になります。
これらのメリットにより、運転資金を繰り返し借り入れる中小企業の事業融資や、不動産投資家が継続的な借り入れを行う場合などに活用されます。
そのため、継続的に融資を受ける場合には、根抵当権が適しているといえるでしょう。
根抵当権の注意すべきデメリットは、借り入れをすべて返済しても自動的に権利が消えるわけではないため、元本確定しなければ根抵当権の抹消登記ができず、担保として提供された不動産の売却は進められません。
この点、抵当権の場合はローンを完済できれば融資先の変更は比較的容易ですが、根抵当権の場合は、金融機関との交渉が必要となる場合があるため、心理的な負担や時間的なロスにつながることもあります。
根抵当権の設定手続きは、以下の流れで行います。
根抵当権の設定手続きの流れは抵当権とほぼ同じですが、契約書に「担保すべき債権の範囲」と「極度額」を明記する点が特徴です。
根抵当権設定には、以下の書類が必要になります。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 登記原因証明情報(根抵当権設定契約書) | 金融機関 |
| 根抵当権者(金融機関など)の資格証明書(発行から3か月以内のもの) | 金融機関など |
| 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) | 不動産の所有者 |
| 登記権利証または登記識別情報 | 不動産の所有者 |
書類に不備があると、法務局からの補正通知に対応する必要が生じるため、手続きが遅れる原因となります。
根抵当権の登記申請は、以下の順序で進めるのが一般的です。
申請後、補正連絡がなければ3〜5営業日で完了するケースが多いです。オンライン申請なら印紙代を電子納付でき、司法書士報酬が不要となるほか、窓口に出向く手間も省けます。
根抵当権の設定費用は、登録免許税と司法書士報酬が中心です。
| 費目 | 金額目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 極度額×0.4% | 例:極度額1000万円の場合、4万円 |
| 司法書士報酬 | 3〜6万円 | 極度額や不動産の数、依頼先で変わる |
| 登記事項証明書 | 600円/通 | 登記完了後に取得 |
費用を抑える場合は、極度額を実際の資金需要に見合った範囲に設定する、あるいは複数案件をまとめて同じ司法書士へ依頼し、手数料を調整してもらう方法があります。
不動産を売却したり、借換えを行うためには、根抵当権の抹消が必要です。根抵当権は、借り入れを完済しても自動的に消滅しないため、元本を確定させたうえで抹消登記を行う必要があります。
この章では、根抵当権の抹消手続きのタイミングや費用内訳を詳しく見ていきましょう。
「元本確定」は、根抵当権の効力が及ぶ範囲を確定させる手続きです。元本確定という手続きを経て、初めて新しい債務を担保しなくなります。確定後は通常の抵当権と同じ扱いになり、抹消登記が可能となります。
元本を確定させないと抹消登記ができず、売却や借り換えは進められません。元本確定通知書を金融機関から受領したら、速やかに抹消登記の準備を進めましょう。
抹消登記は、以下の流れで行います。
抹消登記の手続きの費用は、以下が目安になります。抹消手続きについてもオンライン申請が可能で、登記申請の場合と同様のメリットがあります。
| 区分 | 金額目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 登記申請する不動産1件につき1000円 |
| 司法書士報酬 | 1.5〜3万円 |
| 書類取得費 | 数千円 |
抹消登記は 申請後1~2週間ほどで完了することが多いですが、書類準備や金融機関の手配が重なると 、全体では4〜6週間ほどかかる場合もあります。
根抵当権は将来の借入も含めて一括で担保できる仕組みで、継続的な資金需要に対応する企業融資に適しています。ただし、元本が確定しないと抹消できないため、不動産の売却や借換えを予定する場合は、資産の流動性が制約されるリスクがあります。
有効に活用するには専門的な知識が必要なので、司法書士や金融機関に早めに相談し、契約内容や費用を十分に理解してから手続きを進めましょう。
実務では、中小企業の継続的な資金調達で根抵当権が広く活用されています。根抵当権の設定は将来の取引を見据えた重要な判断なので、制度の仕組みを理解したうえで、資金計画と合わせて利用を検討してください。
