
-
不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...
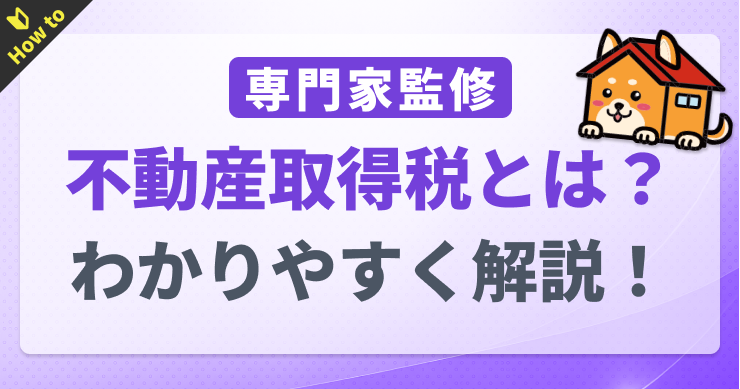
不動産を購入したときに「不動産取得税ってなに?どのくらい払うの?」と疑問に感じたことはありませんか?税金の仕組みは専門用語も多く、わかりにくく感じる方も少なくありません。
しかし、不動産取得税の場合、住宅用の不動産には軽減措置も適用されるため、適用条件などをしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産取得税について、以下のポイントをわかりやすく解説します。
不動産取得税の不安を解消し、安心してマイホームや土地の取得ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、都道府県が課する地方税のことです。購入(売買)だけでなく、贈与や交換、新築・増築によって不動産を取得した場合も課税対象となります。
不動産取得税は、登記の有無に関係なく、取得という権利移転の事実に対して課税されます。なお、相続による取得の場合は原則非課税となります(地方税法第73条の7)。不動産を取得するすべての人が対象となるため、事前にその仕組みを理解しておくことが重要です。
不動産取得税は、取得後に登記を行っていなくても、不動産の取得が確認されれば納税通知書が届く場合があります。これは課税対象が「権利移転そのもの」であり、登記はあくまで第三者対抗要件にすぎないためです。
不動産取得税は、地方税法 第73条の2に定められ、都道府県が課税主体となる地方税です。
売買・贈与と相続で課税関係が異なる点は、実務でも誤解を生みやすいポイントです。取得後の早い段階で、都道府県税の公式サイトや相談窓口を活用して確認しましょう。
不動産取得税は、土地や建物を購入したときだけ課税されるわけではありません。対価の有無を問わず、実質的に土地・建物を取得した場合は原則として課税されます。
具体的には、以下のような場合に不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、「登記の有無」や「対価の有無」にかかわらず、実質的な取得に対して広く課されます。特に注意したいのは、家族間の贈与や相続対策として行った場合です。
贈与で取得した不動産には取得税がかかりますが、相続の場合は非課税扱いになるため、取得経路の違いが税負担に大きく影響します。
不動産取得税は、実際の売買価格(契約金額)そのものではなく、「課税標準額」に税率をかけて計算されます。課税標準額は、各市区町村が決定する固定資産評価額を基に定められ、実際の売買価格よりも低くなることが一般的です。
さらに、住宅用不動産の取得などには軽減措置があり、非課税となるケースも少なくありません。
不動産取得税の基本的な計算式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税標準 | 固定資産税評価額(市区町村が算定) |
| 税率 | 原則4%(土地・住宅の場合は軽減措置で3%) |
| 軽減措置の有無 | 一定条件下で評価額の控除・税率軽減 |
| 納税額の計算式 | 課税標準 × 税率 − 各種控除額(軽減措置) |
たとえば、評価額2,000万円の新築住宅(建物)を取得し、住宅軽減措置(新築控除)1,200万円が適用された場合、不動産取得税は次のように計算されます。
課税標準額:2,000万円 − 1,200万円(新築控除) = 800万円
税額:800万円 × 3% = 24万円
売買契約書の価格(購入金額)ではなく、市区町村が算定した公的な評価額が基準となり、さらに、一定の条件を満たすことで軽減措置が適用される点が大きな特徴です。
なお、新築住宅が認定長期優良住宅の場合は、控除額が1,200万円ではなく1,300万円に拡充されます。
参照:総務省|不動産取得税
不動産取得税の課税標準に使われる「固定資産税評価額」は、各市区町村が3年ごとに総務省の「固定資産評価基準」に基づき見直します。評価額は実際の売買価格より3割程度低い水準になることが一般的です。
また、住宅用不動産に対する軽減措置は、地方税法附則第7条に定められており、新築住宅の建物部分には1,200万円(認定長期優良住宅の場合1,300万円)の控除が適用されます。住宅用土地にも、一定の面積要件を満たすことで控除が適用されます。
このような制度は、住宅取得者の税負担軽減を目的としており、都道府県の住宅政策にも大きく関係しています。実務では、評価額の誤認や軽減措置の適用漏れにより過大納税が発生することもあるため、取得後は都道府県税事務所の課税明細を確認することが重要です。
不動産取得税には、一定の条件を満たすと税負担を大幅に軽減できる「軽減措置」が設けられています。主にマイホーム取得者を対象とする制度で、要件を満たせば控除額の適用や税率の引き下げが受けられます。
軽減措置の仕組みは少し複雑ですが、事前に確認しておくことで、マイホーム購入の資金計画も立てやすくなるでしょう。
たとえば、新築住宅の建物部分では、評価額から1,200万円が控除されるほか、税率も4%から3%に軽減されます。中古住宅でも耐震性などの基準を満たしていれば軽減の対象になるため、事前に不動産会社や市区町村の担当窓口に確認しておくのがおすすめです。
新築住宅を取得した場合は、不動産取得税の軽減措置がもっとも手厚く適用されます。新築住宅に適用される軽減内容は以下になります。
| 軽減内容 | 詳細 |
|---|---|
| 建物の評価額控除 | 最大1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)控除 |
| 土地の控除 | 次のいずれか高い額を控除
①45,000円 ②土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積×2倍(200㎡/戸上限)×税率 |
| 税率の軽減 | 原則4% → 軽減後3% |
| 適用条件 | ・居住用であること ・住宅取得後6か月以内の居住開始 ・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
ただし、これらの条件を満たしていれば自動的に軽減措置が適用されるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きは基本的に都道府県事務所で行いますが、電子申請が可能な自治体もあります。
中古住宅を購入した場合でも、一定の条件を満たせば不動産取得税の軽減措置を受けることができます。築年数や耐震性などの要素が重視されるため、物件探しの段階から条件確認をしておくことが大切です。
築年数の要件は 「新耐震基準(昭和57年以降)」が基準です。旧耐震の住宅は「耐震改修」または「耐震診断」を行い、証明書を取得することで軽減対象にできます。
住宅用の土地を取得した際にも、不動産取得税の軽減措置が適用されます。以下の条件を満たせば、土地部分の課税標準は大幅に減額できます。
土地と建物を別々に購入した場合、土地に軽減措置が適用されるかは、土地・建物それぞれの取得したタイミングが関係する点に注意が必要です。
不動産取得税の軽減措置は、自動的に適用されるわけではなく、納税者自身が所定の手続きを行う必要があります。不動産を取得後、都道府県税事務所に対して、一定期間内(原則60日以内)に申請書と必要書類を提出するのが一般的です。
申請期限は、原則として取得日から60日以内となっていますが、自治体によって異なる場合があるため、事前に確認してください。期日を過ぎると、正当な理由がない限り軽減が受けられなくなる可能性があるため、早めの準備と手続きが肝心です。
なお、建物の種類(新築・中古)や土地の用途によって必要書類は異なるため、事前に都道府県の公式サイトで確認しておくと安心です。
不動産取得税の納税通知書は、不動産の取得後、おおむね4~6か月で都道府県税事務所から届きます。納付期限は通知書に記載されており、期限までに一括で納付するのが原則です。ただし、一括で支払うことができない合理的な理由がある場合、分納が認められることもあります。
納付時期と主な方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通知書の到着時期 | 不動産の取得(登記完了)後4〜6か月程度(都道府県により異なる) |
| 納付期限 | 納税通知書に記載された期日 |
| 支払方法 | 一括支払いが原則 |
| 分納の可否 | 所得状況などにより一括支払いができない合理的な理由があれば認められるケースあり |
| 主な納付手段 | 金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード、eLTAX経由のインターネットバンキング、スマホ決済アプリ ※自治体によって異なる場合あり |
納税通知書が届いたからといって即日支払う必要はありませんが、納付書に記載された期限を過ぎると延滞金が加算される可能性があるため、注意が必要です。通知書が届いたらすぐに内容を確認し、余裕をもったスケジュールで納付しましょう。
不動産取得税は、原則、すべての不動産取得に課されますが、法律上の「非課税」の扱いとなるケースもあります。
不動産取得税が非課税となる主なケース
| 区分 | 非課税・免除となる例 |
|---|---|
| 相続による取得 | 相続(遺産分割を含む)で取得した場合 ※ただし、法定相続人以外が特定遺贈により財産を取得する場合は非課税の対象外 |
| 公共の用に供する道路 | 不特定多数の人が通行する私道(公衆用道路)を取得した場合 |
| 土地区画整理事業など | 土地区画整理事業や市街地再開発事業によって、従来の土地と異なる土地を取得した場合(換地) |
| 法人の合併または分割 | 法人が組織再編により合併または分割するにともなって不動産を取得した場合 |
| 特定の法人による事業用不動産の取得 | 学校法人や宗教法人、社会福祉法人などが、事業を行うために取得する場合 |
非課税事由に該当すれば、納税通知書自体が送付されない場合もあります。納付書が届いた場合は、課税根拠に間違いがないか都道府県税事務所に確認してみると安心です。
不動産取得税は金額が大きくなることもあるため、納付期限までに一括で支払うのが難しいケースもあります。こうした状況を放置してしまうと、延滞税や財産の差し押さえといったリスクがあるため、早めに相談するのが最善の対策です。
不動産取得税を支払えない状況でも、早めに申し出て相談すれば、柔軟に対応してもらえることもあります。無視したり放置したりすると、財産の差し押さえや信用情報に影響しかねません。
納付が難しいと分かった段階で、速やかに都道府県税事務所へ相談することが最善の対処法といえるでしょう。
不動産に関連する税金には、「不動産取得税」以外にも「固定資産税」・「都市計画税」「登録免除税」など複数の税金があります。これらは課税のタイミングや納税者、税率の考え方が異なるため、混同しないよう整理して理解しておくことが大切です。
不動産取得税と他の代表的な税金の比較
| 税金の種類 | 課税のタイミング | 納税者 | 管轄先 |
|---|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を取得したとき | 取得した人 | 都道府県 |
| 固定資産税 | 毎年1月1日時点 | 毎年1月1日時点の所有者 | 市区町村 |
| 都市計画税 | 毎年1月1日時点 ※固定資産税と併せて納付 |
毎年1月1日時点の所有者 | 市区町村 |
| 登録免許税 | 不動産登記申請時 | 登記申請者 | 国税(法務局を通じて納付) |
固定資産税・都市計画税は、取得後も「保有」する限り毎年課される税金です。一方で、不動産取得税や登録免許税は、取得時や登記申請時のみ課税されます。
それぞれの税金が、どのタイミングで必要となるかを正しく把握しておくことで、購入後の資金計画を立てやすくなります。
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される地方税です。不動産を取得(登記完了)してから、4~6か月程度で届くのが一般的です。
ただし、住宅用の土地・建物では、税額の基準となる固定資産税評価額の控除や税率の軽減などの軽減措置が設けられており、非課税となるケースも少なくありません。制度を正しく理解することで、余分な支出を避けることができます。
不動産取得にかかる費用は税金も含めて大きな出費となるため、あらかじめ税金を含めた諸費用を、支払うタイミングも含めて把握しておくことが重要です。
特に、不動産取得税の場合、軽減措置の対象かどうかを早めに確認することで、購入後の資金計画にも余裕をもって対応できるでしょう。
